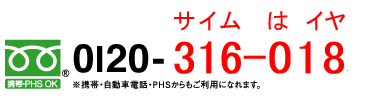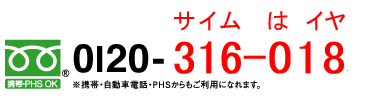平成22年6月1日/最高裁判所第三小法廷/判決/平成21年(受)17号
判例ID28161473
事件名/損害賠償請求、民訴法260条2項の申立て事件
裁判結果:破棄自判 /上訴等:確定 /
最高裁判所第三小法廷 平成21年(受)第17号 平成22年06月01日 主文
1 原判決中、上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
3 被上告人は、上告人に対し、4億5962万1587円及びこれに対する平成20年11月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 控訴費用、上告費用及び前項の裁判に関する費用は、被上告人の負担とする。 理由
第1 上告代理人小澤英明ほかの上告受理申立て理由第2及び第3について
1 本件は、上告人との間で売買契約を締結して土地を買い受けた被上告人が、上告人に対し、上記土地の土壌に、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして上記売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことから、このことが民法570条にいう瑕疵に当たると主張して、瑕疵担保による損害賠償を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
(1) 被上告人は、平成3年3月15日、上告人から、第1審判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を買い受けた(以下、この契約を「本件売買契約」という。)。本件土地の土壌には、本件売買契約締結当時からふっ素が含まれていたが、その当時、土壌に含まれるふっ素については、法令に基づく規制の対象となっていなかったし、取引観念上も、ふっ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず、被上告人の担当者もそのような認識を有していなかった。
(2) 平成13年3月28日、環境基本法16条1項に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められた平成3年8月環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)の改正により、土壌に含まれるふっ素についての環境基準が新たに告示された。
平成15年2月15日、土壌汚染対策法及び土壌汚染対策法施行令が施行された。同法2条1項は、「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう旨を定めるところ、ふっ素及びその化合物は、同令1条21号において、同法2条1項に規定する特定有害物質と定められ、上記特定有害物質については、同法(平成21年法律第23号による改正前のもの)5条1項所定の環境省令で定める基準として、土壌汚染対策法施行規則(平成22年環境省令第1号による改正前のもの)18条、別表第2及び第3において、土壌に水を加えた場合に溶出する量に関する基準値(以下「溶出量基準値」という。)及び土壌に含まれる量に関する基準値(以下「含有量基準値」という。)が定められた。そして、土壌汚染対策法の施行に伴い、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)115条2項に基づき、汚染土壌処理基準として定められた都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)56条及び別表第12が改正され、同条例2条12号に規定された有害物質であるふっ素及びその化合物に係る汚染土壌処理基準として上記と同一の溶出量基準値及び含有量基準値が定められた。
(3) 本件土地につき、上記条例117条2項に基づく土壌の汚染状況の調査が行われた結果、平成17年11月2日ころ、その土壌に上記の溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていることが判明した。
3 原審は、上記事実関係の下において、次のとおり判断して、被上告人の請求を一部認容した。
居住その他の土地の通常の利用を目的として締結される売買契約の目的物である土地の土壌に、人の健康を損なう危険のある有害物質が上記の危険がないと認められる限度を超えて含まれていないことは、上記土地が通常備えるべき品質、性能に当たるというべきであるから、売買契約の目的物である土地の土壌に含まれていた物質が、売買契約締結当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが、その後、有害であると社会的に認識されたため、新たに法令に基づく規制の対象となった場合であっても、当該物質が上記の限度を超えて上記土地の土壌に含まれていたことは、民法570条にいう瑕疵に当たると解するのが相当である。したがって、本件土地の土壌にふっ素が上記の限度を超えて含まれていたことは、上記瑕疵に当たるというべきである。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべきところ、前記事実関係によれば、本件売買契約締結当時、取引観念上、ふっ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず、被上告人の担当者もそのような認識を有していなかったのであり、ふっ素が、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは、本件売買契約締結後であったというのである。そして、本件売買契約の当事者間において、本件土地が備えるべき属性として、その土壌に、ふっ素が含まれていないことや、本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない。そうすると、本件売買契約締結当時の取引観念上、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されていなかったふっ素について、本件売買契約の当事者間において、それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれていないことが予定されていたものとみることはできず、本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても、そのことは、民法570条にいう瑕疵には当たらないというべきである。
5 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、被上告人の請求は理由がなく、これを棄却した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却すべきである。
第2 上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てについて
上告人が上記申立ての理由として主張する事実関係は、別紙「仮執行の原状回復及び損害賠償を命ずる裁判の申立書」(写し)記載のとおりであり、被上告人は、これを争わない。上記事実関係によれば、上告人は、平成20年11月26日、被上告人に対し、原判決に付された仮執行の宣言に基づき4億5962万1587円を給付したものというべきである。そして、原判決中上告人敗訴部分が破棄を免れないことは前記説示のとおりであるから、原判決に付された仮執行の宣言はその効力を失うことになる。そうすると、被上告人に対し、4億5962万1587円及びこれに対する給付の日の翌日である平成20年11月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人の申立ては、正当として認容すべきである。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 堀籠幸男 裁判官 那須弘平 裁判官 田原睦夫 裁判官 近藤崇晴)
東京高等裁判所 平成19年(ネ)第4169号 平成20年09月25日
1
売買契約の目的物である土地に含まれていた物質(ふっ素)が、当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが、売買契約後に有害であると社会的に認知された場合に、瑕疵が認められた事例。
2
第一審で自ら否定した主張を控訴審で提出した場合であっても、それが法的構成の誤りを正したにすぎないものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法の提出には当たらない。
同代表者理事 角田公
同訴訟代理人弁護士 荒木孝壬
同 梶山正三
被控訴人(被告) AGCセイミケミカル株式会社
同代表者代表取締役 安藤豊
同訴訟代理人弁護士 小澤英明
同 矢嶋雅子
同 河端雄太郎
同 渡邊典和
同(復代理人) 齋藤梓 主文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、4億4893万2750円並びにうち2368万2750円に対する平成18年11月5日から、及びうち4億2525万円に対する平成20年7月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを100分し、その3を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決は、第1項の(1)に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、4億6095万5250円及びこれに対する平成18年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は、第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。
(3) 仮執行の宣言
2 被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、被控訴人から土地を買い受けたが、当該土地の土壌が有害物質により汚染されていたため、その後施行された東京都条例の規制に従い、汚染拡散防止措置を行わなければならなくなったと主張して、被控訴人に対し、民法570条の瑕疵担保責任に基づき、損害賠償として同措置に要する費用等相当額合計4億6095万5250円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成18年11月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は、控訴人の請求を棄却した。これを不服とする控訴人が控訴を提起した。控訴人は、当審において、本件売買契約締結当時本件土地の土壌がふっ素で汚染されていたことが本件土地の隠れた瑕疵であるというべきであるとし、この瑕疵が上記東京都条例の制定、施行により顕現化された旨の主張をするところ、被控訴人は、控訴人の上記主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たるとし、民事訴訟法157条に基づく却下の決定を求める旨の申立てをした。
控訴人は、当審において、請求額を12億3375万5250円に拡張する旨の「請求の趣旨増額の申立」と題する書面を提出したが、口頭弁論期日において同書面を陳述せずに、本件訴えのうち上記のとおり拡張した請求に係る部分を取り下げ、取下げ後の控訴人の本件請求が請求額12億3375万5250円の一部請求であることを明示した。
2 争いのない事実等は、原判決「事実及び理由」欄中の「第2 事案の概要」の1(原判決2頁4行目から4頁18行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。当事者の主張は、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示する(民事訴訟法253条2項)の限度で、次の3から6までのとおり請求の原因、請求の原因に対する認否、抗弁、抗弁に対する認否を摘示する。
3 控訴人の請求の原因
(1) 本件売買契約の締結
控訴人は、平成3年3月15日、被控訴人との間で、代金23億3572万6120円で原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を被控訴人から買い受ける旨の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。
(2) 本件土地の土壌中のふっ素の存在及びその有害性の認識
本件売買契約締結当時、客観的には、目的物である本件土地の土壌中にふっ素が含まれていたが、当時の取引観念上は土壌中にふっ素が含まれていることが有害であるとは認識されておらず、控訴人の担当者もふっ素が有害であると認識していなかった。
(3) 本件都条例の施行
東京都は、平成12年12月22日、東京都公害防止条例の全部を改正し、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)と題名を改めてこの条例(以下「本件都条例」という。)を公布し、平成13年4月1日本件都条例を施行した。本件都条例117条は、原判決別紙条文目録記載のとおり、土地の改変時における改変者の義務について規定するところ、同年10月1日に施行された。
本件都条例2条12号は、「有害物質」の意義について、「人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質で、別表第4に掲げるものをいう。」と定義し、別表第4には、鉛、砒素、カドミウム、ふっ素及びポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等を含む26種類の有害物質が掲げられている。
(4) 土壌中のふっ素の存在の有害性の認識
本件売買契約後、土壌中のふっ素の存在が有害であると社会的に認識され、当該物質を土壌を汚染するものとしてこれを規制する法規が制定されるに至った。
(5) 本件土地の土壌汚染調査による土壌中のふっ素の存在の判明
平成17年11月2日ころ、本件土地について土壌汚染調査が行われた結果、本件売買契約の目的物である本件土地の土壌中にふっ素が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明した。
(6) 本件土地の隠れた瑕疵
本件売買契約締結当時本件土地の土壌がふっ素で汚染されていたことは、本件土地の隠れた瑕疵に当たる。
(7) 控訴人の受けた損害
ア 控訴人は、本件土地につき土壌汚染対策工事請負契約を締結するに先立ち、平成17年8月4日、本件都条例117条1項に基づき、本件土地における過去の有害物質の取扱事業場の設置状況等規則所定の事項について調査するため、清水建設株式会社との間で契約金額5万2500円で委託契約を締結し、清水建設株式会社に本件土地の土壌汚染調査に係る地歴等調査を行わせ、同年10月19日、同社に対し、上記5万2500円を支払った。
イ 控訴人は、その結果を受け、本件都条例117条2項に基づき、東京都知事に対し、本件土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告するため、帝人エコ・サイエンス株式会社との間で、平成17年9月27日付けで契約金額945万円で、新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地土壌汚染調査委託契約を締結し、同年10月4日付けで上記原契約の変更契約を締結すると共に、契約金額を252万円とする追加調査委託契約を締結した。
控訴人は、平成17年12月22日、同社に対し、費用及び報酬として合計1197万円を支払った。
ウ 上記調査の結果、地下5mの地点でも汚染が確認され、更に深い深度でのボーリング調査を行って汚染深度を把握する必要が生じたため、控訴人は、同年11月3日、帝人エコ・サイエンス株式会社との間で、契約金額1869万円で土壌汚染調査の追加調査を行うことを委託する委託契約を締結し、平成18年3月31日、同社との間で、契約金額を1848万5250円に変更することなどを内容とする変更契約を締結し、同社に本件土地について土壌汚染の追加調査を行わせ、同年6月15日、同社に対し、費用及び報酬として1848万5250円を支払った。
エ 以上により、控訴人は、本件土地について土壌汚染対策工事を実施する必要が生じ、まず、平成18年9月8日、パシフィックコンサルタンツ株式会社との間で、契約金額519万7500円で上記対策工事発注仕様書の作成業務を委託する旨の委託契約を締結し、同社に上記工事の見積りをさせ、平成18年11月5日以前に、同社に対し上記契約金額を支払った。
オ 控訴人は、本件土地について土壌汚染の除去等の拡散防止措置を実施するために、平成18年12月26日、清水・竹内・太和建設共同企業体代表者清水建設株式会社との間で、契約金額4億2525万円で、新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地の土壌汚染対策工事請負契約を締結し、同額の債務を負担した。
(8) 一部請求である旨の明示
その後、本件土地の土壌汚染対策工事は設計変更及び工事代金増額を余儀なくされた。その結果、控訴人は、本件土地の隠れた瑕疵により、総額12億3375万5250円の損害を受けた。控訴人は、本件訴訟においては、上記12億3375万5250円のうち4億6095万5250円の限度で損害賠償請求をする。
(9) よって、控訴人は、被控訴人に対し、民法570条に基づき、上記12億3375万5250円のうち4億6095万5250円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成18年11月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
4 請求の原因に対する認否
(1) 請求の原因(1)(本件売買契約の締結)の事実は認める。
(2) 同(2)(本件土地の土壌中のふっ素の存在及びその有害性の認識)の事実のうち、本件売買契約締結当時の取引観念上は土壌中にふっ素が含まれていることが有害であると認識されていなかったことは認める。本件売買契約締結当時目的物である本件土地の土壌中に客観的にはふっ素が含まれていたこと、控訴人の担当者もふっ素が有害であると認識していなかったことは不知。
(3) 同(3)(本件都条例の施行)の事実は認める。
(4) 同(4)(土壌中のふっ素の存在の有害性の認識)のうち本件売買契約後、土壌中のふっ素の存在が土壌を汚染するものとしてこれを規制する法規が制定されるに至ったことは認め、その余の事実は不知。
(5) 同(5)(本件土地の土壌汚染調査による土壌中のふっ素の存在の判明)の事実は不知。
(6) 同(6)(本件土地の隠れた瑕疵)は争う。民法570条にいう隠れた瑕疵とは、売買の目的物が通常有すべき性能、品質を欠いていた場合又は契約当事者が契約上予定していた性質を欠いていた場合をいい、瑕疵の有無の判断に当たっては、売買契約締結当時の知見、法令等を基礎として判断すべきである。ふっ素については、その濃度によっては人の健康に被害を及ぼすおそれがあるという知見に基づき、「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月23日環境庁告示第46号)が改正されて基準が定められるに至ったが、それは平成13年3月28日のことであり、本件売買契約締結から約10年を経過した時点である。本件売買契約締結から約10年を経過した時点ではじめて確立された知見を基に本件売買契約締結時における取引社会の認識を議論することは不合理である。本件土地の土壌内にふっ素が存在しているとしても、本件売買契約締結時において、〈1〉土壌内のふっ素について何らの法的規制は存在せず、(2)土壌内のふっ素が人の健康上有害であるとの社会一般の認識もなく、〈3〉本件売買契約の当事者間において、土壌内のふっ素が本件土地の経済的効用及び交換価値を低下させる要因として認識されることはなかったことから、本件売買契約締結時において本件土地が通常有すべき品質、性能を備えていたことは明らかである。控訴人は、本件土地の土壌内から検出されたふっ素につき、本件売買契約締結当時に法的規制はなくとも、取引社会において、法的規制の有無にかかわらず、その存在ゆえに土地取引を断念するのが常であったことや、土地の売買価格に影響をもたらすことが常であったことなどの事実を主張立証しなければ、本件土地に隠れた瑕疵が存在したことを主張立証したことにならない。
(7) 同(7)(控訴人の受けた損害)の事実は不知。主張は争う。
(8) 同(8)(一部請求である旨の明示)の事実は不知。主張は争う。
(9) 同(9)は争う。
5 抗弁
(1) 本件土地の引渡し
被控訴人は、平成4年4月2日、控訴人に対し、本件売買契約に基づき、目的物である本件土地を引き渡した。
(2) 本件土地の引渡しの日から10年間の経過
上記引渡しの日から10年後である平成14年4月2日は既に経過した。
(3) 時効の援用
被控訴人は、上記消滅時効を援用する。
6 抗弁に対する認否
(1) 抗弁(1)(本件土地の引渡し)の事実は認める。しかし、消滅時効の進行は、権利の性質上その行使を現実に期待できる状態になければ進行しないとされているところ、控訴人が、被控訴人から本件売買契約に基づく本件土地の引渡しを受けたときには、本件損害賠償請求権はいまだ発生していなかったから、本件土地の引渡時から消滅時効が進行するということはできない。本件損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、本件都条例によって本件土地の瑕疵が顕現化された時点、すなわち、本件土地について新たな負担が付された時点又はその負担を原告が実行した時点と解すべきである。
(2) 同(2)(本件土地の引渡しの日から10年間の経過)の事実は認める。
(3) したがって、本件損害賠償請求権は、時効消滅していない。 第3 当裁判所の判断
1 被控訴人の民事訴訟法157条に基づく時機に後れた攻撃防御方法の却下の決定を求める申立てについて
控訴人は、当審において、本件売買契約締結当時本件土地の土壌がふっ素で汚染されていたことが本件土地の隠れた瑕疵であるというべきであり、この瑕疵が本件都条例の制定、施行により顕現化された旨の主張をするところ、被控訴人は、控訴人の上記主張が時機に送れた攻撃防御方法に当たるとし、民事訴訟法157条に基づく却下の決定を求める旨の申立てをしたので、まず、この申立てについて判断する。
控訴人は、原審において、(1)本件売買契約締結当時、控訴人は、本件土地がふっ素等で汚染されていたことを知らなかったとし、その後本件都条例が施行され、本件土地の土壌汚染調査を実施したところ、本件土地の土壌は、ふっ素等の有害物質により、本件都条例で定められた土壌汚染処理基準を遙かに超えて汚染されていることが明らかになったとし、本件都条例により、控訴人が本件土地を公園として使用することは本件土地の改変となり、これに伴う汚染拡散防止措置を必要とすることになったとし、本件都条例の規制を受けること自体本件土地に民法570条にいう隠れた瑕疵があるというべきである旨主張し(訴状、原告平成19年2月21日付け準備書面)、(2)本件売買契約締結当時、本件土地はふっ素等で汚染されていたが、本件都条例はいまだ制定されていなかったこと、その後本件都条例が施行され、控訴人が本件土地を公園用地として使用するについて本件都条例117条1項、同条3項及び4項により本件土地の土壌汚染調査及び汚染の拡散防止措置を行わなければならないという新たな規制を受けるに至ったこと、本件都条例により本件土地について上記のような規制を受けること自体が本件土地に瑕疵があったというべきであること、本件土地に民法570条にいう隠れた瑕疵があると主張する根拠は、ふっ素等によって本件土地の土壌が汚染されていること自体を主張するものではなく、本件都条例によって定められた土壌汚染調査を行った結果、汚染が認められた場合には、汚染の拡散防止措置を執らなければならず、これを行わずには本件土地を公園用地として改変することができないという新たな規制を受けるに至ったのであり、そのこと自体が本件土地に新たに瑕疵があると本件都条例により公的に確認されたことを示すものである(本件都条例により隠れた瑕疵として公的に顕現化された)と主張するものであること、以上のとおり主張し(原告平成19年4月11日付け準備書面)、(3)さらに、本件売買契約締結当時本件土地の土壌がふっ素等によって汚染されていたことは疑いのない事実であるが、当時本件都条例が施行されておらず、控訴人は上記土壌汚染が本件土地の使用に影響する瑕疵と考えることができなかったのであるから、本件都条例が制定、施行され、工事費用の負担が生じたことで、売主の瑕疵担保責任が発生することとなったと主張していた(原告平成19年5月30日付け準備書面)。
これによれば、控訴人は、原審において、法的構成としては、文言上、本件土地に民法570条にいう隠れた瑕疵があると主張する根拠として、ふっ素等によって本件土地の土壌が汚染されていること自体を主張するものではなく、本件都条例によって定められた土壌汚染調査を行った結果、汚染が認められた場合には、汚染の拡散防止措置を執らなければならず、これを行わずには本件土地を公園用地として改変することができないという新たな規制を受けるに至ったことをもって、本件土地に民法570条にいう隠れた瑕疵があると主張していたものといわざるを得ないが、他方、控訴人の原審における主張の全趣旨にかんがみれば、控訴人は、〈1〉本件売買契約締結当時本件土地の土壌中にふっ素が(大量に)存在していたこと、〈2〉その後本件都条例が施行され、土壌汚染調査により、本件土地の土壌がふっ素等の有害物質で本件都条例で定められた土壌汚染処理基準を遙かに超えて汚染されていることが明らかになったため、本件都条例により、控訴人が本件土地を公園として使用することは本件土地の改変となり、これに伴う汚染拡散防止措置を必要とすることになったこと、〈3〉そのこと自体が本件土地に新たに瑕疵があると本件都条例により公的に確認されたことを示すものであることを主張していたのであり、上記〈1〉が上記〈2〉の不可欠の前提であることは客観的に明らかであったから、控訴人は、本件請求の根拠として、上記〈1〉及び〈2〉を主張していたものというべきである。控訴人は、本来ならば、法的構成としても、上記〈1〉及び〈2〉を根拠に、本件土地に民法570条にいう隠れた瑕疵があるというべきであると明示的に主張すべきであったのであり、明示的にそのように主張していれば、原審においても、控訴人が上記〈1〉と切り離して上記〈2〉だけを主張しているものと誤解されることはなかったというべきである。したがって、控訴人に法的構成における誤りがあったことは否定し難いが、その誤った法的構成においても、上記〈1〉が事実主張としては不可欠の前提であることは動かし難いから、控訴人は、原審においても、本件請求の根拠として、上記〈1〉及び〈2〉を主張していたものというべきである。
控訴人は、当審において、本件売買契約締約当時本件土地の土壌中にふっ素が(大量に)存在しており、土壌汚染が生じていたのであり、このことが本件土地の隠れた瑕疵であるというべきであって、この瑕疵が本件都条例の制定、施行により顕現化された旨の主張を明示的にするに至ったが、控訴人の当審における上記主張は、本件請求の根拠として上記〈1〉及び〈2〉を主張するものであり、原審における控訴人の主張の全趣旨を変更するものではなく、法的構成における誤りを正したにすぎないものというべきである。
以上によれば、控訴人が当審において上記のとおり主張して法的構成における誤りを正したことは、控訴人が時機に後れて攻撃方法を提出したことには当たらないから、民事訴訟法157条に基づく却下の決定を求める被控訴人の申立ては理由がないというべきである。
2 認定事実
前記引用に係る原判決摘示の争いのない事実等に証拠(甲3の1、3の2、4の1から4の5まで、5の1から5の4まで、6、7、9、15、25、26、32、35、36、37の1、37の2、38、39、45、47、50から52まで、54から56まで、58、60から71まで、72の2、乙5、8、9、19、20、22、25)を併せて考えれば、次の事実を認めることができる。
(1) 本件売買契約の締結
控訴人は、平成3年3月15日、被控訴人との間で、代金23億3572万6120円で本件土地を被控訴人から買い受ける旨の本件売買契約を締結した。
控訴人が本件売買契約を締結したのは、平成3年当時、控訴人が、足立区から、東京都が進めていた東京都荒川区日暮里と東京都足立区舎人地区を結ぶ新交通システム日暮里・舎人線(仮称)の開設に不可欠な用地の被買収者に対して提供する代替地の取得を要請されていたためであった。
本件売買契約締結当時、客観的には、目的物である本件土地の土壌中にふっ素が含まれていたが、当時の取引観念上は土壌中にふっ素が含まれていることが有害であるとは認識されておらず、控訴人の担当者もふっ素が有害であると認識していなかった。
(2) 本件土地の利用状況
本件土地は、昭和59年4月1日までは株式会社アスニーが、同社が被控訴人に吸収合併された同日以降は被控訴人が、主に工業用フッ化水素酸を製造するための工場用地として利用していた。
(3) 土壌調査
控訴人は、本件売買契約に先立ち、株式会社環境技術研究所に本件土地の土壌調査を委託した。
平成3年2月20日に行われた土壌調査(以下「平成3年調査」という。)の結果、本件売買契約締結当時、本件土地の表層土に、東京都の定める公用地取得に係る重金属等による汚染土壌の処理基準値を超える量の鉛、砒素及びカドミウムが含有されている部分が存することが判明した。
(4) 本件都条例の施行等(顕著な事実)
ア 東京都は、平成12年12月22日、東京都公害防止条例の全部を改正し、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)と題名を改めてこの条例を公布し、平成13年4月1日本件都条例を施行した。本件都条例117条については、同年10月1日に施行された。
イ 本件都条例2条12号は、「有害物質」の意義について、「人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質で、別表第4に掲げるものをいう。」と定義し、別表第4には、鉛、砒素、カドミウム、ふっ素及びPCB等を含む26種類の有害物質が掲げられている。ふっ素が加えられたのは平成15年2月15日である。
ウ 本件都条例117条は、原判決別紙条文目録記載のとおり、土地の改変時における改変者の義務について規定している。
(5) 平成13年3月28日、環境基本法16条に基づく平成3年8月環境省告示第46号「土壌の汚染に係る環境基準について」の一部が平成13年3月28日付け環境省告示第16号をもって改正され、別表の項目にふっ素が加えられ、ふっ素の環境上の条件は「検液1Lにつき0.8mg以下であること」と定められ、これが環境基準であるとされた。この改正の眼目は、これをふっ素についていえば、ふっ素による土壌の汚染に適切に対処しようとするものである。
(6) 平成14年5月29日土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)が公布され、平成15年2月15日同法が施行された。同法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とし(同法1条)、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを「特定有害物質」としている(同法2条1項)。これを受けて、土壌汚染対策法施行令1条21号は、「ふっ素及びその化合物」を、土壌汚染対策法2条1項の政令で定める物質としている。
(7) 代替地としての提供
東京都足立区は、平成14年4月、新交通システム日暮里・舎人線(仮称)の江北駅(仮称)駅前広場予定地を、甲野太郎から買収することになったところ、同人及び同土地上に存する建物を同人から賃借して運送業を営む株式会社扇運輸(以下、甲野太郎と併せて「甲野ら」という。)から、代替地の提供を求められた。控訴人は、東京都足立区の要請により、本件土地を甲野らに対する被買収土地の代替地として提供するための協議を行った。
(8) 控訴人は、本件土地につき土壌汚染対策工事請負契約を締結するに先立ち、平成17年8月4日、本件都条例117条1項に基づき、本件土地における過去の有害物質の取扱事業場の設置状況等所定の事項について調査するため、清水建設株式会社との間で契約金額5万2500円で委託契約を締結し、清水建設株式会社に本件土地の土壌汚染調査に係る地歴等調査を行わせ、同年10月19日、同社に対し、上記5万2500円を支払った。
(9) 控訴人は、その結果を受け、本件都条例117条2項に基づき、東京都知事に対し、本件土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告するため、帝人エコ・サイエンス株式会社との間で、平成17年9月27日付けで契約金額945万円で、新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地土壌汚染調査委託契約を締結し、同年10月4日付けで上記原契約の変更契約を締結すると共に、契約金額252万円とする追加調査委託契約を締結した。
帝人エコ・サイエンス株式会社は、上記各契約に基づき、本件土地について土壌汚染調査を実施し、控訴人に対し、同年11月2日付け「新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地の土壌汚染調査報告書」(甲4の4)を提出した。上記報告書によれば、試料を採取した40地点のすべての地点でふっ素が検出され、その量は、40地点のすべての地点で溶出量基準値を超え(最高で基準値の1200倍)、39地点で含有量基準値を超え(最高で基準値の23倍)、ふっ素による地下水汚染が確認されたというものであった。上記報告書は、そのため、敷地境界を囲む少なくとも四方位4箇所に最初の帯水層(恒常的に地下水が存在する宙水層又は第一帯水層)の底部までを設置深度とする観測井を設け、速やかに地下水の水質測定(モニタリング)を開始し、その結果を東京都に定期的に報告する必要があり、また、ふっ素等の特定有害物質による汚染土壌が存在するため、汚染の除去等の拡散防止措置を実施する必要があることなどを指摘した。
このように、本件土地について土壌汚染調査が行われた結果、本件土地がふっ素によって人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて汚染されていることが判明した。
控訴人は、平成17年12月22日、同社に対し、費用及び報酬として合計1197万円を支払った。
(10) 上記調査の結果、地下5mの地点でも汚染が確認され、更に深い深度でのボーリング調査を行って汚染深度を把握する必要が生じたため、控訴人は、同年11月3日、帝人エコ・サイエンス株式会社との間で、契約金額1869万円で土壌汚染調査の追加調査を行うことを委託する委託契約を締結し、平成18年3月31日、同社との間で、契約金額を1848万5250円に変更することなどを内容とする変更契約を締結し、同社に本件土地について土壌汚染の追加調査を行わせ、同年6月15日、同社に対し、費用及び報酬として1848万5250円を支払った。
(11) 以上により、控訴人は、本件土地について土壌汚染対策工事を実施する必要が生じ、まず、平成18年9月8日、パシフィックコンサルタンツ株式会社との間で、契約金額519万7500円で上記対策工事発注仕様書の作成業務を委託する旨の委託契約を締結し、同社に上記工事の見積りをさせ、平成18年11月5日以前に、同社に対し上記契約金額を支払った。
(12) 控訴人は、本件土地について土壌汚染の除去等の拡散防止措置を実施するために、平成18年12月26日、清水・竹内・太和建設共同企業体代表者清水建設株式会社との間で、契約金額4億2525万円で、新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地の土壌汚染対策工事請負契約を締結し、同額の債務を負担した。
3 売買契約の目的物である土地に含まれていた物質が当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが売買契約後に有害であると社会的に認知された場合と民法570条にいう隠れた瑕疵
(1) 居住その他の土地の通常の利用をすることを目的として締結される売買契約の目的物である土地の土壌に人の生命、身体、健康を損なう危険のある有害物質が上記の危険がないと認められる限度を超えて含まれていないことは、上記売買契約の目的に照らし、売買契約の目的物である土地が通常備えるべき品質、性能に当たるというべきである。したがって、上記売買契約の目的物である土地の土壌に実際には有害物質が含まれていたが、売買契約締結当時は取引上相当な注意を払っても発見することができず、その後売買契約の目的物である土地の土壌に売買契約締結当時から当該有害物質が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明した場合(以下「〈1〉の場合」という。)には、目的物である土地における上記有害物質の存在は民法570条にいう隠れた瑕疵に当たると解するのが相当である。
ところで、居住その他の土地の通常の利用をすることを目的として締結された売買契約の目的物である土地の土壌に含まれていた物質が当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが、売買契約後に有害であると社会的に認識された場合において、売買契約の目的物である土地の土壌に当該物質が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明したとき(以下「〈2〉の場合」という。)にも、売買契約の目的物である土地の土壌に人の生命、身体、健康を損なう危険のある有害物質が上記の危険がないと認められる限度を超えて含まれていないことという、上記売買契約の目的物である土地が通常備えるべき品質、性能を欠くというべきであり、この点において〈1〉の場合と差はない。また、〈2〉の場合には、買主にとっては、売買契約締結当時取引上相当な注意を払っても売買契約の目的物である土地に含まれていた物質が有害であると認識することはできなかったというべきであって、この点においても〈1〉の場合と差はない。さらに、売買契約締結当時、売買契約の目的物である土地に含まれている物質の有害性が社会的に認識されていたかどうかは、当事者が売買契約を締結するに当たって前提となる事実をどのように認識していたか、また、認識可能であったかに包含される問題であって、事実の範疇に包含される問題であると考えられる。そして、このことは、上記売買契約の目的物である土地に含まれていた物質が当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが売買契約後に有害であると社会的に認識されたために、当該物質を土壌を汚染するものとしてこれを規制する法令が制定されるに至った場合において、売買契約の目的物である土地の土壌に当該物質が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明したとき(以下「〈3〉の場合」という。)にも当てはまるのであり、売買契約締結当時土壌を汚染するものとして当該物質を規制し、汚染の除去等の措置を定める法令の規定が存在しなかったことを理由に、売買契約締結当時は目的物である土地の土壌中に当該物質が含まれていても、上記売買契約は適法であったとして、〈3〉の場合に、民法570条にいう隠れた瑕疵が存在することを否定することは、できないものというべきである。民法570条に基づく売主の瑕疵担保責任は、売買契約の当事者間の公平と取引の信用を保護するために特に法定されたものであり、買主が売主に過失その他の帰責事由があることを理由として発生するものではなく、売買契約の当事者双方が予期しなかったような売買の目的物の性能、品質に欠ける点があるという事態が生じたときに、その負担を売主に負わせることとする制度である。このことにかんがみると、民法570条の適用上、〈1〉の場合と〈2〉の場合及び〈3〉の場合とで区別することは、相当ではないというべきである。
以上によれば、居住その他の土地の通常の利用をすることを目的として締結された売買契約の目的物である土地の土壌に人の生命、身体、健康を損なう危険のある有害物質が上記の危険がないと認められる限度を超えて含まれていたが、当時の取引観念上はその有害性が認識されていなかった場合において、その後、当該物質が土地の土壌に上記の限度を超えて含まれることは有害であることが社会的に認識されるに至ったときには、上記売買契約の目的物である土地の土壌に当該有害物質が上記の限度を超えて含まれていたことは、民法570条にいう隠れた瑕疵に当たると解するのが相当である。そして、上記の場合において、土壌を汚染するものとして当該物質を規制し、汚染の除去等の措置を定める法令の規定が定められ、買主が当該規定に従い、汚染の除去等の措置に必要な費用を負担したときには、買主は売主に対し、民法570条に基づき、上記の費用相当額の損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。
被控訴人は、民法570条にいう隠れた瑕疵とは、売買の目的物が通常有すべき性能、品質を欠いていた場合又は契約当事者が契約上予定していた性質を欠いていた場合をいい、瑕疵の有無の判断に当たっては、売買契約締結当時の知見、法令等を基礎として判断すべきである旨主張する。しかしながら、民法570条に基づく売主の瑕疵担保責任は、上記のとおり、売主に過失その他の帰責事由があることを理由として発生するものではなく、売買契約当事者間の公平と取引の信用を保護するために特に法定されたものであるから、売買契約締結当時の知見、法令等が瑕疵の有無の判断を決定するものであるとはいえない。したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) 前記認定事実によれば、本件売買契約締結当時、目的物である本件土地の土壌中にふっ素が含まれていたが、当時の取引観念上は土壌中にふっ素が含まれていることが有害であるとは認識されておらず、控訴人の担当者もふっ素が有害であると認識していなかったこと、しかし、本件売買契約締結後、平成13年3月28日、環境基本法16条に基づく平成3年8月環境省告示第46号「土壌の汚染に係る環境基準について」の一部が平成13年3月28日付け環境省告示第16号をもって改正され、別表の項目にふっ素が加えられ、ふっ素の環境上の条件は「検液1Lにつき0.8mg以下であること」と定められ、これが環境基準であるとされたこと、この改正の眼目は、これをふっ素についていえば、ふっ素による土壌の汚染に適切に対処しようとするものであること、東京都は、上記の改正に先立ち、平成12年12月22日、東京都公害防止条例の全部を改正し、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)と題名を改めてこの条例を公布し、平成13年4月1日本件都条例を施行したこと、本件都条例2条12号は、「有害物質」の意義について、「人の健康に障害を及ぼす物質のうち水質又は土壌を汚染する原因となる物質で、別表第4に掲げるものをいう。」と定義し、別表第4には、鉛、砒素、カドミウム、ふっ素及びPCB等を含む26種類の有害物質が掲げられていること(ふっ素が加えられたのは平成15年2月15日である。)、平成14年5月29日土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)が公布され、平成15年2月15日同法が施行されたこと、同法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とし(同法1条)、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを「特定有害物質」としていること(同法2条1項)、これを受けて、土壌汚染対策法施行令1条21号は、「ふっ素及びその化合物」を、土壌汚染対策法2条1項の政令で定める物質としていること、控訴人は、本件都条例117条2項に基づき、東京都知事に対し、本件土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告するため、帝人エコ・サイエンス株式会社との間で、平成17年9月27日付けで新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地土壌汚染調査委託契約(甲4の1)を締結し、同年10月4日付けで上記原契約の変更契約(甲4の2)及び追加委託契約(甲4の3)を締結したこと、帝人エコ・サイエンス株式会社は、上記各契約に基づき、本件土地について土壌汚染調査を実施し、控訴人に対し、同年11月2日付け「新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地の土壌汚染調査報告書」(甲4の4)を提出したこと、上記報告書によれば、試料を採取した40地点のすべての地点でふっ素が検出され、その量は、40地点のすべての地点で溶出量基準値を超え(最高で基準値の1200倍)、39地点で含有量基準値を超え(最高で基準値の23倍)、ふっ素による地下水汚染が確認されたため、敷地境界を囲む少なくとも四方位4箇所に最初の帯水層(恒常的に地下水が存在する宙水層又は第一帯水層)の底部までを設置深度とする観測井を設け、速やかに地下水の水質測定(モニタリング)を開始し、その結果を東京都に定期的に報告する必要があり、また、ふっ素等の特定有害物質による汚染土壌が存在するため、汚染の除去等の拡散防止措置を実施する必要があることなどが明らかになったこと、このように、本件土地について土壌汚染調査が行われた結果、本件土地がふっ素によって人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて汚染されていることが判明したこと、以上の事実を認めることができる。
上記認定事実によれば、本件売買契約当時、その目的物である本件土地の土壌中にふっ素が含まれていたが、当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったところ、本件売買契約後の平成13年3月28日にふっ素が有害であると社会的に認識されたために、当該物質を土壌を汚染するものとしてこれを規制する法規が制定されるに至ったものということができるのであり、平成17年11月2日ころ、本件売買契約の目的物である本件土地の土壌中にふっ素が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明したものということができる。
以上のとおり、本件売買契約の目的物である本件土地の土壌中に上記のとおりふっ素が含まれていたことは、民法570条にいう隠れた瑕疵に当たるというべきである。したがって、控訴人は、被控訴人に対し、本件都条例に基づき、汚染の除去等の拡散防止措置を実施するために負担した必要な費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
4 損害について
前記認定事実によれば、〈1〉控訴人は、本件土地につき土壌汚染対策工事請負契約を締結するに先立ち、平成17年8月4日、本件都条例117条1項に基づき、本件土地における過去の有害物質の取扱事業場の設置状況等所定の事項について調査するため、清水建設株式会社との間で契約金額5万2500円で委託契約を締結し、清水建設株式会社に本件土地の土壌汚染調査に係る地歴等調査を行わせ、同社に対し、上記5万2500円を支払ったこと、〈2〉控訴人は、その結果を受け、同年9月27日、本件都条例117条2項に基づき、本件土地について土壌汚染調査を行うため、帝人エコ・サイエンス株式会社との間で、契約金額945万円で委託契約を締結し、同年10月4日、同社との間で変更契約を締結すると共に、契約金額252万円で追加委託契約を締結し、同社に本件土地について土壌汚染調査を行わせ、同社に対し、費用及び報酬として合計1197万円を支払ったこと、〈3〉上記〈2〉の調査の結果、地下5mの地点でも汚染が確認され、更に深い深度でのボーリング調査を行って汚染深度を把握する必要が生じたため、控訴人は、同年11月3日、帝人エコ・サイエンス株式会社との間で、契約金額1869万円で土壌汚染調査の追加調査を行うことを委託する委託契約を締結し、平成18年3月31日、同社との間で、契約金額を1848万5250円に変更することなどを内容とする変更契約を締結し、同社に本件土地について土壌汚染の追加調査を行わせ、同社に対し、費用及び報酬として1848万5250円を支払ったこと、〈4〉以上により、控訴人は、本件土地について土壌汚染対策工事を実施する必要が生じ、まず、平成18年9月8日、パシフィックコンサルタンツ株式会社との間で、契約金額519万7500円で上記対策工事発注仕様書の作成業務を委託する旨の委託契約を締結し、同社に上記工事の見積りをさせ、同社に対し上記契約金額を支払ったこと、〈5〉控訴人は、本件土地について土壌汚染の除去等の拡散防止措置を実施するために、平成18年12月26日、清水・竹内・太和建設共同企業体代表者清水建設株式会社との間で、契約金額4億2525万円で、新田1丁目、日暮里・舎人線関連用地の土壌汚染対策工事請負契約を締結し、同額の債務を負担したことが認められる。上記〈1〉の契約の締結及び金銭の支出並びに上記〈2〉の各契約の締結及び金銭の支出は、本件都条例117条1項及び同条2項によりされたものであり、本件売買契約の目的物である本件土地の土壌中にふっ素が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたという隠れた瑕疵が存在していたこととの間に相当因果関係はないというべきであるが、他方、上記〈3〉の契約の締結及び金銭の支出、上記〈4〉の契約の締結及び金銭の支出並びに上記〈5〉の契約の締結及び債務の負担は、本件土地の上記の隠れた瑕疵によるものであり、上記の隠れた瑕疵の存在との間に相当因果関係が存在するというべきである。したがって、控訴人は、被控訴人に対し、上記〈3〉から〈5〉までの支出額及び債務負担額合計4億4893万2750円の損害賠償請求をすることができることになる。控訴人は、上記損害額元本に対する本件訴状送達の日の翌日である平成18年11月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払も請求するところ、上記〈5〉のとおり控訴人が負担した債務については、控訴人が支払った前払金の額は証拠上明らかでないが、甲第9号証により、控訴人は、上記債務の全額について、遅くとも平成20年7月8日(約定の工期である同年3月31日から40日経過した同年5月10日の後である本件口頭弁論終結の日)までには支払うべき義務を負ったものと認めることができるから、4億2525万円に対する遅延損害金の起算日は平成20年7月8日とすべきである。
以上によれば、控訴人の請求は、4億4893万2750円並びにうち2368万2750円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成18年11月5日から、及びうち4億2525万円に対する平成20年7月8日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める部分につき理由があるから、上記の限度でこれを認容すべきであるが、控訴人の請求中その余の部分については理由がないから、これを棄却すべきである。
5 被控訴人の消滅時効の抗弁について
瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である(最高裁平成10年(オ)第773号同13年11月27日第三小法廷判決・民集55巻6号1311頁参照)。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ、上記第三小法廷判決は、通常の場合には、買主が、売買の目的物の引渡しを受けた後、瑕疵を発見するについて法律上の障害はなく、合理的に行動する買主を想定してその者が取引上必要とされる注意を払えば売買の目的物の瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することが可能であることを前提にしているのであり(上記第三小法廷判決参照)、上記第三小法廷判決の法理は、合理的に行動する買主を想定してその者が取引上必要とされる注意を払ったとしても、取引観念上瑕疵が存在するものとは評価されなかったために、売買の目的物の引渡しを受けた時から損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在する場合にまで及ぶものではない。
これを本件についてみるに、本件売買契約当時、その目的物である本件土地の土壌中にふっ素が含まれていたが、当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったこと、本件売買契約後の平成13年3月28日に土壌中のふっ素が有害であると社会的に認識されたために、当該物質を土壌を汚染するものとしてこれを規制する法令が制定されるに至ったものということができることは、前記のとおりである。これによれば、控訴人が本件売買契約の目的物である本件土地の引渡しを受けた時には、本件土地に取引観念上瑕疵が存在するものとは評価されなかったために、控訴人が本件売買契約の目的物である本件土地の引渡しを受けた時から損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在したというべきであって、控訴人が本件土地に隠れた瑕疵があるとして民法570条に基づく損害賠償請求権を行使することができる時は、控訴人が本件土地の引渡しを受けた時ではなく、土壌中のふっ素が有害であると社会的に認識されるに至った平成13年3月28日であるというべきである。そして、控訴人は、平成17年11月2日ころ、本件売買契約の目的物である本件土地の土壌中にふっ素が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明したことを受け、平成18年10月27日に本件訴訟を提起して上記損害賠償請求権を行使するに至ったのであるから、平成13年3月28日から進行する消滅時効の時効期間が経過する前に、上記損害賠償請求権を行使したものということができる。したがって、被控訴人の消滅時効の抗弁は理由がない。
第4 結論
以上の認定及び判断の結果によると、控訴人の請求は、4億4893万2750円並びにうち2368万2750円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成18年11月5日から、及びうち4億2525万円に対する平成20年7月8日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める部分につき理由があるから、上記の限度でこれを認容すべきであるが、控訴人の請求中その余の部分については理由がないから、これを棄却すべきである。そうすると、当裁判所の上記判断と異なり、控訴人の請求をすべて棄却した原判決は一部不当であるから、これを上記の趣旨に変更することとして、主文のとおり判決する。 第21民事部 (裁判長裁判官 渡邉等 裁判官 髙世三郎 裁判官 西口元)
東京地方裁判所 平成18年(ワ)第23983号 平成19年07月25日
平成19年(ネ)第4169号
本件は、原告が、被告から買い受けた土地の土壌が有害物質により汚染されていたため、その後施行された東京都条例の規制に従い、汚染拡散防止措置を行わなければならなくなったこと等が民法570条にいう「瑕疵」に当たると主張して、被告に対し、同条の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として、同措置に要する費用等合計4億6095万5250円の支払を求める事案である。
判例研究【3】を学ぶにあたっての基礎知識

さらに、これは瑕疵の様態に応じて、権利の瑕疵と物の瑕疵とに分けられるが、特に、後者にあっては、「瑕疵担保責任」とよばれ、不動産に関する紛争事例として近年、土壌汚染を中心に数多く取り上げられている。
公共用地の取得にあたっては、この土壌汚染への対応に係る取扱指針等が示されており、契約前により慎重な調査等の実施、土壌汚染の状況を踏まえた適正な損失補償の確保等が求められている。一方、先行取得等を例とした土壌汚染対策施工前に契約がなされたケースにおいては、その目的物である土地にかかる法令等の規制を超える有害物質の存在が後に判明し、取り上げられている瑕疵担保責任の問題が発生し得ることも想定される等、改めて留意すべきものと思われるため、今回その近時の判例を紹介するものである。
民法・関連条文
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的の場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は契約を解除することができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 略
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
(売主の瑕疵担保責任)
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があった時は、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
Xは、Yから、その所有地を購入する際に、この土地の土壌を調査したところ、当該土地の表層土に、東京都の定める公用地取得に係る重金属等による汚染土壌の処理基準を超える量の亜鉛、砒素及びカドミウムの含まれている部分が存在することが判明した。
Xは、このような状況下で、平成3年3月15日にYと約23億円で売買契約を締結した。
本件土地の土壌には、本件売買契約締結当時からふっ素が含まれていたが、その当時、土壌に含まれるふっ素については、法令に基づく規制の対象となっていなかったし、取引観念上も、ふっ素が土壌に含まれることに起因して、人の健康に係る被害を生じる恐れがあると認識しておらず、Yもそのような認識を有していなかった。
その後ふっ素についての新環境基準が平成13年3月28日に告示され、Xは、平成3年の上記調査の結果、本件土壌に上記亜鉛、砒素等が包含されていたので、他の有害物質による汚染の有無についても調査したところ(平成17年11月2日ごろ)、当該土地の表層土に、条例・その施行規則が定める汚染土壌処理基準を超える量のふっ素の包含されている部分が存することが判明した。
このふっ素の包含量は、人の生命・身体・健康を損なう危険があることが明確となり、Xは、本件土地を公園用地として利用することとしていたため、土壌汚染対策工事の実施を余儀なくされた。そこで、Xは、Yに対し、瑕疵担保責任による損害賠償を求めた。
論点 1 瑕疵の存在時期 2 瑕疵担保責任の消滅時効

売買の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約当時の取引観念をしんしゃくして判断すべきところ、前記事実関係によれば、本件売買契約締結当時、取引観念上、フッ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおされがあると認識されておらず、被上告人の担当者もそのような認識を有していなかったのであり、フッ素が、それが土壌に含まれことに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは、本件売買契約締結ごであったというのである。
そして、本件売買契約の当事者間において、本件土地が備えるべき属性として、その土壌に、フッ素が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない。そうすると、本件売買契約締結当時の取引観念上、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害に生ずるおそれがあると認識されていなかったフッ素について、本件売買契約の当事者間において、それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれてないことが予定されていたものとみることはできず、本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれも超えるフッ素が含まれていたとしても、そのことは、民法570条にいう瑕疵には当たらないというべきである。
【論点】瑕疵担保責任の要件/瑕疵担保責任の消滅時効(排斥期間)

①「隠れた瑕疵」の存在----瑕疵の判断時期
②売買の責任期間
1 瑕疵担保責任の要件
- 「隠れた瑕疵」の存在
また、ここに言う瑕疵は、隠れたものであることを要し、隠れたものであるとは、通常の注意をしていても、瑕疵を発見できないことを意味する。
なお、ここでは、買主が瑕疵を知らないことにつき、過失がないことが必要と解されている。
本件事案においては、隠れた瑕疵が存すると判断する時期がいつであるかが主要な問題となっている。
- 売主の責任期間
2 検討
1瑕疵の判断時期
2 検討
1瑕疵の判断時期
本件の控訴審判決(東京高判決平成20年9月25日判決)は、当時の取引観念上は、その有害性が認識されていなかった場合において、その後、当該物質が土地の土壌に非との声明・身体・健康を損なう危険のある有害物質であることが社会的に認識されるに至ったときは、民法570条にいう隠れた瑕疵に当たるというのが相当であるとしている。
また、民法570条に基づく売主の瑕疵担保責任は、売主に過失その他の帰責事由があることや理由としてとして発生するものではなく、売買契約者間の公平と取引の信用を保護するために法定されたものであるから、売買契約締結当時の知見、法令等が瑕疵の有無の判断を決定するものであるとはいえない、としている。
以上から、本判決は、売買契約の目的物である土地の土壌中に上記のとおりふっ素が含まれていたことは、民法570条にいう隠れた瑕疵に当たるというべきである、としている。
本件判決が述べているように、たとえ契約締結時に売主に瑕疵担保責任を、売買の公平と取引の信用・保護の観点から認めようとしても、契約の当時において、予測可能性がないのに、売主に担保責任を認めるには、無理があろう。
また、目的物が買主の支配下に移転した後に発生した事象まで、売主に責任を負わせるのは酷であろう。
② 売主の責任期間
民法566条3項の準用により(本文570条本文)、契約の解除または損害賠償の請求は、買主が事実を知った時より1年以内にしなければならない。つまり、買主が瑕疵を知った時を起算点として、短期の解決が図られている。
もっとも、宅地建物取引業法40条は、取引業者が自ら売主となった場合には、目的物の引き渡しから2年以上の特約を認めないとしている。
なお、売主の1年の責任期間と、売主の責任について10年の一般消滅時効期間(民法167条1項)との関係は、後者は、買主が目的物の引き渡しを受けた時から進行する点で(最高裁平成13年11月27日第3小法廷判決民集55巻6号311頁)、相違がある。
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行するが(民法166条1項)、上記最高裁判決は、通常の場合には、買主が、売買目的の引き渡しを受けた後、瑕疵を発見することについて法律上の障害はなく、合理的に行動する買主を想定してその者が損害賠償請求権を行使することが可能であることを前提としているのであり(上記第三小法廷判決参照)、上記第三小法廷判決の法理は、合理的に行動する買主を想定してその者が取引上必要とされる注意を払っていたとしても、取引観念上 瑕疵が存在するとは評価されなかったために、売買の目的物の引渡しを受けた時から損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在する場合までに及ぶものではない。
上告人が本件売買契約の目的物である本件土地の引渡しを受けた時には、本件土地に取引観念上瑕疵が存在するものとは評価されなかったために、上告人が本件売買契約の目的物である本件土地の引き渡しを受けた時から、損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在するとは評価されなかったために、売買の目的物の引渡しを受けた時から損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在する場合までに及ぶものではない。
上告人が本件売買契約の目的物である本件土地の引渡しを受けた時には、本件土地に取引観念上瑕疵が存在するものとは評価されなかったために、上告人が本件売買契約の目的物である本件土地の引き渡しを受けた時から、損害賠償請求権を行使することができない特段の事情が存在したというべきであって、上告人が本件土地に隠れた瑕疵があるとして、民法570条に基づく損害賠償請求を行使することができる時は、控訴人が本件土地の引渡しを受けた時ではなく、土壌中のふっ素が有害であると社会的に認識されるに至った平成13年3月28日であるというべきである。
以上から上記小法廷の述べるところは正鵠を得ており、指示できるところであろう。
賃貸借契約に関する判例(借地借家法32条1項)
平成30年05月30日/東京高等裁判所/第23民事部/判決/平成30年(ネ)787号
【事案概要】
株式会社である原告が、株式会社である被告との間で締結した建物賃貸借契約に係る賃料が不相当に低額になった旨主張して、被告に対し、借地借家法32条1項の賃料増額請求に基づき同建物の賃料が増額となったことの確認を求めるとともに、同上2項ただし書きに基づき、増額となった賃料に係る不足額の支払いを求めた件につき、原告の請求がいずれも棄却された原判決を不服として原告が控訴した控訴審において、同控訴が棄却された...
準備中
神戸地方裁判所
平成25年(ワ)第604号/平成25年(ワ)第1006号平成30年02月21日
【事案概要】
被告を賃貸人とし、原告を賃借人とする建物の賃貸借契約及びこれに付随する塔屋の使用契約に関し、原告が借地借家法に基づく賃料減額請求により減額されたはずの賃料及び共益費の確認等の請求を行い、被告が、借地借家法に基づく賃料増額請求により増額されたはずの賃料及び共益費の確認等を求める反訴を提起した件に関し、原告の請求が一部認容された事例。
主文
1 被告が原告に賃貸している別紙2物件目録2記載の各部分の基本賃料の合計額は、平成24年12月22日以降、月額3490万9000円(消費税別)であることを確認する。
2 被告は、原告に対し、8820万6179円及び別表1「附帯請求認容額一覧」の各「元金」欄記載の各金員に対する同各「起算日」欄記載の各日から支払済みまでそれぞれ年1割の割合による金員を支払え。
3 原告が被告に対して支払うべき別紙1物件目録1記載2の建物の塔屋部分に係る広告宣伝使用料は、月額50万0400円(消費税別)であることを確認する。
4 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
5 被告の反訴請求に係る訴えのうち、別紙2物件目録2記載の各部分の共益費の確認を請求する部分を却下する。
6 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
8 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
(略語)
本判決においては、別紙1ないし3の各物件目録記載の各物件につき、以下の略語を用いる。
別紙1物件目録1記載1の土地 本件土地
別紙1物件目録1記載2の建物 本件建物
別紙1物件目録1記載3の土地 隣接地
別紙2物件目録2記載1の部分 本件建物部分1
別紙2物件目録2記載2の部分 本件建物部分2
別紙2物件目録2記載3の部分 本件建物部分3
本件建物部分1から3まで (併せて)本件各建物部分
別紙3物件目録3記載1の部分 当初建物部分1-1
別紙3物件目録3記載2の部分 当初建物部分1-2
別紙3物件目録3記載3の部分 途中建物部分1
本件建物の塔屋部分 本件塔屋
第1 請求
1 本訴請求
(1) 主位的請求
ア 被告が原告に賃貸している本件各建物部分の基本賃料の合計額は、平成24年12月22日以降、月額2815万9000円(消費税別)であることを確認する。
イ 被告が原告に賃貸している本件各建物部分の共益費の合計額は、平成24年12月22日以降、月額533万8657円(消費税別)であることを確認する。
ウ 被告は、原告に対し、6億0005万8074円及び別表2「附帯請求請求額一覧」の各「元金」欄記載の各金員に対する同各「起算日」欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年1割の割合による金員を支払え。
エ 原告が被告に対して支払うべき本件塔屋に係る広告宣伝使用料は、月額50万0400円(消費税別)であることを確認する。(主文第3項と同旨)
(2) 予備的請求(上記(1)イ及びウの共益費に係る部分につき)
被告は、原告に対し、1973万2545円及びこれに対する平成27年3月25日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 反訴請求
(1) 被告が原告に賃貸している本件各建物部分の基本賃料の合計額は、平成25年3月1日以降、月額4182万9000円(消費税別)であることを確認する。
(2) 被告が原告に賃貸している本件各建物部分の共益費の合計額は、平成24年11月1日から平成25年3月31日までにおいて、月額885万9379円(消費税別)であることを確認する。
(3) 原告が被告に対して支払うべき本件塔屋に係る広告宣伝使用料は、平成24年11月1日以降、月額83万4000円(消費税別)であることを確認する。
第2 事案の概要
1 事案の骨子
本件は、被告を賃貸人とし、原告を賃借人とする本件各建物部分の賃貸借契約及びこれに付随する本件塔屋の使用契約に関し、以下の本訴請求及び反訴請求から成る事案である。
(1) 本訴請求
原告が、本件各建物部分の現行の基本賃料(月額3639万6740円。消費税別)及び共益費(月額722万1867円。消費税別)が不相当に高額となっており、また、本件塔屋に係る広告宣伝使用料(月額50万0400円。消費税別)の増額を求める被告の請求(後記(2)ウ)は根拠を欠くなどと主張して、被告に対し、以下の各事項を求める事案である。
ア 上記基本賃料につき、〈1〉 借地借家法32条1項に基づく減額請求により減額されたことを前提に、同請求の日である平成24年12月22日以降、月額2815万9000円(消費税別)であることの確認(上記第1の1(1)ア)及び、〈2〉 同条3項に基づき、同日から平成29年6月24日に支払った分までの超過額(消費税込)として合計4億8840万4968円及び各超過額(別表2「附帯請求請求額一覧」の「賃料」欄記載の各金額)に対する各受領の日(同「起算日」記載の各日)から支払済みまで同項所定の年1割の割合による利息の支払(上記第1の1(1)ウの一部)
イ 上記共益費につき、
(ア) 主位的に、〈1〉 借地借家法32条1項に基づく減額請求により減額されたことを前提に、同請求の日である平成24年12月22日以降、月額533万8657円(消費税別)であることの確認(上記第1の1(1)イ)、及び、〈2〉 同条3項に基づき、同日から平成29年6月24日までに支払った分の超過額(消費税込)として、合計1億1165万3106円及び各超過額(別表2「附帯請求請求額一覧」の「共益費」欄記載の各金額)に対する各受領の日(同「起算日」記載の各日)から支払済みまで同項所定の年1割の割合による利息の支払(上記第1の1(1)ウの一部)
(イ) 予備的に、暫定的な支払額である上記共益費と確定した実費の金額との差額を清算する旨の合意により生ずる清算金請求権に基づき、平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月31日)分の超過額(消費税込)として1973万2545円及びこれに対する平成27年3月25日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(同(2))
ウ 本件塔屋に係る広告宣伝使用料につき、上記賃貸借契約に基づき、現行の月額50万0400円(消費税別)のままであることの確認(上記第1の1(1)エ)
(2) 反訴請求
被告が、本件各建物部分の現行の基本賃料及び共益費が不相当に低額となっており、また、本件塔屋に係る広告宣伝使用料が不確定期限の到来により現行の額に減額される前の額(月額83万4000円。消費税別)に復したなどと主張して、原告に対し、以下の各事項を求める事案である。
ア 上記基本賃料につき、借地借家法32条1項に基づく増額請求により増額されたことを前提に、同請求の日である平成25年3月1日以降、月額4182万9000円(消費税別)であることの確認(上記第1の2(1))
イ 上記共益費につき、平成24年11月1日から平成25年3月31日までの分につき、暫定的な支払額と前年度の実費に基づき協議して決定する旨の合意に基づき、その額が月額885万9379円(消費税別)であることの確認(上記第1の2(2))
ウ 本件塔屋に係る広告宣伝使用料につき、減額前の月額83万4000円(消費税別)であることの確認(上記第2の2(3))
2 前提事実(争いのない事実、後掲各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者(弁論の全趣旨)
ア 原告
原告は、平成18年3月1日に設立された、百貨店業、商業ビルの管理、運営等を目的とする株式会社であるところ、その設立に至る経緯及び現在に至るまでの経緯は、以下のとおりである。
(ア) 株式会社十字屋(以下「十字屋」という。)は、平成7年9月1日、株式会社ダイエー・アゴラ(以下「ダイエー・アゴラ」という。)を吸収合併した(その登記は同年12月8日に経由された。)。ダイエー・アゴラは、その当時、株式会社ダイエー(以下「ダイエー」という。)の完全子会社であった。(甲2)
(イ) 十字屋及びその親会社であるダイエーは、平成16年12月28日、株式会社産業再生機構法22条3項に基づく支援決定を受けた。(乙13)
(ウ) 十字屋は、平成17年7月1日、ダイエーの完全子会社となった。(乙35・参考資料〈6〉~〈8〉)
(エ) 十字屋は、平成18年3月1日、会社分割(新設分割)により、原告をその完全子会社として設立した。(乙15、35・参考資料〈6〉~〈8〉)
(オ) ダイエーは、平成19年1月16日、十字屋を吸収合併した。これにより、原告はダイエーの完全子会社となった。
イ 被告(乙10、25・資料60、乙39の1、2)
(ア) 被告は、昭和53年11月6日に設立された、ホテル業、不動産の賃貸業等を目的とする株式会社である。
(イ) 被告の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までである。
(2) 対象不動産等(甲8、10、23、乙1、18~20、23、25・資料44、弁論の全趣旨)
ア 本件土地等
(ア) 本件土地及び隣接地は、JR・E駅、G・I駅に隣接している。
(イ) 隣接地は、J・I駅に隣接している。
(ウ) 本件土地及び隣接地は、平成11年9月1日以降、西日本旅客鉄道株式会社が所有している。
イ 本件建物
(ア) 本件建物(昭和56年3月5日新築)は、本件土地上に建築された、「Kビル」という名称の地下2階付14階建のビルである。
(イ) 本件建物は、地下2階、1階、2階及び3階に出入口が設けられ、地下2階の出入口は地下通路と、2階及び3階は駅前広場(ペデストリアンデッキ)と接続している。
(ウ) 被告は、昭和56年5月1日当時、本件建物のうち2階部分から13階部分を所有していた。被告は、平成13年10月1日、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発に対し、上記部分に係る持分1万分の3287を売った。
(エ) 西日本旅客鉄道株式会社は、本件建物のうち地下2階部分から1階部分を所有している。同社は、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発に対し、上記部分を賃貸している。そして、同社は、被告に対し、上記部分を賃貸(転貸)している。
(オ) 被告は、本件建物のうち本件各建物部分を除く部分について、ホテルの営業等を行っている。
(3) 本件賃貸借契約の概要(甲1、2、7、9、23、弁論の全趣旨)
被告は、遅くとも平成23年6月17日以降、原告に対し、要旨、以下の約定により、本件各建物部分を賃貸している(以下「本件賃貸借契約」という。)。ただし、後記(6)エ及びカのとおり、基本賃料及び共益費につき、借地借家法32条1項に基づく増減額の請求がされている。また、後記第3の2、11及び12のとおり、本件各建物部分の賃料の直近合意時点及び平成24年11月22日以降の本件塔屋に係る広告宣伝利用料の金額につき、当事者間で争いがある。
ア 基本賃料(以下「本件賃料」という。)
月額3639万6740円(消費税別)(以下「現行賃料」という。)
(内訳)
〈1〉 本件建物部分1
月額3311万2000円(以下「現行賃料1」という。)
〈2〉 本件建物部分2
月額 134万5740円(以下「現行賃料2」という。)
〈3〉 本件建物部分3
月額 193万9000円(以下「現行賃料3」という。)
イ 共益費(以下「本件共益費」という。)
月額722万1867円(消費税別)(以下「現行共益費」という。)
(内訳)
〈1〉 本件建物部分1
月額 664万5800円(以下「現行共益費1」という。)
〈2〉 本件建物部分2
月額 28万5521円(以下「現行共益費2」という。)
〈3〉 本件建物部分3
月額 29万0546円(以下「現行共益費3」という。)
ウ 歩合賃料
原告の本件各建物部分における売上高が年額72億円を上回った場合に、当該上回った額に対して1%を乗じた額
エ 本件塔屋の利用
原告は広告宣伝に必要な設備を本件塔屋に設置することができ、その使用料(以下「本件塔屋使用料」という。)として、被告に所定の月額を支払う。
(4) 本件各建物部分の利用状況(甲8、10、23、30、40、乙1、40~42、弁論の全趣旨)
原告は、「L」という名称で、本件各建物部分において衣料品及び雑貨の販売を中心とする商業施設を運営し、複数の小売業者に対し、上記部分を店舗として転貸している。
(5) 本件賃貸借契約の推移
以下のとおり、ダイエー・アゴラ及び十字屋と被告との間で、本件各建物部分及び本件塔屋に係る賃貸借契約及びその内容の変更契約が締結され、原告が賃借人の地位を承継した結果、現行の本件賃貸借契約に至った。その概要は、別表3「本件建物賃貸借契約の経緯について」のとおりである。
ア 本件原始契約1(甲2)[別表3「平成7年8月29日」欄]
被告は、平成7年8月29日、ダイエー・アゴラに対し、要旨、以下の約定で、当初建物部分1-1(別紙3物件目録3記載1の部分)を賃貸した(以下「本件原始契約1」という。)。被告は、同年9月30日、同契約に基づき、ダイエー・アゴラに対して当該部分を引き渡した。
(ア) 使用目的
百貨店業等の営業及びこれに付帯関連する業務
(イ) 賃貸期間
平成7年10月1日から20年間。ただし、期間満了の6か月前までに当事者のいずれも更新拒絶の意思表示をしないときは更に3年更新され、以後も同様とする。
(ウ) 基本賃料
月額3291万7000円(消費税別)。当月分を前月25日までに支払う。
基本賃料は起算日より3年間据え置き、満3年経過時及び以降3年経過ごとに協議の上改定する。ただし、経済情勢等に著しい変動を生じた場合には、別途協議することができる。
(エ) 共益費
別途協議の上決定する基準に基づき被告が計算した以下の費用(〈4〉以下は固定関係経費)を毎月支払う。以下の費用及び専用施設の諸経費(ダイエー・アゴラの負担)以外のものでいずれの負担に属するか明らかでない経費については、協議の上分担を決定するものとする。
〈1〉 冷暖房換気に関する経費
〈2〉 電灯、電力に関する経費
〈3〉 給排水に関する経費
〈4〉 清掃衛生に関する経費
〈5〉 昇降機等機械関係経費
〈6〉 保安に関する経費
〈7〉 その他共用部分に関する経費
(オ) 歩合賃料
ダイエー・アゴラの上記賃借部分における売上高が前年度の売上高を超過した場合に、当該超過額に2%を乗じた額。金額が確定した月の翌月25日に支払う。
(カ) 本件塔屋の利用
ダイエー・アゴラは広告宣伝に必要な設備を本件塔屋に設置することができ、その使用料として月額83万4000円を支払う。
(キ) 敷金 4億6419万2100円
(ク) 保証金 18億5676万8400円
(ケ) 特記事項
被告は、ダイエー・アゴラが十字屋と平成7年9月1日付けで合併することに伴い、同日以降は本契約に関するダイエー・アゴラの債権債務一切を十字屋が継承することを確認する。
イ 本件原始契約2(甲3)[別表3「平成7年9月27日」欄]
被告は、平成7年9月27日、十字屋に対し、要旨、以下の約定で、当初建物部分1-2(別紙3物件目録3記載2の部分)を賃貸した(以下「本件原始契約2」という。)。被告は、同年10月1日までに、同契約に基づき、十字屋に対して当該部分を引き渡した。
(ア) 使用目的 事務室・倉庫
(イ) 賃貸期間
平成7年10月1日から平成10年9月30日まで。ただし、期間満了の6か月前までに当事者のいずれも更新拒絶の意思表示をしないときは更に2年更新され、以後も同様とする。
(ウ) 賃料
月額26万6000円(消費税別)。毎月25日までに当月分を支払う。
(エ) 共益費
月額7万9800円(消費税別)。賃料に準じて支払う。
(オ) 賃料及び共益費の改定
契約期間中であっても、公租公課の増徴、土地建物の価格の高騰、施設の改造、建物の保全費の増加、建物管理費の増加、その他負担の増加及び経済情勢の変動等、やむを得ない事由があるとき、並びに近隣の建物に比較して著しく不相当と認められたときは、被告は賃料及び共益費を改定することができる。
(カ) 敷金 478万8000円
ウ 本件共益費覚書(甲13、乙6)[別表3「平成8年2月1日」欄]
十字屋と被告は、平成8年2月1日、本件原始契約1に基づく共益費について、要旨、以下のとおりとする旨を記載した「共益費に関する覚書」と題する書面(以下「本件共益費覚書」という。)を作成した。
(ア) 平成7年度(同年4月1日~平成8年3月31日)分は暫定額として月額656万6000円とし、その実費が確定した時点で清算する。
(イ) 平成8年度以降の共益費の額については、別途定める。
エ 本件塔屋覚書(甲12)
十字屋と被告は、平成12年7月1日付けで、本件原始契約1による本件塔屋の使用につき、当分の間において、使用料を月額50万0400円とする合意をした旨を記載した覚書(以下「本件塔屋覚書」という。)を作成した。
オ 本件変更契約1(甲7、弁論の全趣旨)[別表3「平成13年12月7日」欄]
十字屋と被告は、平成13年12月7日、本件原始契約1及び2に関し、要旨、その内容を次のとおりに変更する旨を合意した(以下「本件変更契約1」という。)。被告は、その頃、十字屋に対し、同契約に基づき、その対象となった部分を引き渡した。
(ア) 賃貸借の対象
途中建物部分1(別紙3物件目録3記載3の部分)に変更する。また、本件原始契約2の賃貸借の対象は、途中建物部分1のうち地下1階の一部分(53.2m2)に該当するものとする。
(これにより、本件原始契約1の対象部分について11.28m2の減床がされ、同2の対象部分についてこれと同一の面積に相当する他のフロアに変更された。)。
(イ) 賃料
〈1〉 本件原始契約1の基本賃料を、平成13年3月1日以降、月額3284万6000円に改める。
〈2〉 本件原始契約2の基本賃料及び共益費は、従前のとおりとする。
〈3〉 本件原始契約1の歩合賃料については、平成13年10月1日から平成16年9月30日までの3年間、暫定的に、売上高が年額70億円を上回った場合に、当該上回った額に1%を乗じた額とする。
カ 本件変更契約2(甲9)[別表3「平成18年1月24日」欄]
十字屋と被告は、平成18年1月24日、本件原始契約1及び本件変更契約1に関し、要旨、その内容を次のとおり変更する旨を合意した(以下「本件変更契約2」という。)。被告は、その頃、十字屋に対し、同契約に基づき、本件建物部分2を引き渡した。
(ア) 賃貸借の対象
本件建物部分2を追加する(3階部分を拡張する。)。
(イ) 賃料及び共益費
〈1〉 平成17年9月1日以降、基本賃料を月額134万5740円(現行賃料2と同額)とする。
〈2〉 平成17年9月1日以降、共益費を月額28万5521円(現行共益費2と同額)とする。
〈3〉 本件原始契約1の歩合賃料については、本件変更契約1から継続して、売上高が年間70億円を上回った場合に、当該上回った額に1%を乗じた額とする。
(ウ) 賃料改定の時期
本件原始契約1の定めるところによる。
(エ) その他
変更した事項以外については、本件原始契約1に係る契約書で定めるとおりとする。
キ 本件承継覚書(乙15)
原告と被告は、平成22年4月1日、要旨、以下の記載のある「賃借人地位承継に関する覚書」と題する書面(以下「本件承継覚書」という。)を作成した。
(ア) 平成18年3月1日付け会社分割により原告が十字屋から新設され、同日付けをもって、本件原始契約1上の十字屋の賃借人の地位(権利・義務一切及び営業場所にかかわる資産)が原告に承継されていることを確認する。
(イ) 本覚書は平成18年3月1日に遡って効力を生じる。
(ウ) 本覚書に定める事項以外、本件原始契約1及びこれに付随する各種の契約書等に何ら変更のないことを相互に確認する。
ク 本件変更契約3(甲1、弁論の全趣旨)[別表3「平成23年6月17日」欄]
原告と被告は、平成23年6月17日、本件原始契約1並びに本件変更契約1及び2に関し、要旨、その内容を以下のとおり変更する旨を合意した(以下「本件変更契約3」という。)。被告は、同年9月30日頃、原告に対し、同契約に基づき、その対象となった部分を引き渡した。
(ア) 賃貸借の対象
本件建物部分3(2階部分の217.81m2及び3階の倉庫部分の8.90m2)を追加するとともに、地下1階の倉庫部分の一部(0.78m2)を解約する。これにより、平成23年9月30日をもって、賃貸借の面積は5606.97m2(各階の面積は別紙物件目録2記載のとおり)となる。
(イ) 賃料及び共益費
〈1〉 基本賃料
上記(ア)の賃借面積の変更により、本件原始契約1の基本賃料を、平成23年10月1日以降、月額3445万7740円(6404円/m2、消費税別)から月額3639万6740円(6491円/m2、消費税別。現行賃料と同額)に改める。
なお、上記基本賃料の改定時期は、本件原始契約1の定めによるものとし、上記基本賃料の変更については、借地借家法32条による賃料増額請求に基づく改定とはみなさない。
〈2〉 共益費
上記〈1〉に伴い、本件原始契約1の共益費を、平成23年10月1日以降、月額693万1321円(1288円/m2、消費税別)から月額722万1867円(1288円/m2、消費税別。現行賃料と同額)に改める。
〈3〉 歩合賃料
本件原始契約1の歩合賃料につき、本件変更契約1で定めた基準売上高を年間70億円から年間72億円に改定し、変更後の基準売上高を上回った額に1%を乗じた額を支払う。
(ウ) 敷金(上記(ア)による増床部分に係るもの)
2660万円
ケ 契約の更新(弁論の全趣旨)
本件賃貸借契約は、本件原始契約1の賃貸期間が開始してから現在まで、その賃貸人又は賃借人が相手方に対して解約の申入れをしたことはないため、借地借家法26条1項又は同契約の約定により更新され、存続している。
(6) 本件訴えに至る経緯(弁論の全趣旨)
ア 被告は、平成24年6月28日、原告に対し、〈1〉 同年8月末をもって本件塔屋覚書に基づく本件塔屋使用料の減額措置を取り止めたい、〈2〉 本件共益費を適正化して月額1102万8910円(1m2当たり1967円)、としたい、〈3〉 本件賃料を改定したい旨の提案をした。(甲14)
イ 被告は、平成24年9月7日、原告に対し、自らが適正と考える本件共益費の額として、月額939万1675円(1m2当たり1675円)を提示した。もっとも、原告は、被告の求める共益費の増額に応じなかった。(甲15、29)
ウ 被告は、平成24年11月22日、原告に対し、〈1〉 同月分から、本件塔屋使用料として減免前の月額83万4000円(消費税別)を請求する、〈2〉 同月分から、本件共益費として月額843万2882円(消費税別)を請求する旨を通知した。(甲4、5、11)
エ 原告は、平成24年12月22日、被告に対し、借地借家法32条1項に基づき、同日以降、本件賃料(現行賃料3639万6740円)及び本件共益費(現行共益費722万1867円)を相当額に減額することを請求した(以下「本件減額請求」という。)。(甲6の1・2)
オ 原告は、平成25年1月17日、被告に対し、上記第1の1(1)ア、イ及びエと同様の事項を求め、民事調停の申立てをした(神戸簡易裁判所平成25年(ユ)第3号賃料減額確認調停申立事件)。
カ 被告は、平成25年2月21日、原告に対し、借地借家法32条1項に基づき、同年3月1日以降、本件賃料を相当額に増額することを請求した(以下「本件増額請求」という。)。(乙5)
キ 上記オの民事調停は、平成25年3月15日、不成立により終了した。
ク 原告は、平成24年11月30日以降、被告に対し、別表4の「支払賃料」の「合計」欄記載のとおり、本件賃料及び本件共益費として、現行賃料(月額3639万6740円及び消費税)並びに現行共益費(月額722万1867円及び消費税)に相当する額を支払っている。
(7) 本件訴えの経過(当裁判所に顕著)
ア 原告は、平成25年3月25日、上記第1の1(1)ア、イ及びエを求め、本訴を提起した。
イ 被告は、平成25年5月21日、上記第1の2(1)から(3)まで(ただし、(2)につき、確認の対象とする共益費の終期を定めていなかった。)を求め、反訴を提起した。
ウ 原告は、平成27年3月17日、上記第1の1(2)の請求(同(1)イの予備的請求)を、本訴請求に追加する旨の訴えの変更の申立てをした。
エ 被告は、平成28年2月10日、上記第1の2(2)のとおり請求を特定する(確認の対象とする共益費の終期を定める)旨の訴えの変更の申立てをした。
オ 当裁判所は、平成28年9月13日の本件弁論準備手続期日において、M不動産鑑定士(以下「以下「裁判所鑑定人」という。)を、本件訴えの鑑定人に選任した。
カ 裁判所鑑定人は、〈1〉 平成28年11月11日付けで、本件各建物部分の適正賃料(継続賃料)を鑑定した鑑定書、及び適正共益費を鑑定した意見書を作成するとともに、〈2〉 平成29年3月13日付けで、同鑑定書に対する原告と被告の質問事項への回答を内容とする鑑定補充書(2通)を作成した(以下では、これらを併せて「裁判所鑑定書」という。)。
キ 原告は、平成29年7月13日、上記第1の1(1)ウの請求(同ア及びイの附帯請求)を、本訴請求に追加する旨の訴えの変更の申立てをした。
ク 本件訴えにおいて、本件各建物部分の適正賃料(継続賃料)の額につき、〈1〉 原告は、株式会社プライム評価研究所(N不動産鑑定士)の作成した平成24年12月7日付け不動産鑑定評価書(2通。以下「原告鑑定書」という。)を提出している一方、〈2〉 被告は、株式会社横須賀不動産鑑定事務所(O不動産鑑定士、P不動産鑑定士)の作成した平成25年4月25日付け不動産鑑定評価書(以下「被告鑑定書」という。)を提出している。(甲8、10、乙1)
3 争点
以下では、本件賃料、本件共益費及び本件塔屋使用料の各金額は、特に断りのない限り、消費税別の金額をもって表記する。
(1) 本案前の争点-反訴請求(2)について(争点1)
本件共益費の額を前年度の実費に基づいて協議して決定する旨の合意に基づき、その額の確認を求める反訴請求(2)に係る訴えは、適法であるか。
(2) 本案の争点
ア 本件賃料の増減請求に係る争点-本訴請求(1)ア・ウ及び反訴請求(1)について(争点2)
(ア) 原告又は十字屋と被告が、現実に現行賃料1の額を合意した直近の時点(以下「直近合意時点」という。)はいつか。[争点2-1]
なお、現行賃料2の直近合意時点が平成17年9月1日(本件変更契約2による変更の始期)であることについては、当事者間に争いはない。
(イ) 本件賃料(現行賃料)の額は、平成24年12月22日(本件減額請求がされた日)当時又は平成25年3月1日(本件増額請求による効力が発生するとされた日)当時、不相当に高額又は低額であったか。また、その当時における本件賃料の相当額は、いくらであったか。[争点2-2]
ただし、上記が具体的に問題になるのは、現行賃料1から3までのうち、同1及び2のみである。
イ 本件共益費に係る争点(争点3)
(ア) 本件共益費に関する合意内容に係る争点-本訴請求(1)イ・ウ及び(2)並びに反訴請求(2)について(争点3-1)
a 十字屋と被告は、本件共益費覚書において、平成8年度以降の本件共益費につき、どのような合意をしたか。[争点3-1-1]
b 原告又は十字屋と被告の間において、平成24年12月22日(本件減額請求がされた日)までに、現行共益費の金額をもって本件共益費を固定する旨の合意が成立していたか。[争点3-1-2]
(イ) 本件共益費の減額請求に係る争点-本訴請求(1)イ及びウについて(争点3-2)
a 本件共益費が、借地借家法32条1項に基づく減額請求の対象となるか。[争点3-2-1]
b 本件共益費の額は、平成24年12月22日(本件減額請求がされた日)当時、不相当に高額であったか。また、その当時における本件共益費の相当額は、いくらであったか。[争点3-2-2]
(ウ) 本件共益費に関するその余の請求に係る争点-本訴請求(2)及び反訴請求(2)について(争点3-3)
a 本件共益費に含まれる実費の範囲(費目)は何か。[争点3-3-1]
b 平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月31日)の本件共益費はいくらか。[争点3-3-2]
c 平成24年11月1日から平成25年3月31日までの本件共益費はいくらか。[争点3-3-3]
ウ 本件塔屋使用料の額の確認請求に係る争点-本訴請求(1)エ、反訴請求(3)について(争点4)
(ア) 十字屋と被告は、本件塔屋覚書において、本件塔屋使用料の減額につき不確定期限(終期)を付す旨の合意をしたか。[争点4-1]
(イ) 本件口頭弁論終結日(平成29年11月21日)までに、上記不確定期限が到来したか。その場合、その時期はいつか。[争点4-2]
第3 争点に対する当事者の主張
1 争点1(反訴請求(2)の適法性)について
(被告の主張)
原告と被告は、平成8年度以降の本件共益費につき、実費を確定して清算することも、別途その金額を決定することもできていない。この点、本件共益費の金額は各年度で同一ではないが、平成24年11月1日から平成25年3月31日までの分の算定方式が裁判所により決定されれば、原告と被告は、それ以降の分についても、その金額を確定することができる。
したがって、本件共益費の額を前年度の実費に基づいて協議して決定する旨の合意に基づき、その額の確認を求める反訴請求(上記第1の2(2))に係る訴えは、確認の利益を有し、適法である。
(原告の主張)
本件共益費に関し、原告(又は十字屋)と被告との間では、平成8年度以降の分につき汎用性のある決定方法が合意されていないところ、新たな合意に達することのないまま協議が尽きているから、裁判所において、形成的・創造的にその額を認定することはできない。
なお、本件共益費が実費に基づいて年度ごとに確定するものであるとすれば、被告は、現行共益費と実費との差額分につき、その支払を求める給付訴訟を提起することができる。
よって、本件共益費の額を前年度の実費に基づいて協議して決定する旨の合意に基づき、その額の確認を求める反訴請求(上記第1の2(2))に係る訴えは、確認の利益を欠き、不適法である。
2 争点2-1(現行賃料1の直近合意時点)について
(原告の主張)
現行賃料1(月額3311万2000円)の直近合意時点は、平成7年10月1日である。
(1) 本件変更契約1による賃料合意の有無
本件建物部分1に係る基本賃料は、〈1〉 本件原始契約1及び2の賃貸期間が開始した平成7年10月1日当時、月額3318万3000円であったところ、〈2〉 本件変更契約1(平成13年12月7日付け)により、平成13年3月1日から月額3311万2000円と変更された。
上記〈1〉の内訳は、当初建物部分1-1の対象面積(5114.83m2)につき3291万7000円(6436円/m2)、当初建物部分1-2の対象面積(53.2m2)につき26万6000円(5000円/m2)であった。
他方、上記〈2〉の内訳は、同記載3の対象面積の一部(5156.75m2から後記53.2m2を控除した5103.55m2)につき3284万6000円(6436円/m2)、その余の対象面積(53.2m2)につき26万6000円(5000円/m2)である。
そうすると、1m2当たりの賃料は、上記〈1〉及び〈2〉のいずれも6436円(53.2m2以外の部分)及び5000円(53.2m2の部分)であり、これらを区分せずに計算したとしても6421円である。
したがって、本件建物部分1に係る基本賃料の単価は、本件変更契約1により変更されていないから、同契約による賃料変更の時期は、賃料を現実に合意した直近合意時点には当たらない。
(2) 本件変更契約2による賃料合意の有無
本件変更契約2(平成18年1月24日付け)は、本件建物部分2を新たに追加的に賃借することを目的として締結されたものであって、同契約で変更した事項以外については、本件原始契約1に定めるとおりとしているにすぎず、同契約の内容を確認したにとどまるものである。このことは、本件変更契約2により、本件建物部分1に係る基本賃料の単価(単位面積当たりの賃料)が変更されていないことからも明らかといえる。
この点、上記のような条項は、賃借条件の一部を変更するに際し、しばしば設けられるが、それ自体に特段の形成的な意味はない。このことは、本件承継覚書(平成22年4月1日付け)における、本覚書に定める事項以外、本件原始契約1及びこれに付随する契約書等に何らの変更のないことを確認する旨の定めが、本件建物部分1に係る基本賃料の額を現実に合意するものではないことと同じである。
上記のとおり、本件変更契約2の締結に当たり、十字屋と被告は、本件建物部分1に係る基本賃料の額につき実質的な交渉を行っていないから、両者の間で、その当時の経済事情等に応じた相当な賃料が現実に合意されたわけではない。したがって、同契約による本件賃貸借契約の変更の始期である平成17年9月1日は、賃料を現実に合意した直近合意時点には当たらない。
(3) 改定条項に基づく協議の不存在
本件原始契約1は、3年ごとに基本賃料を改定する旨を定めているが、実際には、原告(又は十字屋)と被告との間で、本件建物部分1に係る基本賃料の改定についての協議は行われていない。
(4) 被告の認識
被告は、平成24年6月28日、書面及び口頭で、原告に対し、平成7年に締結した本件原始契約1及び2以降、本件建物部分1に係る基本賃料を改定したことがなく、その額が不変のまま推移してきたことを指摘した。また、被告は、本件訴えにおいても、これと同様の主張を繰り返している。
このことは、被告自身、平成7年10月1日が現行賃料1の直近合意時点であると認識していた証左である。
(5) 小括
以上によれば、現行賃料1の直近合意時点は、本件原始契約1及び2の賃貸期間が開始した平成7年10月1日である。
(被告の主張)
現行賃料1(月額3311万2000円)の直近合意時点は、平成17年9月1日である。
(1) 本件変更契約2について
本件変更契約2(平成18年1月24日付け)は、本件建物部分2の貸増しに際して作成されたものではあるものの、その点のみならず、既存の賃貸借部分である本件建物部分1について、賃料の点を含め、その契約内容を再度合意したものである。
すなわち、本件賃貸借契約において、歩合賃料は基本賃料と一体となって賃料を形成するところ、本件変更契約2は、同1(平成13年12月7日付け)における歩合賃料に係る暫定的な合意を継続する旨合意している上、変更した事項以外については、本件原始契約1に定めるとおりとすると定め、基本賃料の額を積極的に確認している。
したがって、本件変更契約2による変更の始期である平成17年9月1日は、賃料を現実に合意した直近合意時点に当たる。
(2) 本件承継覚書について
本件承継覚書(平成22年4月1日付け)は、合併に伴い賃借人の地位が承継される際に一般的に作成される書面であって、単に地位の承継があったことを確認したものにすぎず、それを超えて賃料の内容を積極的に合意するものではない。そうすると、本件承継覚書は、歩合賃料を含めた賃料が実質的に合意された本件変更契約2とは、性質を異にする。
したがって、本件承継覚書が作成された平成22年4月1日は、賃料を現実に合意した直近合意時点には当たらない。
(3) 本件変更契約3について
本件変更契約3(平成23年6月17日付け)は、基本賃料の変更については、借地借家法第32条による賃料増額請求に基づく改定とみなさないと明示している。
したがって、本件変更契約3による変更の始期である平成23年10月1日は、賃料を現実に合意した直近合意時点に当たらない。
(4) 賃料単価の変更がないことについて
確かに、本件建物部分1については、本件原始契約1及び2の賃貸期間が開始した平成7年10月1日以来、賃貸借の対象面積が変更されているものの、賃料単価には変化がない。
しかし、賃料の単価に変更があったか否かと、当事者が賃料額の合意をしたか否かは別問題であり、たとえ賃料の単価に変更がなくとも、当事者が従前と同一の単価とすることを改めて合意した場合には、当該合意をもって賃料額の直近合意とすべきことは当然である。むしろ、賃貸借契約の当事者間で、賃料に関する事項を含む書面が新たに作成された場合には、特段の事情のない限り、その時点において、賃料額についての合意がされたとみるのが、当事者の意思解釈として合理的である。
しかるところ、上記(1)のとおり、本件変更契約2において、十字屋と被告との間で本件建物部分1に係る賃料の合意がされたと解されるのである。
(5) 被告の言動について
確かに、被告は、原告に対し、平成7年以降の本件賃料の水準が不変である旨を指摘したことはある。
しかし、被告は、本件賃料の水準が不変であったという事実を指摘したにすぎず、原告又は十字屋と被告の間に賃料額の合意がなかったことまで主張しているわけではない。そして、直近合意時点の認定は、裁判所の法的判断によるところであるから、上記事実をもって、本件原始契約1及び2の締結以降、原告又は十字屋と被告の間に賃料額の合意がなかったということはできない。
(6) 小括
以上によれば、現行賃料1の直近合意時点は、本件変更契約2の変更の始期である平成17年9月1日である。
3 争点2-2(本件賃料の増減請求の可否及び相当額)について
(原告の主張)
平成24年12月22日(本件減額請求がされた日)当時、本件賃料の相当額は月額2815万9000円であったから、本件賃料(現行賃料)の額(月額3639万6740円)は不相当に高額であった。
(1) 現行賃料1について
ア 直近合意時点
上記2(原告の主張)のとおり、平成7年10月1日である。
イ 現行賃料の不当性
本件建物は、平成15年度から平成24年度までの9年間において、固定資産税及び都市計画税につき658万9501円(約25.9%)、その評価額につき3億8761万7700円の下落が生じている。平成14年度以前の分は明らかでないものの、上記を踏まえて概算すると、本件建物は、平成7年度から平成24年度までの間に、税額につき1244万6835円(約39.8%)、評価額につき7億3216万6766円の下落が生じていることとなる。
そして、原告鑑定書によれば、平成7年度から平成24年度までの間に、本件建物部分1の基礎価格につき37億1000万円(約59.8%)、一棟の建物の積算価格につき110億1000万円(約59.9%)、近隣の公示地価につき644万円/m2(約68.5%)の下落が生じている。
また、原告鑑定書によれば、平成7年度から平成24年度までの間に、経済変動を示す統計、具体的には、市街地価格指数につき67.8%、大型小売店商品販売額につき15.7%、地方別賃料指数につき41.8%、企業向けサービス価格指数につき5.8%の下落が生じている。
さらに、原告鑑定書によれば、近傍同種の建物の比準賃料(新規、実質賃料)は月額2370万円であるのに対し、現行賃料1は月額3389万4000円であって、不相当に高額であることは明らかである。
以上のとおり、本件建物部分1につき、土地又は建物に対する租税その他の負担の減少、土地又は建物の価格の低下、その他の経済事情の変更、近傍同種の建物の借賃等に加え、直近合意時点(平成7年10月1日)から本件減額請求(平成24年12月22日)まで17年以上が経過していることに照らすと、現行賃料1は不相当に高額となった。
ウ 本件賃料の相当額
上記イを踏まえた原告鑑定書(甲8)によれば、平成24年12月22日当時の本件建物部分1に係る適正な賃料の額は、月額2500万円となる。
また、裁判所鑑定書に必要な修正を加えると、同日当時の本件建物部分1に係る適正な賃料の額は、月額2460万円となる。
(2) 現行賃料2について
ア 直近合意時点
平成17年9月1日である。
イ 現行賃料の不当性
本件建物は、平成17年度から平成24年度までの7年間において、固定資産税及び都市計画税につき658万9501円(約25.9%)、その評価額につき3億8761万7700円の下落が生じている。
そして、原告鑑定書によれば、平成17年度から平成24年度までの間に、本件建物部分2の基礎価格(建物部分)につき1150万円(約25.4%)、一棟の建物の積算価格(建物部分)につき7億9000万円(約25.5%)の下落が生じている。
また、原告鑑定書によれば、平成17年度から平成24年度までの間に、経済変動を示す統計、具体的には、市街地価格指数につき15.4%、大型小売店商品販売額につき2.9%、地方別賃料指数につき13.5%、企業向けサービス価格指数につき5.5%の下落が生じている。
さらに、原告鑑定書によれば、近傍同種の建物の比準賃料(新規、実質賃料)は月額105万円であるのに対し、現行賃料2は月額134万5740円であって、不相当に高額であることは明らかである。
以上のとおり、本件建物部分2につき、土地又は建物に対する租税その他の負担の減少、土地又は建物の価格の低下、その他の経済事情の変更、近傍同種の建物の借賃等に加え、直近合意時点から本件減額請求まで7年以上が経過していることに照らすと、現行賃料2は不相当に高額となった。
ウ 本件賃料の相当額
上記イを踏まえた原告鑑定書(甲8)によれば、平成24年12月22日当時の本件建物部分2に係る適正な賃料の額は、月額122万円となる。
また、裁判所鑑定書に必要な修正を加えると、同日当時の本件建物部分2に係る適正な賃料の額は、月額117万円となる。
(3) 被告の主張について
被告は、〈1〉 本件建物が大都市圏のターミナル駅の駅ビルで立地がよいこと、〈2〉 本件建物における原告以外のテナントが、現行賃料より大幅に高い賃料を支払っていること、〈3〉 現行賃料3(本件建物部分3に係る賃料)の水準が高い上、平成23年9月には、原告が本件建物の他の部分についても現行賃料よりも高い水準での借入れを申し入れたこと、〈4〉 原告が、本件各建物部分につき、多額の転貸料を得ていることなどからすれば、現行賃料が不当に低額である旨を主張する。
しかし、上記〈1〉については、駅ビルの賃料は、駅ビルという類型や立地条件のみから決定されるわけではなく、新築後相当期間を経過しているか否かなど、集客力の多寡が影響する。また、被告の指摘する駅ビルの平均賃料は、本件建物の属する関西圏の駅ビルの賃料相場、本件建物と類似の規模の駅ビルの賃料相場を適切に反映したものであるかが明らかでない。
上記〈2〉については、現行賃料が適正であるか否かは、本件賃貸借契約と原告以外のテナントとの賃貸借契約との比較のみによって決まるものではない。加えて、これらの契約は対象面積が異なるから、両者の間で賃料単価が異なることも当然である。
上記〈3〉については、原告が現行賃料よりも高い水準での賃借の申入れを行ったのは、原告が、その当時、既存の賃借部分があることを前提に増床を検討していたところ、隣接して競合店が出店することを阻止するとともに、より広い連続した売場を構成することにより競争力を向上させ、全体として損益を向上させる目的を有していたからである。すなわち、上記申入れに当たっては、被告に強い交渉力があったにすぎない。
上記〈4〉については、原告が多額の転貸料を得ている事実はない。仮にそうであるとしても、それは、原告の営業努力によるものであること、原告の事業が、単なる転貸事業ではなく、テナントを統括して「L」という商業施設(10代前半から30代の女性を中心的な顧客とするファッション専門店ビル)を運営するという特殊なものであることなどを反映したものである。したがって、本件各建物部分に係る転貸料との比較から、現行賃料の金額が不当に低額と判断されることはない。
(4) 小括
以上のとおり、平成24年12月22日当時、本件賃料の相当額は月額2815万9000円(内訳は、本件建物部分1につき月額2500万円、同2につき月額122万円、同3につき月額193万9000円)であったから、現行賃料の額(月額3639万6740円)は不相当に高額であった。
(被告の主張)
平成25年3月1日(本件増額請求による効力が発生するとされた日)当時、本件賃料の相当額は月額4182万9000円であったから、本件賃料(現行賃料)の額(月額3639万6740円)は不相当に低額であった。
(1) 直近合意時点
上記2(被告の主張)のとおり、本件建物部分1及び2のいずれについても、平成17年9月1日である。
(2) 現行賃料1及び2の不当性
ア 本件建物の特殊性
本件賃貸借契約の対象である本件建物(Kビル)は、関西圏の代表的な都市の一つであるQの中心という希少立地に位置し、しかも、複数の交通機関が集中するターミナルに当たる駅ビルである。しかるところ、駅ビルの賃料相場は、一般的に他の物件よりも抜きん出て高く、また、商業施設の賃料額は、地価等の不動産の価格ではなく、集客力及び利便性(収益力)により左右される。
したがって、本件賃料の相当額を決定するに当たっては、不動産価格や物価等の一般的な経済動向、新築からの経過年数、他の収益力の劣る商業施設の賃料水準等は、大きな意味を持たないというべきである。
このことは、日本ショッピングセンター協会の資料によれば、大都市の駅ビルにおける平均賃料は、平成17年において月額3万9455円/坪であったが、平成24年において月額7万0591円/坪と上昇していることからも裏付けられる。
また、被告の所属する企業グループでは、駅ビルを含めたショッピングセンター事業や百貨店事業を20数社営んでいるが、原告の本件建物における事業運営が特に優れた実績を示しているとは考えられず、原告のブランド力を大きく評価すべきではない。むしろ、上記のとおり、本件建物の売上げが向上しているのは、その立地が好条件にあることが大きいというべきである。
イ 現行賃料の額が決定及び維持された経緯
本件建物部分1及び2に係る賃料は、平成7年に阪神大震災が発生した直後であったため、低額に設定され、その後も、十字屋の親会社であるダイエーの業績が著しく悪い状態が継続したこと、ダイエー及びその関連会社の交渉力が勝っていたことなどから、その後修正されることのないまま、平成25年3月1日まで維持されてきた。
そして、上記賃料(現行賃料)は、その間、周辺の復興が遅れる中で本件建物に需要が集中して本件建物における売上が震災前よりも増加したこと、近傍同種の建物の賃料が上昇したことなどにより、相当額との間に乖離が生じている。
ウ 賃料相場からの乖離を裏付ける事情
被告鑑定書によれば、平成25年3月1日時点における近傍同種の建物の新規賃料は月額2万3070円/m2、継続賃料は8255円/m2であるのに対し、現行賃料は月額6491円/m2である。したがって、近傍同種の建物の借賃は、新規賃料及び継続賃料のいずれについても、現行賃料の水準を上回っている。
しかも、本件建物(1階部分)の2店舗の賃料(月額)は、2万4200円/m2、3万6300円/m2であって、原告以外のテナントに対する本件建物の賃料水準が、現行賃料の水準を大きく上回っている。
また、被告は、原告がエンドテナントから受領している本件各建物部分に係る賃料(転貸料)につき、売上歩合につき16.3~18.5%、最低保証賃料につき月額1万4500円~2万1400円/m2程度であると聞いている。しかるところ、原告は、この転貸料収入のうち月額6491円/m2(現行賃料)しか被告に支払っておらず、約55~70%の差益を得ている(転貸料の売上歩率を低めの16%で計算しても、原告は、月額9100万円以上の賃料収入を得ており、約60%の差益を得ていることになる。)。この点、転貸事業の一般的な売上歩率は15%程度である。このように、原告は、本件各建物部分につき、多額の転貸料を得ている(さらに、後記8(被告の主張)(1)のとおり、原告は、共益費の名目で、月額133万7684円を超える実質賃料を収受している。)。このことは、本件訴えにおいて、原告が頑なに転貸料収入の額を明らかにしようとしないことからも、明らかである。
さらに、原告は、本件変更契約3(平成23年6月17日付け)により、本件建物部分3を、当時の本件建物部分1及び2(月額6354円/m2)よりも2000円以上も高い賃料単価(月額8582円/m2)で賃借している上、同年9月には、被告に対し、本件建物の1階部分につき、現行賃料の4倍に当たる賃料単価(月額2万5757円/m2)での借入れを申し入れている。このように、原告自身、現行賃料の水準が低いことを認識している。
エ まとめ
以上のとおり、本件建物部分1及び2につき、近傍同種の建物の借賃等に加え、現行賃料の額が決定及び維持された経緯等に照らすと、現行賃料1及び2は不相当に高額となった。
(3) 本件建物部分1及び2に係る基本賃料の相当額
被告鑑定書(乙1)によれば、平成25年3月1日当時の本件建物部分1及び2に係る適正な賃料の額は、月額3989万円となる。
(4) 小括
以上のとおり、平成25年3月1日当時、本件賃料の相当額は月額4182万9000円(内訳は、本件建物部分1及び2につき月額合計3989万円、同3につき193万9000円)であったから、現行賃料の額(月額3639万6740円)は不相当に低額であった。
4 争点3-1-1(本件共益費覚書における合意内容)について
(被告の主張)
十字屋と被告は、本件共益費覚書において、平成8年度以降の本件共益費につき、毎年、その額を前年度の実費に基づき協議して決定する旨を合意した。
(1) 本件共益費覚書の内容
本件共益費覚書には、本件共益費につき、〈1〉 平成7年度(平成7年4月1日~平成8年3月31日)の分は、暫定額として月額656万6000円とし、実費が確定した段階で清算する、〈2〉 平成8年度以降の分は、別途定める旨が記載されている。
(2) 本件共益費覚書の趣旨
本件共益費のうち平成7年度の分については、阪神淡路大震災による混乱の中、経理上の理由から、暫定的にそれ以前の分の金額(固定額)をもって定めた上、その確定に当たっては、震災直後で経費が安定しておらず、半期のみ(同年10月1日~平成8年3月31日)の営業であったため、事後的に実費に基づいて清算することとした。
これに対し、平成8年度以降の分は、平成7年度の実績に加え、大規模修繕費用等を要したことを踏まえ、別途協議して決定するものとされた。もっとも、上記のとおり、本件建物の共益費は、平成4年度以降の分が固定額で運用されてきたことに鑑み、実績等を勘案して将来に向かって固定化した金額を決定する趣旨であった。
したがって、本件共益費覚書は、平成8年度以降の共益費については、平成7年度のように、当該年度の実費に基づいて事後的、機械的に金額を算定するのではなく、毎年、当事者において、前年度の実績を主な基準として(社会経済情勢又は物的設備等の変動が予定される場合には、それも考慮した上で)、その額を固定額として決定することを約した趣旨であると解される。
(3) 原告の主張について
原告は、本件共益費の実費清算について、現に支出された時期とは異なる年度の実費を基準とすることとなって不合理であると主張する。
しかし、このような算定方法であっても、本件共益費の実費が翌年度の額に反映されること、一般的に、共益費の額は近い年度間では大きな変動がないことなどからすれば、上記のような算定方法が不合理とはいえない。
(原告の主張)
(1) 主位的主張
十字屋と被告は、本件共益費覚書において、平成8年度以降の本件共益費につき、毎年協議して決定する旨を合意していない。
すなわち、被告は、平成8年度以降、十字屋又は原告に対し、本件共益費に係る実費の金額を提示して清算を求めたことはないのみならず、1年ごとに本件共益費の改定を求めたこともない。
(2) 予備的主張
十字屋と被告は、本件共益費覚書において、平成8年度以降の本件共益費につき、当該年度中に暫定的に一定額(現行共益費の額)を支払い、その後に確定した当該年度の実費の額との間に過不足が生じたときは、これを清算する(不足が生じたときは十字屋が差額の支払義務を負い、超過が生じたときは被告が差額の返還義務を負う。)旨を合意した。
すなわち、本件共益費覚書は、平成7年度の分は同年度の実費に基づいて確定し、平成8年度以降の分は別途協議するとしたものの、後者については、その額が十字屋又は原告と被告の協議によって決定されていない。しかるところ、一般的に、共益費が実費に基づいて算定されるものであることからすれば、ある年度における共益費の額は、当該年度に支出された実費の額に基づいて決定されると解される。そうであるとすれば、平成8年度以降の本件共益費の額は、当該年度の実費の額に基づいて確定されると解するのが、本件共益費覚書の合理的な解釈というべきである。
被告は、本件共益費の算定につき、前年度の実費の額に基づいて当該年度の額が決定される旨を主張するが、このような合意は不合理である上、そのような内容は本件共益費覚書に全く記載されていない。
5 争点3-1-2(本件共益費を固定する旨の合意の成否)について
(原告の主張)
原告又は十字屋と被告の間において、遅くとも平成24年12月22日(本件減額請求がされた日)までに、現行共益費の金額をもって本件共益費を固定する旨の合意が成立していた。
すなわち、上記4(原告の主張)(1)のとおり、被告は、平成8年度以降、十字屋又は原告に対し、本件共益費に係る実費の金額を提示して清算を求めたことはないのみならず、1年ごとに本件共益費の改定を求めたこともない。そして、十字屋又は原告は、平成8年度以降、毎年、被告に対し、現行共益費の単価(1288円/m2)に対象面積を乗じた額を支払い続けてきた。
したがって、十字屋と被告との間では、平成8年度末(平成9年3月31日)までには、毎年本件共益費を清算することはせず、現行共益費が実費に対応するものであることを前提に、現行共益費の金額をもって本件共益費を固定する旨の合意が成立していたものと解すべきである。仮にそうでないとしても、遅くとも本件減額請求がされた日(平成24年12月22日)までには、原告と被告の間で同旨の合意が成立していたと解すべきである。
(被告の主張)
原告又は十字屋と被告の間において、平成24年12月22日(本件減額請求がされた日)までに、現行共益費の金額をもって本件共益費を固定する旨の合意は成立していない。
確かに、平成8年度以降の本件共益費について、十字屋又は原告と被告との間では、協議は行われず、また、毎年支払われた現行共益費の清算も行われてこなかった。
しかし、その原因は、〈1〉 原告において、清算しない方が支払額が少なく有利であると判断し交渉しようとしなかったこと、〈2〉 その一方で、被告において、本件共益費覚書の作成に関与した代表取締役が退任した等の理由から業務の引継ぎが十分に行われず、その後の担当者が協議を失念し、又は、消費低迷の影響により、本件共益費の増額となるような協議をためらったことにあると思われる。
また、十字屋又は原告と被告は、既に暫定的に現行共益費の額の支払が完了し、かつ、異議を述べられなかった各年度の本件共益費については、無用の紛争を拡大させない趣旨から、その都度、黙示的に、当該支払額を当該年度分の額として確定する旨を合意したものと認められる。
そうすると、十字屋又は原告と被告との間で、平成8年度以降の本件共益費につき協議及び清算が行われなかったことをもって、将来に向かって、現行共益費の金額をもって本件共益費を固定する旨の合意が成立したということはできない。
6 争点3-2-1(本件共益費に対する借地借家法32条1項の適用の有無)について
(原告の主張)
借地借家法32条1項にいう「借賃」は、名目のいかんを問わず、賃貸人に支払われる全ての経済的な対価をいうところ、本件共益費は、本件建物の使用の経済的対価にほかならないから、上記「借賃」に当たる。
また、本件共益費は、本件賃料とは区別して合意されているが、上記5(原告の主張)のとおり、現行共益費の額による定額とされ、これと適正な共益費の水準との間に乖離が生じた場合には、これを是正する必要がある。
したがって、本件共益費は、借地借家法32条1項に基づく減額請求の対象となる。
(被告の主張)
共益費は、本来、賃貸人が立替払した賃借人が負担すべき実費であって、不動産の果実である賃料とは異なるものであるから、借地借家法32条に基づく増減請求の対象とはならないのが原則である。この点、賃料と共益費を区別しない賃貸借契約においては、賃料と共益費の合計額が上記請求の対象となる余地はある。しかし、本件賃貸借契約では、賃料と共益費が明確に区別されている。
したがって、本件共益費は、借地借家法32条1項に基づく減額請求の対象とはならない。
7 争点3-2-2(本件共益費の減額請求の可否及び相当額)について
(原告の主張)
平成24年12月22日(本件減額請求がされた日)当時、本件共益費の相当額は月額511万2856円(533万8657円を下回る額)であったから、本件共益費(現行共益費)の額(月額722万1867円)は不相当に高額であった。
(1) 直近合意時点
現行共益費(月額722万1867円)の直近合意時点は、以下のとおりである。
〈1〉 現行共益費1(月額664万5800円)
平成7年10月1日(本件原始契約1及び2に基づく賃貸期間の始期)
〈2〉 現行共益費2(月額28万5521円)
平成17年9月1日(本件変更契約2に基づく変更の始期)
〈3〉 現行共益費3(月額29万0546円)
平成23年9月30日(本件変更契約3に基づく変更の始期)
(2) 現行共益費の不当性
原告又は十字屋は、本件共益費覚書の作成(平成8年2月1日)から平成24年に至るまでの間、被告から、本件共益費の内訳について説明を受けたことはなかった。この点、本件共益費の実額は被告のみが知るところであって、原告においてこれを明らかにすることはできなかった。
しかるところ、被告は、原告に対し、平成24年6月28日、本件共益費の適正化を図りたいとの意向を明らかにするとともに、同年9月7日及び同年11月22日、本件共益費の費用項目及び金額を明らかにした。しかるに、それによれば、被告が、十字屋(これを承継した原告)との間で合意した使途とは異なる使途に本件共益費を使用するとともに、必要となる本件共益費の額(後記(3)のとおり)が、現行共益費の額よりも相当程度低額であることが判明した。
以上のとおり、本件共益費の具体的な費用項目及び金額は、17年以上も明らかにされていなかったところ、その額が不相当に高額となっていたことは、それ自体、借地借家法32条1項に基づく減額請求の根拠となる事情の変更に当たるというべきである。
(3) 本件共益費の相当額
平成24年12月22日当時の適正な本件共益費の額は、別表5「相当共益費(主位的請求)」の「月額」欄のとおり、月額511万2856円である。
なお、本件共益費の額を算定する基礎となる実費の範囲は、後記8(原告の主張)のとおりである。
(4) 小括
以上のとおり、平成24年12月22日当時、本件共益費の相当額は月額511万2856円であったから、現行共益費の額(月額722万1867円)は不相当に高額であった。
(被告の主張)
争う。
現行共益費の額(月額722万1867円)は、本件共益費の相当額(平成24年11月1日以降月額843万2882円)よりも低廉である(後記10(被告の主張)参照)。
8 争点3-3-1(本件共益費の算定の基礎となる実費の範囲)について
(被告の主張)
本件共益費に含まれる実費の範囲(費目)は、別表6「項目」記載の各費目の全てである。
(1) 本件共益費の算定基準等
ア 平成8年度以降の本件共益費につき、原告又は十字屋と被告との間で、具体的な範囲及び算定基準を定めた書面は作成されていない。
したがって、本件共益費の範囲及び金額は、取引の一般的慣行及び通念、本件賃貸借契約の経緯、本件建物及びその設備等の内容、周辺又は同種建物の共益費の相場等に照らし、合理的に決定されるべきである。
イ 共益費は、建物の共用部分に関する費用を基本としつつ、当該契約ごとにその範囲が決定すべきであって、住居又は事務所の賃貸借契約に係る共益費と商業施設のそれとは、その範囲を異にすると解される。
ウ 本件原始契約1(平成7年8月29日付け)は、本件共益費につき、本件賃料とは別個に支払われるべきものとしたが、単に「共益費」ではなく「共益費等」と定めたことからすれば、本件賃貸借契約においては、一般的には共益費に含まれないものも本件共益費に含める趣旨であったというべきである。また、本件共益費は、その内実が実費であるとしても、第三者に対する立替金に限定される理由はない(後記エ参照)。
さらに、昭和56年に開業した本件建物においては、本件原始契約1が締結される以前から、テナントとの間で、共益費に所定の費目を含む運用をしてきたところ、十字屋及び原告は、その中核的なテナント(株式会社プランタンデパート関西)と同一性を有する事業体であって、その地位を引き継いでいる。そうであるとすれば、本件共益費の範囲を決定するに当たっては、上記運用も考慮されるべきである。
エ 日本ショッピング協会の統計調査によれば、平成24年度において、大都市の中心地域の共益費の平均は、月額9093円/坪、駅ビルについては月額8305円/坪である。
このように、現行共益費の額は、同種又は同地域の共益費の相場に比べて低廉である。
オ 原告は、本件各建物部分の転借人(エンドテナント)から、共益費として月額1475万5081円(3636円/m2)を受領しているところ、その金額は、現行共益費(月額1288円/m2)の2.8倍にも相当する。そして、原告は、上記共益費から、少なくとも月額133万7684円の差益を得ている。
しかるところ、上記共益費の収受の事実及び各費目の金額は、本件共益費の相当額を算定するに当たり、重要な間接事実として考慮すべきである。
(2) 個別の費目について
ア 減価償却費(別表6(1)〈1〉〈9〉、(5)〈3〉、(7)〈8〉)
上記(1)のとおり、本件賃貸借契約においては、共用部分の設備の減価償却費を本件共益費に含める旨の特約があった。また、本件建物に設置された機械の固定経費である減価償却費は、本件原始契約1にいう「固定関係経費」のうち「昇降機等機械関係経費」に当たる。
さらに、本件建物においては、阪神大震災からの復旧に当たり、平成6年度及び平成7年度に20億2400万円の投資を行ったところ、うち約10億円が空調、昇降機及び冷却棟等の付属設備に関するものである。この投資については、各テナントがその使用割合に応じて負担するのが合理的である。
また、本件建物においては、本件原始契約1が締結される以前から、テナントとの間で、共益費に減価償却費を含めてきた。加えて、原告は、本件各建物部分の転借人(エンドテナント)から、減価償却費を含む共益費を受領している。
したがって、減価償却費は、本件共益費に含まれる。
イ 備品類等保守費(別表6(6)〈5〉)
上記費用は、本件建物内のホテルフロントに設置された防犯カメラの録画機に係る費用であるところ、当該防犯カメラが本件建物全体の監視の用に供されていることに照らし、本件共益費に含まれる。
ウ 連絡地下通路維持管理費及び地域協賛費(別表6(7)〈4〉〈5〉)
連絡地下通路は、本件建物とJ・I駅及びJR・E駅とをつなぐもので、顧客の重要な来店通路であって、本件建物の廊下や階段等の共用部分と同じ機能を有している。その維持管理費は、R市、阪神電鉄、被告、神戸地下街株式会社及びS店の5者で分割して負担することとされている。
地域協賛費は、本件各建物部分のテナントの営業(売上)に直接又は間接に利益をもたらすものであって、公共料金と同様の公的な性格を有するものである。
また、本件建物においては、本件原始契約1が締結される以前から、上記各費用を共益費に含めてきた。
以上によれば、上記各費用は、本件建物の「共用部分に関する経費」に当たり、本件共益費に含まれるというべきである。
エ 駐車場に関する費用(別表6(7)〈6〉〈7〉)
駐車場委託費は、顧客による駐車場の無料利用(20分未満)につき、被告が業者に支払う委託料である。しかるところ、原告を含む顧客の関係者は、この無料利用により、利益を得ているということができる。
駐車場占有費用は、原告による駐車場(4枠)の占有の対価であるところ、当該駐車場は、搬入スペース及び倉庫と相まって、原告の事業運営にとって不可欠な物品の荷捌き場としての機能を有している。
したがって、上記各費用は、原告に利益をもたらすものとして、本件共益費に含まれるというべきである。
オ 消耗品類費(別表6(7)〈9〉)
上記費用は、不特定多数の者が使用する本件建物のトイレの物品に係る費用であるから、本件共益費に含まれる。
カ 管理費
被告は、本件賃貸借契約に関し、直接経費(別表6(1)~(7)の各費目)に加え、管理部門の人件費及び物的費用(被告の事務所に係る経費)等の間接経費を支出している。本件建物のような大規模な複合商業施設の管理には、相当の人的及び物的資源の投与が必要であるところ、これに要した間接経費は、一般的には、直接経費の10数%程度に相当する。
また、本件建物においては、本件原始契約1が締結される以前から、管理費を共益費に含めてきた。加えて、原告は、本件各建物部分の転借人(エンドテナント)から、管理費を含む共益費を受領している。
したがって、管理費は、本件共益費に含まれる。
(原告の主張)
本件共益費に含まれる実費の範囲(費目)は、別表6「項目」欄記載の各費目(別表5も同様)のうち、減価償却費((1)〈1〉〈9〉、(5)〈3〉、(7)〈8〉)、備品類等保守費((6)〈5〉)、連絡地下通路維持管理費((7)〈4〉)、地域協賛費((7)〈5〉)、駐車場に関する費用((7)〈6〉〈7〉)、消耗品類費((7)〈9〉)及び管理費を除いたものである。
(1) 本件共益費の算定基準等
ア 本件原始契約1は、本件共益費を構成する実費項目として、〈1〉冷暖房換気に関する経費、〈2〉電灯、電力に関する経費、〈3〉給排水に関する経費、〈4〉清掃衛生に関する経費、〈5〉昇降機等機械関係経費、〈6〉保安に関する経費、〈7〉その他共用部分に関する経費を挙げている。
したがって、本件共益費の額は、上記実費の各項目に該当するものを積算することにより、算出すべきである。
イ 被告は、本件共益費の額を算定するに当たっては、共益費の相場を確認する必要がある旨を主張する。
しかし、各建物は物理的な仕様、築年数、床面積等が全て異なる上、清掃、保守点検、警備等の業務は建物ごとに仕様が異なる。
したがって、そもそも、共益費の額に相場が存在するとは認め難く、仮にこれが存在するとしても、本件共益費の算定に当たり、これを確認する必要はない。
ウ 被告は、原告が本件各建物部分の転借人から受領した共益費により収益を得ているとして、本件共益費の額を算定するに当たっては、上記共益費の額と比較する必要がある旨を主張する。
しかし、原告は、本件各建物部分の転借人から、実費としての共益費を受領するにとどまり、これにより利益を得ていない。
また、原告と被告との間の本件賃貸借契約と、原告と転借人との間の転貸借契約とは、その内容を異にする別個の契約である。しかも、本件共益費は、本件建物の共用部分の管理に要する費用であるのに対し、原告が転借人から受領する共益費は、これに加えて賃借部分内部の管理に要する費用も含んでおり、両者はその対象を異にしている。したがって、本件共益費の額を算定するに当たり、両者の額を比較する意味はない。
(2) 個別の費目について
ア 減価償却費(別表5及び6の(1)〈1〉〈9〉、(5)〈3〉、(7)〈8〉)
共益費は、共用部分の維持管理のために必要な、賃借人が負担すべき実費である。これに対し、減価償却費は、設備の取得費用を複数の会計年度で平準化するための会計上の数額であって、実費ではない。
また、賃料(実質賃料)は、種類のいかんを問わず、賃貸人に支払われる経済的な対価をいい、純賃料及び当該賃貸借を継続するために必要な諸経費等から成り立つものであるところ、建物の躯体又は設備の減価償却費は、既に当該建物の賃料に含まれている。
さらに、原告と被告は、本件建物の各種設備の減価償却費を本件共益費の額に含める旨を合意していない。なお、本件原始契約1が締結される前の本件建物の共益費には、減価償却費が含まれていなかったことがうかがわれる。
したがって、上記減価償却費は、本件共益費には含まれない。なお、減価償却費が本件共益費に含まれるとしても、耐用年数が既に経過した設備については、減価償却費を計上する余地はない。
イ 備品類等保守費(別表5及び6の(6)〈5〉)
備品類等保守費は、本件建物内のホテルフロントに設置された防犯カメラの費用であるから、本件建物の「共用部分に関する経費」に当たるとはいえず、本件共益費に含まれない。
ウ 連絡地下通路維持管理費及び地域協賛費(別表5及び6の(7)〈4〉〈5〉)
連絡地下通路維持管理費及び地域協賛費は、本件建物の共用部分でない部分のために発生する費用であり、本件建物の維持管理のために必要な経費でもないから、本件建物の「共用部分に関する経費」に当たらず、本件共益費に含まれない。
エ 駐車場に関する費用(別表5及び6の(7)〈6〉〈7〉)
本件建物の駐車場は共用部分ではないから、駐車場に関する費用(駐車場占有費用、駐車場委託費)は、本件建物の「共用部分に関する経費」には当たらない。なお、本件原始契約1が締結される前の本件建物の共益費には、駐車場に関する費用が含まれていなかったことがうかがわれる。
確かに、上記駐車場は荷捌き機能を有するが、商業施設においては、テナントの搬出入口は、賃借部分以外の設備として、当該建物の所有者が賃借人に提供するものである。すなわち、荷捌き場は、停車スペースを含め、商業施設の賃貸借契約の前提条件であって、その使用料は賃料に含まれている。
したがって、上記各費用は、本件共益費には含まれない。なお、駐車場占有費用が本件共益費の費目に含まれるとした場合には、駐車場委託費及び駐車場システムの減価償却費を本件共益費から支出することは、二重計上として許されない。
| 判例ID | 28261099 |
|---|---|
| 裁判年月日等 | 平成30年2月21日/神戸地方裁判所/第2民事部/判決/平成25年(ワ)604号/平成25年(ワ)1006号 |
| 判示事項 | 【事案概要】 被告を賃貸人とし、原告を賃借人とする建物の賃貸借契約及びこれに付随する塔屋の使用契約に関し、原告が借地借家法に基づく賃料減額請求により減額されたはずの賃料及び共益費の確認等の請求を行い、被告が、借地借家法に基づく賃料増額請求により増額されたはずの賃料及び共益費の確認等を求める反訴を提起した件に関し、原告の請求が一部認容された事例。 |
| 事件名 | 賃料減額確認等請求事件(604号)、賃料増額確認請求等反訴事件(1006号) |
| 出典 | D1-Law.com判例体系 |
| 裁判結果 | 一部認容、一部棄却(604号)、一部却下、一部棄却(1006号) |
| 裁判官 | 山口浩司 和久一彦 日巻功一朗 |
平成30年01月18日/東京高等裁判所/第10民事部/判決/平成29年(ネ)3468号...等
【事案概要】
区分建物について締結された賃貸借契約の賃貸人である原告が、賃借人である被告に対し、賃料及び敷金が不相当になっていると主張して、本件賃貸借契約及び借地借家法32条1項に基づき、賃料の増額の確認及び敷金の不足分の預託義務の存在の確認を求めた件に関し、原告の請求を一部認容した原判決が維持されたうえで、原告の賃料の支払等を追加して求める附帯控訴の一部が認容された事例。
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴に基づく当審における追加請求について
控訴人は、被控訴人に対し、本判決が確定したときは、2881万5028円及び別紙差額賃料利息計算表の番号1ないし37に記載の各金額に対する同表の同番号に記載の各起算日から各支払済みまで年1割の割合による各金員を支払え。
3 被控訴人の原判決主文第3項(訴訟費用の負担)に関する附帯控訴を却下する。
4 当審における訴訟費用は、すべて控訴人の負担とする。 事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴の趣旨
(1) 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 前項の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却する。
(3) 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
2 附帯控訴の趣旨
(1) 原判決主文第3項中、附帯控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 主文第2項と同旨(被控訴人は、当審において、差額賃料等の支払請求を追加した。)。
第2 事案の概要等(以下、略称は原判決のそれによる。)
1 事案の概要
(1) 当事者
ア 被控訴人は、不動産に関するコンサルティング並びに不動産の企画、開発、売買、賃貸、仲介、保有及び管理に関する事業等を目的とする株式会社である。
イ 控訴人は、労務コンサルティング業務等を目的とする株式会社である。
(2) 賃貸借契約
ア C株式会社(C)と控訴人は、平成23年9月16日、原判決別紙物件目録記載の「(一棟の建物の表示)」に係る建物(以下「本件ビル」という。)に属する同目録記載の「(専有部分の建物の表示)」に係る区分建物(以下「本件物件」という。)について、賃料を月額242万8455円(消費税を含まない。)、共益費を月額84万8496円、敷金を2914万1460円、賃貸面積を585.17平方メートル(177.01坪)並びに賃貸期間を平成23年12月15日から平成25年12月14日までと定めて、賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し、その後、Cは、控訴人に対し、本件賃貸借契約に基づき、本件物件を引き渡した。
イ Cは、平成24年4月1日、D株式会社と合併し、その商号はE株式会社となった。E株式会社は、被控訴人に対し、平成26年3月10日、本件物件を売り渡し、併せて本件賃貸借契約の賃貸人の地位を譲渡した。
(3) 賃料増額の意思表示
ア 被控訴人は、控訴人に対し、平成26年7月吉日付け書面をもって、本件賃貸借契約の定める同年9月1日からの賃料を月額304万5812円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)に増額し、敷金を3654万9744円に増額する旨の意思表示をし、同年7月25日、控訴人が同書面を受領した。
イ 被控訴人は、控訴人に対し、平成27年1月21日付け書面をもって、同年4月1日から本件賃貸借契約の定める賃料を月額322万2734円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)に増額し、敷金を3867万2808円に増額する旨の意思表示をし、同年1月21日過ぎ頃、控訴人が同書面を受領した。
(4) 本件請求の内容、原審の判断並びに本件控訴及び本件附帯控訴
本件は、本件賃貸借契約の賃貸人である被控訴人が、賃借人である控訴人に対し、平成26年9月1日以降、本件賃貸借契約に定める賃料が不相当となり、これに伴って敷金も不相当となっていると主張して、本件賃貸借契約の定め及び借地借家法32条1項に基づき、平成26年9月1日から平成27年3月31日までの本件物件に係る賃料が月額304万5812円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)及び同年4月1日以降の賃料が月額322万2734円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)であることの確認並びに控訴人に本件賃貸借契約に定める敷金の不足分として953万1348円の預託義務があることの確認を求めた事案である。
原審裁判所は、被控訴人の各請求のうち、本件建物の賃料が、平成26年9月1日から平成27年3月31日までは月額287万2904円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)及び同年4月1日以降は月額321万4104円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)であることをそれぞれ確認し、その余の請求をいずれも棄却した。
そこで、これを不服とする控訴人が本件控訴をし、また、被控訴人も、附帯控訴をし、訴訟費用について、その2分の1を負担させた原判決の取消しを求めるとともに、借地借家法32条2項ただし書に基づき、本判決が確定したときは、控訴人は、被控訴人に対し、原判決が認定した増額された賃料額と現実に控訴人が支払った賃料額との差額賃料額(ただし、消費税を含む。)の合計額2881万5028円及び別紙差額賃料利息計算表の番号1ないし37に記載の各金額に対する同表の同番号に記載の各起算日から各支払済みまで年1割の割合による各利息の支払を求める請求を追加した。
2 前提事実並びに争点及び当該争点に関する当事者の主張
前提事実並びに争点及び当該争点に関する当事者の主張は、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」第2の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。
(原判決の訂正)
(1) 原判決2頁20行目末尾の次で改行し、以下のとおり加える。
「(1) 当事者
ア 被控訴人は、不動産に関するコンサルティング並びに不動産の企画、開発、売買、賃貸、仲介、保有及び管理に関する事業等を目的とする株式会社である。
イ 控訴人は、労務コンサルティング業務等を目的とする株式会社である。」
(2) 原判決2頁21行目の「(1)」を「(2)」と改め、22行目の「月額242万8455円」の次に「(消費税を含まない。)」を加え、3頁1行目の「(甲1)」を「(甲1、弁論の全趣旨)」と、3頁9行目の「(2)」を「(3)」と、13行目の「(3)」を「(4)」と、それぞれ改める。
(3) 原判決3頁21行目の「意思表示をした(甲5)。」を「意思表示をし、同年7月25日、控訴人が同書面を受領した(甲5、6)。」と改める。
(4) 原判決4頁3行目の「(4)」を「(5)」と改める。
(5) 原判決4頁22行目の「意思表示をした(甲7)。」を「意思表示をし、同年1月21日過ぎ頃、控訴人が同書面を受領した(甲7、弁論の全趣旨)。」と改める。
(6) 原判決4頁23行目の「(5)」を「(6)」と改める。
(当審における控訴人の主張)
(1) 本件賃貸借契約の期間中に賃料の増額を認める理由がないこと
本件賃貸借契約第11条は、賃料改定について規定しているところ、1項と2項の関係については、原則として本件賃貸借契約の更新時に賃料が改定されるものであり、賃貸期間中の賃料改定は、更新を待つこともできないほどに大幅な変更があった場合に、あくまでも例外的に認められるものである。本件においては、被控訴人や前所有者の公租公課の負担が著しく増加している事実はなく、物価が上昇している事実もなく、経済的事情の変動が生じているものでもなく、更に、近傍建物の賃料相場も変動していないなど、同条2項に該当する事項について、例外ともいえる大幅な変更は一切認められない。
(2) F鑑定書の内容の不合理性について
ア 差額配分法による賃料算定の問題点
F鑑定書は、積算法による積算賃料額を504万7600円(同鑑定書20頁)、賃貸事例比較法(新規賃料)による比準賃料額を433万0300円と算定した上、それぞれ50パーセントの割合で合算した結果、正常実質賃料を468万9000円と算定する(同鑑定書23頁)。
しかし、積算法については、賃貸人の期待利回りを重視して算定する手法であり、必ずしも現実を反映しない。これに対し、賃貸事例比較法(新規賃料)については、まさに本件物件の周辺の新規の賃貸借契約における相場を反映したものである。したがって、正常実質賃料の算定に当たっては、積算法よりも新規の賃貸事例比較法(比準賃料)の割合を多くして算定するのが相当である。すなわち、控訴人が提出した乙第5号証の有限会社G作成の「不動産鑑定評価書」(以下「控訴人鑑定」という。)に記載されたとおり、積算賃料を10パーセント、比準賃料を90パーセントの割合で、正常実施賃料を算定するのが相当である。
イ 各手法に基づく賃料額の算入割合の問題点
F鑑定書は、差額配分法、利回り法、スライド法の各手法によって算定された賃料について、それぞれ60パーセント、20パーセント、20パーセントの割合で算入し、鑑定評価額を決定しているところ(同鑑定書27頁)、差額配分法の割合を高くしている理由は不明である。それぞれの、手法のうちどれが秀でていると判断することができないことにかんがみれば、それぞれ同程度の割合で算入するのが相当であるところ、控訴人鑑定によれば、差額配分法、利回り法、スライド法の各手法によって算定された賃料について、それぞれ40パーセント、30パーセント、30パーセントの割合で算入しており、この割合が妥当といえる。
ウ 修繕積立金の増額分負担者の問題点
F鑑定書は、修繕積立金の増額分について、その全額を賃借人の負担とすることを前提に、平成26年9月1日時点の賃料の鑑定評価額に上乗せして平成27年4月1日及び平成28年8月1日時点の各鑑定評価額を算定している(同鑑定書28頁、29頁)。
しかし、そもそも修繕積立金とは、建物の将来の大規模修繕に備えて、計画的に積み立てる趣旨の費用であり、これによって建物の所有権や価値を維持するためのものであるところから、専ら賃貸人(区分所有者)のための費用である。このような修繕積立金の増額という賃貸人(区分所有者)の事情に関して、その全てを賃借人に負担させる理由は一切なく、そのような算定方法自体に問題がある。
エ 以上のことから、F鑑定書における鑑定評価額については、様々な問題があることから、そのまま採用することはできず、むしろ、控訴人鑑定によって算定されるべきである。
(当審における被控訴人の主張)
(1) 訴訟費用の負担について
原判決は、控訴人に対し、訴訟費用の半額しか負担させなかったことは、本件事案の性質からみて、妥当ではない。
(2) 借地借家法32条2項ただし書に基づく請求(当審での追加請求)
ア 本件賃貸借契約の従前の月額賃料は、消費税を除いて242万8455円であったところ、原判決は、平成26年9月1日から平成27年3月31日までは、月額287万2904円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)が相当であり、平成27年4月1日からは月額321万4104円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)が相当であるとした。
イ 前記アによれば、平成26年9月1日から平成27年3月31日までの従前賃料月額242万8455円と原判決が認定した増額後の賃料月額287万2904円との差額は44万4449円であり、これに消費税を加算すると、月額地代の差額は48万0004円(44万4449円×1.08=48万0004円)となり、上記期間である7か月の期間の差額は、48万0004円×7か月=336万0028円となる。
ウ また、前記アによれば、平成27年4月1日から平成29年9月30日までの従前賃料月額242万8455円と原判決が認定した増額後の賃料月額増321万4104円との差額は、78万5649円であり、これに消費税を加算すると、月額地代の差額は84万8500円(78万5649円×1.08=84万8500円)となり、上記期間30か月の期間の差額は、84万8500円×30か月=2545万5000円となる。
エ よって、控訴人は、被控訴人に対し、借地借家法32条2項ただし書に基づき、本件判決が確定したときは、上記イの336万0028円とウの2545万5000円の合計2881万5028円及び別紙差額賃料利息計算表の番号1ないし37に記載の各金額に対する同表の同番号に記載の各起算日から各支払済みまで年1割の割合による各利息の支払義務がある。 第3 当裁判所の判断
1 被控訴人の増額請求された賃料額の各確認請求について
当裁判所も、被控訴人の増額請求された賃料額の各確認請求は、本件物件の賃料が、平成26年9月1日から平成27年3月31日までは月額287万2904円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)及び同年4月1日以降は月額321万4104円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)であることを確認する限度で理由があり、その余の請求はいずれも棄却すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」第3に記載のとおりであるから、これを引用する。
(原判決の付加訂正)
(1) 原判決8頁20行目の「一長一短があることから」を「一長一短があるが、いずれも対象不動産の正常実質賃料の一面を反映した賃料として尊重し、」と改める。
(2) 原判決10頁19行目の「賃料は、」を「増額後の賃料は、」と、20行目の「賃料は」を「増額後の賃料は、」と、それぞれ改める。
(3) 原判決12頁10行目の「差額配分法が、」の次に「価額時点における正常実質賃料と実際実質賃料との間に発生している差額を契約締結の経緯等を考慮して調整を行う賃料であり、」を加え、また、12行目の「妥当性を有し、」の次に「正常実質賃料の査定では、」を加え、17行目から18行目にかけての「当該手法が」を「当該判断が」と改める。
(4) 原判決12頁26行目の「前提とし、」を「前提とし(弁論の全趣旨)、」と改める。
(5) 原判決13頁3行目から4行目にかけての「平成28年6月17日付け有限会社G作成の「不動産鑑定評価書」(以下「G鑑定書」という。)」を「控訴人鑑定」と改める。
(当審における控訴人の主張に対する判断)
(1) 本件賃貸借契約の期間中に賃料の増額を認める理由がないことについて
控訴人は、本件賃貸借契約第11条は、賃料改定について規定しているところ、1項と2項の関係については、原則として本件賃貸借契約の更新時に賃料が改定されるものであり、賃貸期間中の賃料改定は、更新を待つこともできないほどに大幅な変更があった場合に、あくまでも例外的に認められるものであるが、本件においては、被控訴人や前所有者の公租公課の負担が著しく増加している事実はなく、物価が上昇している事実もなく、経済的事情の変動が生じているものでもなく、更に、近傍建物の賃料相場も変動していないなど、同条2項に該当する事項について、例外ともいえる大幅な変更が一切認められない旨主張する。
しかし、前記第2の2で引用した原判決の「事実及び理由」第2の2の前提事実(ただし、訂正後のもの。以下「前提事実」という。)(1)によれば、本件賃貸借契約第11条2項は、「前項にかかわらず、土地建物に対する公租公課の負担の増加、その他経済事情の変動、又は近傍建物の賃料に比較して第7条に定める賃料が不相当となったときは、賃貸人・賃借人協議のうえ賃料の改定を行うことができる。」と定めているところ、先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の4で説示したとおり(原判決13頁)、証拠(甲3、乙5、鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によると、平成22年から平成26年にかけて本件物件の付近に所在する標準地の地価公示価格及び地価調査価額は、いずれも上昇傾向を示しており、東京都(以下略)の主な超高層ビルにおける賃貸市場の動向も、空室率が低下し、募集賃料は増加傾向にあったものと認めることができるのであって、上記の本件賃貸借契約第11条2項の「経済事情の変動」によって「第7条に定める賃料が不相当となったとき」に該当すると解することができ、被控訴人が控訴人に対し、本件賃貸借契約に定める賃料の増額を求めることが、本件賃貸借契約第11条2項の定めに反するものということはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) F鑑定書における差額配分法による賃料算定の問題点について
控訴人は、F鑑定書における差額配分法による賃料算定の問題点として、F鑑定書は、積算法による積算賃料額を504万7600円(同鑑定書20頁)、賃貸事例比較法(新規賃料)による比準賃料額を433万0300円と算定した上、それぞれ50パーセントの割合で合算した結果、正常実質賃料を468万9000円と算定する(同鑑定書23頁)が、積算法については、賃貸人の期待利回りを重視して算定する手法であり、必ずしも現実を反映しないのに対し、賃貸事例比較法(新規賃料)については、まさに本件物件の周辺の新規の賃貸借契約における相場を反映したものであるから、正常実質賃料の算定に当たっては、積算法よりも新規の賃貸事例比較法(比準賃料)の割合を多くして算定するのが相当であって、控訴人鑑定に記載されたとおり、積算賃料を10パーセント、比準賃料を90パーセントの割合で、正常実施賃料を算定するのが相当である旨主張する。
しかし、先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の1(1)イで認定したとおり、F鑑定書は、差額配分法により正常実質賃料を求めるに当たり、積算法においては、その期待利回りを一般財団法人Hの不動産投資家調査(平成26年10月調査)に示された4.7パーセントをもとに、立地条件や競争力等を考慮して5.0パーセントとし、必要諸経費等を踏まえて積算賃料を月額504万7600円(ただし、共益費を含み、消費税を含まない金額。)と算定し、また、賃貸事例比較法においては、本件建物の近隣のビルに係る各新規賃料をもとに、差異に応じた修正を行って、比準賃料を月額433万0300円(ただし、共益費を含み、消費税を含まない金額。)と算定し、積算賃料及び比準賃料に一長一短があるが、いずれも対象不動産の正常実質賃料の一面を反映した賃料として尊重し、その中庸値である月額468万9000円(ただし、共益費を含み、消費税を含まない金額。)を正常実質賃料と算定したものであって、このような適宜の割合で参照する手法が不合理であるということはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(3) F鑑定書における各手法に基づく賃料額の算入割合の問題点について
控訴人は、F鑑定書における各手法に基づく賃料額の算入割合の問題点について、F鑑定書は、差額配分法、利回り法、スライド法の各手法によって算定された賃料について、それぞれ60パーセント、20パーセント、20パーセントの割合で算入し、鑑定評価額を決定しているところ(同鑑定書27頁)、差額配分法の割合を高くしている理由は不明であり、それぞれの、手法のうちどれが秀でていると判断することができないことにかんがみれば、それぞれ同程度の割合で算入するのが相当であり、控訴人鑑定によれば、差額配分法、利回り法、スライド法の各手法によって算定された賃料について、それぞれ40パーセント、30パーセント、30パーセントの割合で算入しており、この割合が妥当といえる旨主張する。
しかし、先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の1(1)カで認定したとおり、F鑑定書は、各手法に基づく賃料額の算入割合について、差額配分法によるものは、その正常実質賃料の査定において、積算法及び賃貸事例比較法を適用しており、その差額部分についても衡平に配分されているとして、一定の規範性を有することから、これを重視しつつ、利回り法及びスライド法についての各試算賃料を比較考量し、その割合を差額配分法60パーセント、利回り法20パーセント、スライド法20パーセントとしているものであって、先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の4で説示したとおり、F鑑定人は、差額配分法が、価額時点における正常実質賃料と実際実質賃料との間に発生している差額を契約締結の経緯等を考慮して調整を行う賃料であり、賃貸借当事者が賃料改定を通じて相互に賃料差額の縮小に努める傾向があるという観点から妥当性を有し、正常実質賃料の査定では、積算法及び賃貸事例比較法の二手法を適用しているために規範性の高いものであり、他方で、スライド法は、経済情勢の変化を反映するものとして客観性があるものの、経済指標等が実態を示しているか不明な部分があり、賃貸借契約当事者間の個別性も反映されないものであること、及び利回り法も、元本価値が賃料変動に直接反映することが妥当かどうか疑問もあることを総合考慮して、上記のような算入割合の判断に至ったものと認めることができるのであって、当該判断が不合理であったということはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(4) F鑑定書における修繕積立金の増額分負担者の問題点について
控訴人は、F鑑定書における修繕積立金の増額分負担者の問題点について、F鑑定書は、修繕積立金の増額分について、その全額を賃借人の負担とすることを前提に、平成26年9月1日時点の賃料の鑑定評価額に上乗せして平成27年4月1日及び平成28年8月1日時点の各鑑定評価額を算定している(同鑑定書28頁、29頁)が、そもそも修繕積立金とは、建物の将来の大規模修繕に備えて、計画的に積み立てる趣旨の費用であり、これによって建物の所有権や価値を維持するためのものであることから、専ら賃貸人(区分所有者)のための費用であり、このような修繕積立金の増額という賃貸人(区分所有者)の事情に関して、その全てを賃借人に負担させる理由は一切なく、そのような算定方法自体に問題がある旨主張する。
しかし、先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の1(2)で認定したとおり、F鑑定人は、平成27年4月1日当時の適正賃料については、時点間の間隔が短いため、平成26年9月1日時点の鑑定評価額を基準としてスライド法を適用し、修繕積立金の増額分を加算して算定することとし、名目国内総生産、消費者物価指数、企業物価指数及びオフィス賃料指数の変動率について、各指数の間に特段の優劣が認められないことから、それらの平均値である101.6%を変動率と査定し、修繕積立金増加分を加算して、その月額支払賃料を406万2600円(ただし、共益費を含み、消費税を含まない金額。)と算出したことが認められ、原判決の「事実及び理由」第3の4で説示したとおり、F鑑定人は、平成26年9月1日時点の賃料の算定に当たっては実額相当額である154万4800円を前提として評価しているものと認めることができ、平成27年4月1日時点においても、本件ビルに係る管理組合が平成26年11月11日に開催された臨時総会において、平成27年4月1日以降、修繕積立金を従前の月額12万8737円(年額154万4844円)から月額40万9619円(年額491万5428円)に増額する旨の決議を行ったことを前提とし(弁論の全趣旨)、その必要諸経費の加算として把握したものということができるから、その評価の手法が妥当性を欠くということはできない(本件物件の所有者で、賃貸人である被控訴人が、修繕積立金の増額分を経費として、賃借人である控訴人にその負担を転嫁することが直ちに不合理であるということはできない。)。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
2 被控訴人の附帯控訴に基づく当審における追加請求について
(1) 前提事実(2)及び(3)によれば、本件賃貸借契約における平成26年9月当時の賃料は、月額242万8455円(消費税を含まない。)のところ、先に引用した原判決の「事実及び理由」第3の2で説示したとおり、本件物件に係る平成26年9月1日から平成27年3月31日までの増額後の賃料は、月額287万2904円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)が相当であり、平成27年4月1日からの増額後の賃料は、月額321万4104円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)が相当である。
(2) 前記(1)によれば、平成26年9月1日から平成27年3月31日までの従前賃料月額242万8455円と増額後の賃料月額287万2904円との差額は44万4449円であり、これに消費税を加算すると、月額地代の差額は48万0004円(≒44万4449円×1.08)となり、上記期間である7か月の期間の差額は、336万0028円(=48万0004円×7か月)となる。
(3) また、前記(1)によれば、平成27年4月1日から平成29年9月30日までの従前賃料月額242万8455円と増額後の賃料月額321万4104円との差額は、78万5649円であり、これに消費税を加算すると、月額地代の差額は84万8500円(≒78万5649円×1.08)となり、上記期間30か月の期間の差額は、2545万5000円(=84万8500円×30か月)となる。
(4) そうすると、控訴人は、被控訴人に対し、借地借家法32条2項ただし書に基づき、本件判決が確定したときは、上記(2)の336万0028円と(3)の2545万5000円の差額賃料合計2881万5028円及び別紙差額賃料利息計算表の番号1ないし37に記載の各金額に対する同表の同番号に記載の各起算日から各支払済みまで年1割の割合による各利息の支払義務があるというべきである。
3 結論
以上によれば、被控訴人の控訴人に対する増額請求された賃料額の各確認請求は、本件物件の賃料が、平成26年9月1日から平成27年3月31日までは月額287万2904円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)及び同年4月1日以降は月額321万4104円(ただし、共益費を除き、消費税を含まない金額。)であることを確認する限度で理由があり、その余の請求は理由がないからこれを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、被控訴人が当審において附帯控訴に基づいて追加した、増額された賃料額と現実に控訴人が支払った賃料額との差額賃料額(ただし、消費税を含む。)の合計額2881万5028円及び別紙差額賃料利息計算表の番号1ないし37に記載の各金額に対する同表の同番号に記載の各起算日から各支払済みまで年1割の割合による各利息の支払請求は、理由があるからこれを認容することとする。
なお、被控訴人は、附帯控訴に基づき、訴訟費用について、その2分の1を負担させた原判決主文第3項の被控訴人の敗訴部分の取消しを求めているところ、民事訴訟法282条によれば、訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができず、控訴人の本件控訴に理由がない本件においては、訴訟費用の負担についての原判決主文第3項に関する附帯控訴は不適法であるから(最高裁昭和53年12月21日第一小法廷判決・民集32巻9号1749頁参照)、これを却下する(なお、この点を措くとしても、原判決が、原審における訴訟費用の2分の1を被控訴人に負担させたことは、本件事案に照らして、特に不合理であるということはできない。)。また、当審における訴訟費用は、上記のとおり訴訟費用の負担に関する原判決に対する被控訴人の附帯控訴が不適法であるとしても、控訴人の本件控訴は理由がなく、被控訴人の附帯控訴に基づいて追加された差額賃料等の請求は理由があるから、民事訴訟法64条ただし書により、これをすべて控訴人に負担させるのが相当である。
よって、主文のとおり判決する。 第10民事部 (裁判長裁判官 大段亨 裁判官 小林元二 裁判官 浦木厚利) (別紙)
差額賃料利息計算表
平成30年01月16日/東京地方裁判所/民事第7部/判決/平成28年(ワ)37783号
【事案概要】
株式会社である原告が、株式会社である被告との間で締結した建物賃貸借契約に係る賃料が不相当に低額になった旨主張して、被告に対し、借地借家法32条1項の賃料増額請求に基づき同建物の賃料が増額となったことの確認を求めるとともに、同上2項ただし書きに基づき、増額となった賃料に係る不足額の支払いを求めた件につき、原告の請求がいずれも棄却された事例。
準備中
平成29年10月13日/東京地方裁判所/民事第37部/判決/平成28年(ワ)14389号
【事案の概要】
本件は、原告が、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)にある各室の賃借人である株式会社ジョイント・プロパティ(以下「ジョイント・プロパティ」という。)との間で貸室27室(以下、併せて「本件各貸室」という。)を対象とする各賃貸借契約(以下「本件各賃貸借契約」という。)を締結した被告株式会社リブ・マックス(以下「被告リブ・マックス」という。)及び被告リブ・マックスの新設分割に伴い設立さ...
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由
第1 請求
1 原告が被告らに対し賃貸中の別紙物件目録記載の建物に所在する別紙貸室目録の各貸室に係る各月額賃料は、同貸室目録記載の各改定(増額)日から同貸室目録記載の各改定賃料記載の各金額であることを確認する。
2 被告らは、連帯して、原告に対し、841万9606円及びうち797万6463円に対する平成29年3月1日から支払済みまで年10%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)にある各室の賃借人である株式会社ジョイント・プロパティ(以下「ジョイント・プロパティ」という。)との間で貸室27室(以下、併せて「本件各貸室」という。)を対象とする各賃貸借契約(以下「本件各賃貸借契約」という。)を締結した被告株式会社リブ・マックス(以下「被告リブ・マックス」という。)及び被告リブ・マックスの新設分割に伴い設立された被告株式会社リブマックスプロパティマネジメント(以下「被告リブマックスPM」という。)に対し、原告がジョイント・プロパティから本件各賃貸借契約の賃貸人の地位を承継したこと及び借地借家法32条1項に基づき賃料増額請求をした旨を主張して、被告らに対し、賃料額の確認を求め、また、借地借家法32条2項に基づき、平成29年2月28日現在の差額賃料合計797万6463円及びこれに対する同日までの確定利息44万3143円並びに同差額賃料に対する平成29年3月1日から支払済みまで年10%の割合による利息の各支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により明白に認められる事実である。)
(1) 原告は、別紙物件目録記載の建物(本件建物)を所有していたところ、本件建物に所在する各貸室について、ジョイント・プロパティに対して賃貸した。
(2) ジョイント・プロパティは、被告リブ・マックスとの間において、別紙貸室目録中の各貸室27室(本件各貸室。なお、本件各貸室のうち、個々の貸室を別紙貸室目録の番号に従い「本件貸室1」「本件貸室2」などという。)について、賃貸借期間開始日を同目録記載「賃貸借期間・開始日」とし、月額賃料(以下、月額賃料を単に「賃料」ということがある。)を同目録記載「現行賃料」の金額として、賃貸借(転貸借)契約(本件各賃貸借契約)を締結した(ただし、本件貸室9及び11の当初賃借人は、被告リブ・マックスの関連会社であるグッド・コミュニケーション株式会社であり、平成26年3月、同社の地位を被告リブ・マックスが承継した。)。
(3) 被告らは、本件各貸室において、サブリース事業、マンスリー(ウィークリー)マンション事業等を実施している。
(4) 原告は、平成26年12月19日、本件建物について、三菱UFJ信託銀行株式会社に対し、信託を原因として所有権を移転し、これに伴い、ジョイント・プロパティから本件各賃貸借契約の賃貸人の地位を承継し、被告リブマックスPMは、当該承継を承諾した。
(5) 原告は、本件各賃貸借契約の各更新に先立ち、被告リブ・マックスに対し、以下の日時に、いずれも更新日である別紙貸室目録記載の各改定日を始期として、同目録記載の改定賃料への増額を請求した。
ア 本件貸室1ないし9については、平成27年9月18日
イ 本件貸室10ないし16については、平成28年1月27日
ウ 本件貸室17ないし24については、平成28年3月9日
エ 本件貸室25ないし27については、平成29年1月11日
(6) 被告リブマックスPMは、原告からの前記(5)アの増額請求に対し、平成27年9月29日付け回答書(甲6)を原告に送付して、平成23年3月に本件建物の共用部において自殺案件(共用部からの転落による死亡事故。以下「本件死亡事故」という。)があり、重要事項告知義務があるものとして近傍類似の賃料と比較して格安の賃料にて借り上げた経緯があるとして、原告の増額請求には応じられない旨回答した。(甲6)。
2 争点
(1) 被告リブ・マックスの被告適格の有無(本案前の主張)
(被告らの主張)
被告リブ・マックスは、平成26年7月1日に、同社の新設分割に伴い設立した被告リブマックスPMに対し、ウィークリー事業不動産賃貸事業及びサブリース事業に係る権利義務を譲渡し、これにより、原告の有する本件各貸室についての権利義務も、同日をもって、被告リブマックスPMが承継した。
よって、原告の被告リブ・マックスに対する本件請求は、被告適格を欠き、不適法なものとしていずれも却下されるべきである。
(原告の主張)
会社分割の対象となる権利義務の存否及び帰属は民法等一般原則の定めに従うとも解されており、本件賃貸借契約においては、賃借人の変更は明示的に禁止され、又は、賃貸人の承諾なく賃借人を変更できる旨の定めはないから、民法等一般原則に従い、賃貸人の承諾なく、賃借人の変更は効力を生じない。
仮に、賃貸人の地位が会社分割により被告リブマックスPMに承継されたとしても、被告リブ・マックスは賃料債務を併存的に引き受け、かつこれを表示している。よって、被告リブ・マックスは、賃料支払債務を連帯して負う。
(2) 賃料増額請求が借地借家法32条1項の要件を充足するか否か
(原告の主張)
ア 直近合意時点
本件各貸室の現行賃料の直近合意時点は、当初賃貸借契約締結の日(ただし、本件貸室12は平成24年4月)である。
イ 現行賃料の不相当性
現行賃料は、後期(ア)ないし(オ)記載の直近合意時点から改定時期までの変動事由により、不相当になった。
また、本件各貸室の改定前賃料(別紙貸室目録記載の現行賃料)は、同貸室の新規適正賃料(同目録記載の改定賃料)に比べ、17室において30%も乖離しており、また、本件建物内にある本件各貸室以外の貸室の改定後賃料とも乖離している。本件各貸室の現行賃料は、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった。
(ア) 不動産価格の上昇
本件建物と同一需給圏内になる地価公示地点における最終合意時点と現在の価格変動に照らすと、各最終合意時点から現時点まで、本件建物の周辺地価においては、全体として10%前後の地価上昇がみられる。また、本件建物の近隣地区(C地区・本件建物の周囲3km四方圏内)におけるマンション売買(分譲)価格は、総じて20%~30%を超える上昇を示している。
(イ) 建設コストの変動
東京都における鉄筋コンクリート共同住宅の建築費指標に照らすと、建設コスト(工事原価)は15%前後の上昇率を示している。
(ウ) 周辺賃料の上昇
C・D地区における共同住宅賃料指数(シングルタイプ・18m2以上30m2未満。平成21年第1四半期を100)に照らすと、周辺賃料水準は10%近い上昇率を示し、改定時期以降も上昇傾向にある。
(エ) 本件死亡事故の影響の消失
本件死亡事故の影響を受けているのは、平成23年10月~12月までに契約した9室(本件貸室1ないし9)である。当該9室は、いずれも月額賃料を1室8万6000円として契約されているところ、本件死亡事故を理由として低額である賃料が定められた。一般的に事故物件であることを理由として募集賃料の減額割合は20%程度・2年間とされていることから、当該9室についてもいわゆる事故物件としての減額が20%以上見込まれたことは明らかである。よって、本件死亡事故から5年以上経過した現時点においては、その影響が消失していることは明白である。
(オ) 賃料を低額にする賃貸人の事情等の消失
本件各貸室は空室率が高い時期に締結される等当時の賃貸人の特殊な事情により締結されたものと想定することができるとしても、現時点における空室率は5%未満(甲28)と大幅に改善される等により、賃料を低額にする特殊な事情や動機は消失した。
ウ 相当賃料
被告らが実施するサブリース事業等は、サブリース事業等として応分のリスクを負担するものではなく、以下のとおり、極めて特殊なものであり、質的に管理業務と異なるところはない。被告らの適正な費用・収益は、PMフィー及び空室損失相当額に相当する月額賃料の84%を上回ることはない(甲10ないし13各16頁1-4.(4)必要経費欄参照)。したがって、本件では、1Kタイプで適正賃料が11万6000円ないし12万1000円とされていることから(甲10ないし13)、被告らの年間の適正費用・利益は、最大限その84%である9万7440円ないし10万1640円、月額にして8120円ないし8470円である。
(ア) 被告らの1か月又は2か月前の予告により何時でも解約が可能であり、相当の事業リスクは負担していないこと。
(イ) その態様においても、利用者とは1か月から数か月という短期間の賃貸借契約が締結されており、マンスリーマンションとして一般の賃貸借事業とは異なる態様で行われていること。
(ウ) 敷金・保証金・更新料等の負担はないこと。
(エ) 入居者には賃料保証会社の加入を義務づけ、定額の退去費用を負担させる等、賃料未回収その他のリスクを回避していること。
(オ) 本件建物一棟全部を対象としたサブリースではなく、本件建物の共用部分の保守管理は要せず、貸室に限った費用負担に限定され(その大部分は入居者負担である。)、さしたる費用も発生していないこと。
(被告らの主張)
ア 直近合意時点
本件各貸室の現行賃料の直近合意時点は、本件各貸室につき賃貸借契約の更新ないし賃料の変更合意がなされた日であり、本件貸室10は平成24年2月21日、本件貸室11は平成24年3月5日、本件貸室12は平成24年4月1日、本件貸室13ないし同16は平成24年4月30日、本件貸室17ないし24は平成24年5月27日、本件貸室1ないし7は平成25年10月31日、本件貸室8は同年11月17日、本件貸室9は同年12月16日である。
イ 現行賃料の不相当性
仮に、原告が前記(原告の主張)イ(ア)ないし(ウ)において主張する各価格等が上昇しているとしても、同上昇の事実をもって原告が請求する増額賃料の相当性が立証される訳ではない。
本件貸室10ないし24は、いずれも、本件死亡事故があった平成23年3月以前に賃貸借契約が締結されており、同契約締結に当たり、本件死亡事故は賃料額決定の要素となっていない。
本件貸室1ないし9は、本件各貸室のうち本件死亡事故より前に賃貸借契約が締結された本件貸室17ないし24と比較して、4000円が減額されたにとどまるのであり、同減額も、従前の賃貸借を踏まえた交渉の結果に過ぎないことからすれば、上記9室の賃貸借契約締結に当たり、事故物件の減額が行われていないことは明らかである。
ウ 相当賃料
転貸の収支は、事情変更とは無関係であり、相当賃料の算定に当たって考慮すべき事実ではない。そもそも、原告が基準とするところの適正費用・収益は、何をもって適正としているのかが不明であり、原告からは、そのような適正費用・収益を基に相当賃料を定める根拠も全く示されていない。 第3 当裁判所の判断
1 被告リブ・マックスの被告適格の有無(本案前の主張)(争点(1))
証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば、被告リブ・マックスは、平成26年7月1日、新設分割により被告リブマックスPMを設立し、同被告に対し、被告リブ・マックスが経営する事業のうち、サブリース事業及びウィークリー・マンスリーマンションの仕入事業に関する権利義務を被告リブマックスPMに承継させたこと、これにより、被告リブマックスPMは、原告と被告リブ・マックスとの間の本件各賃貸借契約に関する権利義務を承継したこと、その一方、被告リブ・マックスは、被告リブマックスPMが承継する一切の債務について、併存的に債務を引き受けたことが認められる。
被告リブ・マックスに対する本件訴えは、原告が、原告と被告リブ・マックスとの間における、本件各賃貸借契約に関する賃料額をめぐる権利義務の存否を確定する判決を求めるものであり、その法律関係は、原告と被告リブ・マックスとの間で決せられるべきものである上、上記のとおり、被告リブ・マックスは、被告リブマックスPMが承継する一切の債務について、併存的に債務を引き受けているのであるから、被告リブ・マックスに本件訴えの当事者適格がないとの被告らの主張は、採用することができない。
2 賃料増額請求が借地借家法32条1項の要件を充足するか否か(争点(2))
(1) 直近合意時点
直近合意時点とは、現実の合意がなされた時点を指すところ、証拠(甲2、22。枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、本件各貸室の現行賃料の直近合意時点は、本件貸室1ないし8は平成23年10月28日、本件貸室9は平成23年12月16日、本件貸室10は平成22年2月5日、本件貸室11は平成24年3月2日、本件貸室12は平成24年4月1日、本件貸室13ないし16は平成22年3月30日、本件貸室17ないし24は平成22年5月27日、本件貸室25ないし27は平成25年2月1日であると認められる。
被告らは、被告リブ・マックスが、ジョイント・プロパティとの間で、本件各物件の賃貸借契約を更新する際、賃貸条件を吟味した上でそのまま更新すべきかを検討している旨を指摘して更新時においても現実の合意がなされた旨を主張し、本件貸室11について取り交わされた契約変更合意書(甲2の11)及び本件貸室12について取り交わされた家賃等変更通知書(甲2の12)が、被告リブ・マックスとジョイント・プロパティとの間で、サブリースに供している本件各貸室の賃貸条件を検討して更新合意に至っていることを裏付けている旨指摘する。しかし、被告リブ・マックスとジョイント・プロパティとの間で、本件各貸室の賃貸期間満了に当たり、従前の契約条件と同一の条件で賃貸借契約を継続する旨合意したことを裏付ける確たる証拠が見当たらず、上記各書面によっても、各書面が対象とする貸室以外の貸室についての合意更新があると認めるには足りない。よって、直近合意時点に関する被告らの上記主張は採用できない。
(2) 現行賃料の不相当性
ア 原告は、直近合意時点から改定時期までに生じた変動事由(不動産価格、建設コスト及び周辺賃料の各上昇、本件死亡事故の影響及び賃料を低額にする賃貸人の事情等の各消失)を指摘し、また、本件各貸室の現行賃料と新規適正賃料や本件建物内にある本件各貸室以外の貸室の改定後賃料とも乖離しているとして、現行賃料が不相当になった旨主張するところ、証拠(甲16ないし21)及び弁論の全趣旨によれば、前記(1)において認定した本件各貸室に係る賃料の直近合意時点を基準とした場合、不動産価格、建設コスト及び周辺賃料の相場が、平成28年度においていずれも上昇していることが認められる。
イ しかし、不動産価格等の上昇についてみると、一般的に、上記価格等につき上昇傾向がみられることは、居室等の賃料額に影響を与え得る事由であるとはいえるものの、居室等の賃料額の増減に影響を与えうる事由は種々考えられるところであることに照らせば、上記相場の上昇傾向のみをもって、直近合意時点の賃料が増額請求時点までの間にいかなる影響を受けたかを具体的に把握することはできないというべきであるし、本件各貸室の現行賃料が、賃料増額請求時点において不相当となったとも認められない。
ウ また、本件死亡事故による影響についてみると、そもそも、本件貸室1ないし9の現行賃料を決定する際に、本件死亡事故の影響を踏まえて大幅な減額がなされたとまでは認められず、同事故の影響の消失を指摘して現行賃料が不相当になった旨をいう原告の主張は採用できない。
すなわち、本件貸室1ないし9の賃料額(いずれも8万6000円)について、20%以上の減額が見込まれたということは、元々の賃料額が10万7500円以上であったことを意味するが、上記各貸室に係る賃貸借契約締結当時、上記各貸室の賃料額がそうした水準にあったことを認めるに足りる証拠は見当たらず(なお、本件死亡事故直前において、類似の階層にあり、同一の貸室面積を持つ貸室(本件貸室17ないし24)につき合意された賃料額は9万円である。)、上記各貸室について20%以上の減額が見込まれたとは考えにくい。また、被告リブ・マックスは、本件死亡事故前である平成22年2月5日に1室(本件貸室10)を賃料11万5000円で、平成22年3月30日に4室(本件貸室13ないし16)を賃料11万円で、平成22年5月27日に8室(本件貸室17ないし24)を9万円で、それぞれジョイント・プロパティから賃借しているところ、上記のとおり、貸室の賃借数が増加し、しかも同一機会にまとまった数の貸室を賃借するごとに賃料が減額される傾向がみられることに照らすと、平成23年10月ないし同年12月までに契約された本件貸室1ないし9についての減額の影響が、貸室の賃借数の増加に伴うものである旨の被告らの主張を、むやみに排斥することはできないというべきである。
エ そして、本件各賃貸借契約が、空室率の高い時期に締結されたことなど、当時の賃貸人の特殊な事情により締結された旨をいう原告の同主張は、本件建物の空室率を含む賃貸人側の事情の変動を指摘するものにすぎず、経済事情の変動により現行賃料が不相当になったことを主張するものではないから、採用できない。
オ また、原告は、本件各貸室の現行賃料が、同貸室の新規適正賃料に比べて30%も乖離していること、また、本件建物内にある本件各貸室以外の貸室の改定後賃料とも乖離していることを指摘して、本件各貸室の現行賃料が、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった旨を主張し、本件各貸室の新規適正賃料を裏付ける証拠として、本件各貸室の調査報告書(甲10ないし14)を提出する。
しかし、各調査報告書は、いずれも平成28年7月31日時点の調査価格を示すにとどまり、直近合意時点以降における賃料を基準として、同賃料が不相当となったか否かの判断要素となる借地借家法32条1項所定の各要素に照らして算出された適正賃料を示すものではないばかりか、直近合意時点と賃料増額請求時点における、借地借家法32条1項所定の経済事情の変動や、これが本件各貸室の賃料に与えた影響、直近合意時点から賃料増額請求時点までの間における近傍同種の建物の借賃の増減、その増減を踏まえた本件各貸室の賃料との比較を示すものではないから、上記各調査報告書をもって、本件各貸室の現行賃料が不相当になったと認めることはできず、その他、本件各貸室の現行賃料が不相当になったことを認めるに足りる的確な証拠はない。
カ なお、原告は、相当賃料に係る主張において、被告らが実施するサブリース事業等が、応分のリスクを負担するものではなく、極めて特殊なものである旨を指摘するので、現行賃料の不相当性を認めるべき事情に当たるか否かについて念のため検討すると、証拠(甲2、22。枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、被告リブ・マックスが、ジョイント・プロパティとの間で、本件建物の一部の貸室を対象とした定額借上賃貸借契約(本件各賃貸借契約)を締結したこと、同契約において、被告リブ・マックスは、1か月前ないし2か月前の予告により同契約を解除できることや、被告は敷金・保証金・更新料を負担しないことなどが合意されたことが認められ、こうした契約内容等に照らせば、被告らが転貸事業を展開するに当たり一定のリスク軽減措置を組み込んだことは、本件各賃貸借契約締結時に前提とされ、各直近合意時点の賃料にもその旨が反映されていたというべきであるから、被告らの転貸事業が特殊であることを指摘して現行賃料が不相当になった旨をいう原告の主張は採用できない。
3 結論
よって、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 民事第37部 (裁判官 辻由起) 別紙(省略)