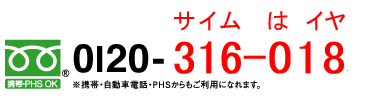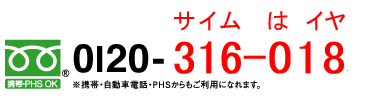最高裁判所第一小法廷 平成14年(受)第852号 平成15年10月23日
1
いわゆるサブリース契約において賃料保証特約が存在するとしても、特段の事情のない限り、賃料増減額請求に関する借地借家法32条の適用があるというべきであるが、賃料増減額の当否と相当賃料額の判断に当たって、賃料保証特約の存在や保証賃料額が決定された事情を考慮すべきである。
2
サブリース契約における賃料減額請求の当否や賃料相当額の判断に当たっては、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合的に考慮すべきであり、特に賃料保証特約の存在や保証賃料額が決定された事情をも考慮すべきである。
3
サブリース契約は建物賃貸借契約に当たり、借地借家法の適用があり、特段の事情のない限り借地借家法32条の適用がある。
判決理由 以下一部抜粋
3 原審は、次のとおり説示して、上告人の本訴請求<1><2>を棄却し、同<3>を却下し、被上告人の反訴請求<1><2>を認容すべきものと判断した。
(1) 本件契約における合意の内容は、被上告人が上告人に本件建物を賃貸し、上告人が被上告人にその対価として賃料を支払うという建物賃貸借契約そのものであるから、本件契約に借地借家法の適用があることは明らかである。
(2) 建物賃借人の賃料減額請求権を認めた借地借家法三二条と建物賃貸人の解約に正当事由を要求する同法二八条は、相互に補完し合って借家関係を規律するものであり、仮に賃貸人による解約に制限がない場合には、賃借人が賃料減額の判決を得ても、賃貸人が賃貸借契約を解約することによって、賃料減額の判決の効力が事実上否定されることとなるから、この場合、裁判所が賃料額について審理判断するのは無益であり、賃借人に賃料減額請求権を認める必要もない。
そして、本件契約のように転貸目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約が終了しても賃貸人が転貸借契約を承継して転借人が建物の使用を継続できるものについては、賃貸人が賃貸借契約の解約を申し入れるについて、特別の事情のない限り、解約の正当事由が肯定され、賃貸人による解約に制限はないものと解するのが相当であるから、本件契約では、本来、被上告人による解約に制限がなく、上告人に借地借家法三二条の賃料減額請求権は認められないものというべきである。
なお、賃貸借契約の当事者がその本来有する解約の自由を一定期間放棄し、その間の賃料額を固定する合意をしているときには、そこに私的自治が行われているのであるから、裁判所は、これを尊重してその内容に介入してはならず、その結果、当事者は、借地借家法三二条の賃料増減額請求権を行使することができないと解するのが相当である。
したがって、上告人には借地借家法三二条の賃料減額請求権は認められないから、上告人の本訴請求<1><2>は理由がなく、被上告人の反訴請求<2>は理由がある。また、賃料保証の内容に変更がないから、被上告人の反訴請求<1>も理由がある。
(3) 上告人の本訴請求<3>は、将来契約期間が経過したときの法律関係の確認請求であり、現在確定することができないものであるから、同請求に係る訴えは、訴えの利益がなく、不適法である。
4 しかしながら、原審の上記(1)の判断は是認することができるが、(2)の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
本件契約が建物賃貸借契約に当たり、これに借地借家法の適用があるという以上、特段の事情のない限り、賃料増減額請求に関する同法三二条も本件契約に適用があるというべきである。
本件契約には賃料保証特約が存し、上告人の前記賃料減額請求は、同特約による保証賃料額からの減額を求めるものである。借地借家法三二条一項は、強行法規であって、賃料保証特約によってその適用を排除することができないものであるから(最高裁昭和二八年(オ)第八六一号同三一年五月一五日第三小法廷判決・民集一〇巻五号四九六頁、最高裁昭和五四年(オ)第五九三号同五六年四月二〇日第二小法廷判決・民集三五巻三号六五六頁参照)、上告人は、本件契約に賃料保証特約が存することをもって直ちに保証賃料額からの減額請求を否定されることはない。
ところで、本件契約は、不動産賃貸業等を営む会社である上告人が、土地所有者である被上告人の建築したビルにおいて転貸事業を行うことを目的とし、被上告人に対し一定期間の賃料保証を約し、被上告人において、この賃料保証等を前提とする収支予測の下に多額の銀行融資を受けてビルを建築した上で締結されたものであり、いわゆるサブリース契約と称されるものの一つである。そして、本件契約は、上告人の転貸事業の一部を構成するものであり、それ自体が経済取引であるとみることができるものであり、また、本件契約における賃料保証は、被上告人が上告人の転貸事業のために多額の資本投下をする前提となったものであって、本件契約の基礎となったものということができる。しかし、このような事情は、本件契約に借地借家法三二条が適用されないとする特段の事情ということはできない。また、本件契約に転貸借承継合意が存することによって、被上告人が解約の自由を有するということはできないし、仮に賃貸人が解約の自由を有するとしても、賃借人の賃料減額請求権の行使が排斥されるということもできない。ただし、賃料減額請求の当否や相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合考慮すべきであり、特に本件契約においては、上記の賃料保証特約の存在や保証賃料額が決定された事情をも考慮すべきである。
以上によれば、本件契約の当事者が借地借家法三二条に基づく賃料増減額請求権を行使することができないとの判断に立って、上告人の本訴請求<1><2>を棄却し、被上告人の反訴請求<2>を認容すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中本訴請求<1><2>及び反訴請求<2>に関する部分は破棄を免れない。そして、上告人の賃料減額請求の当否等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき、本件を原審に差し戻すこととする。なお、上告人は、本訴請求<3>に関する上告については上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから、同部分に関する上告は却下することとする。
東京地方裁判所 平成28年(ワ)第12351号 平成29年11月29日
本件は、原告及び被告ほか2名の合計4名で締結した協定書の内容に被告が違反して原告が損害を負ったとして、債務不履行に基づき、損害金1233万4980円及びこれに対する請求後である平成28年5月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
千葉県(以下略)
原告 株式会社AZ
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 田中康友
千葉県(以下略)
被告 エイジニアリング株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 河合敏男 主文
1 被告は、原告に対し、金1233万4980円及びこれに対する平成28年5月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 この判決は、1項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は、原告及び被告ほか2名の合計4名で締結した協定書の内容に被告が違反して原告が損害を負ったとして、債務不履行に基づき、損害金1233万4980円及びこれに対する請求後である平成28年5月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実
当事者間に争いがないか、証拠(証人C、被告代表者)、後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実は、以下のとおりである。
(1) 協定締結
平成26年3月27日、原告、被告、訴外広島建設株式会社(以下「広島建設」という。)及び訴外有限会社ベスト・ワン・ハウス(以下「ベスト・ワン・ハウス」という。)は、原告代表者Aが個人で所有する千葉県(以下略)の土地上に、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付高齢者向け住宅(名称「D」。以下「本件高齢者向け住宅」という。)を原告が建築し、これを社団法人移住・住みかえ支援機構(以下、単に「支援機構」という。)に賃貸し、被告が支援機構とサブリース契約を締結して本件高齢者向け住宅の施設運営を行う事業(以下「本件事業」という。)の開始を目的として、相互に協力する旨の協定書(甲1)を締結した(以下「本件協定」という。)。
(2) 本件協定1項の内容
本件協定1項には、その本文部分において、協定書添付の「工程表…を順守し、事業を進めるものとし、社会情勢や止むを得ない事由を除き、それぞれが担当している業務に遅延、又は、それを理由に関係者及び第三者に対して損失を与えた場合は、それぞれの担当が責任と負担を持って対処するものとする。尚、各担当の業務は次の通りとする。」と規定されている。なお、上記「工程表」において、補助金申請は平成26年5月から6月までになされ、同年7月には工事着工するものとされている。
本件協定1項のなお書き部分に基づく各人の行うべき業務は、以下のとおりである。
ア 原告
・ 事業主として、本件事業の開始に必要な行政及び関係機関等に対する申請書類への署名捺印
・ 広島建設と本件高齢者向け住宅の建築工事に関する請負契約の締結及び本件高齢者向け住宅の建築費用の負担
・ 事業主として、上記建築工事に伴い負担すべき水道負担金等の諸費用の負担
イ 被告
・ 本件事業の所轄行政庁である千葉県へのサービス付高齢者向け住宅事業の事業者(施設運営者)としての登録に係る一切の業務(以下「本件事業者登録業務」という。)
・ 本件事業に係る国土交通省に対する補助金申請及び補助金受領に関する一切の業務(以下「本件補助金業務」という。)
手続の流れは、千葉県への登録を条件として事前に事務局へ事前申請を行い、1ないし2か月で補助金交付決定書が発行される。建物(本件高齢者向け住宅)の完成後、再度申請を行い、申請後1か月で登録事業者に補助金が交付されるというものである。当該補助金は、良質なサービス付高齢者向け住宅の供給を図るため、国土交通省において事業主に対して事業資金の一部を補助する制度に基づき、交付されるものである。
ウ 広島建設
・ 本件高齢者向け住宅の建築に係る所轄行政庁に対する申請手続(建築確認申請及び完了検査申込から検査済証の発行までの一連の業務)及び建築工事の施工
・ 被告が行う本件事業の登録申請に必要な図面の作成
・ 被告が行う本件事業の補助金申請に必要な図面及び書類の作成
エ ベスト・ワン・ハウス
・ 原告、被告及び広島建設の各業務の補助及び管理監督業務
(3) その後の経緯
平成26年5月23日までに、被告は本件事業者登録業務を完了した。
平成27年4月27日、原告、広島建設及びベスト・ワン・ハウスは被告に対し、本件補助金業務を7日以内に行うよう催告した(甲6の1・2)。
同年6月10日、原告、広島建設及びベスト・ワン・ハウスは被告に対し、被告の債務不履行を理由として、本件協定を解除するとの意思表示をした(甲9の1・2)。
被告は、本件補助金業務に係る申請をしていない。
2 争点
(1) 本件協定1項の法的性質(請求原因関係)
(2) 被告の帰責事由(抗弁関係)
(3) 損害の有無及び内容(請求原因関係)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 本件協定1項の法的性質
(原告の主張)
本件協定当事者は、本件協定1項により、本件協定当事者が本件協定に基づく義務(債務)の履行を懈怠することによって他の本件協定当事者に損害を与えた場合、その損害の責めを負う旨の規定である。その法的効力を否定すべき根拠はない。
(被告の主張)
原告と被告との間の本件協定による契約関係を否認する。
本件協定は、本件事業を実現させるための準備として、当事者間の役割分担を定めたものにすぎず、紳士協定であって、具体的な債権債務関係を生じさせるものではない。このことは、重要な立場にある支援機構が本件協定の当事者に加わっておらず、事業実現の確実性が必ずしも担保されていないことからも明らかである。
(2) 被告の帰責事由
(被告の主張)
履行遅滞につき、被告には何ら帰責事由がない。
本件協定によれば、被告が本件補助金業務をするのに先立って、広島建設において「必要な図面及び書類の作成」がなされる必要がある。その広島建設が作成すべき必要書類には、少なくとも、配置図、平面図、住戸タイプごとの平面詳細図、用途別求積表、面積表、按分面積表、工事費内訳書があるところ、これらのほとんどが整っておらず、今日に至っても、被告は広島建設から必要書類を受け取れていない。少なくとも被告に帰責性はなく、被告に請求するのは筋違いである。
(原告の主張)
否認ないし争う。
被告が本件協定で合意した補助金申請義務を履行しなかった理由は、図面の未完成などではなく、別件事業における広島建設の建物施工に関する不満である。補助金申請に必要な図面は遅くとも平成26年4月11日には完成しており、被告もこれを用いて補助金申請を行うと明言していた。
(3) 損害の有無及び内容
(原告の主張)
原告は、本件事業が白紙となったことで、以下のとおり、合計1233万4980円の損害を被った。
ア 広島建設への支払分(合計953万4980円)
・ 地盤調査費用…37万4000円
・ 電波障害事前調査費用…5万4000円
・ 設計費用…837万円
・ 確認申請費用等…38万9000円
・ 設計住宅性能評価申請料…12万7980円
・ 諸経費…21万6000円
建築確認申請は見地を始める前に取得しなければならず、同申請のためには添付設計図面の作成が必要である。平成25年8月29日、原告は広島建設に対して、設計業務を依頼し(甲10)、広島建設において、設計図面を作成して、平成26年1月24日に確認申請書を提出し、同年2月27日に確認が下りている(甲12)。広島建設は受託した業務を完了しており、原告に対してその費用請求をしているにすぎない(甲14)。
イ 有限会社若葉設計企画への支払分…280万円
本件高齢者向け住宅を建築するためには都市計画法29条の許可を要するため、原告が有限会社若葉設計企画に業務を委託し、その許可を取得した(甲15)。
(被告の主張)
否認ないし不知。
本件協定によれば、原告と広島建設との工事請負契約は、補助金交付決定通知書発行後、遅滞なく締結するものとされ(4項)、本件事業の建物の間取り及び仕様は、関係者全員にて協議した後に締結する原告と広島建設との工事請負契約書に記載する内容にて確定するものとされている(5項)。
しかし、補助金交付決定通知は発行されておらず、原告と広島建設との工事請負契約は未だ締結されているはずがない。本件事業の建物の間取りや仕様について関係者間の協議は行われておらず、設計図面も未確定である。この段階で、広島建設から原告に対する設計費用等の請求権が正当に発生するはずがない。 第3 当裁判所の判断
1 本件協定1項の法的性質について
本件協定1項は、その体裁をみても、本件協定当事者が本件協定に基づく義務(債務)の履行を懈怠することによって他の本件協定当事者に損害を与えた場合、その損害の責めを負うことを、法的拘束力をもって定めたものとみるしかなく、原告の主張するとおりと認められる。
被告は本件協定1項が紳士協定であるなどと主張するが、本件協定1項全体が紳士協定であるとの主張と解すると、役割分担を定めた部分まで法的拘束力がないということになり、それを根拠とした被告のその他の主張と整合性が取れない。他方、本件協定1項の責任に関する部分のみが紳士協定であるとの主張と解すると、同じ項内に法的拘束力が生じない本文部分と法的拘束力が生じるなお書き部分とが存在することとなるが、本文部分で担当業務について触れられている本件において、そのような解釈は不自然というほかない。支援機構が本件協定の当事者でないことや本件協定に至る経緯は、被告がほか3名と本件協定(合意)に及んだ以上、前記判断を左右する要素とはならない。被告の主張は採用できない。
2 被告の帰責事由について
(1) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
広島建設特建事業部に所属する本件事業担当者C(以下「C」という。)と被告代表取締役B(以下「B」という。)は、別紙メール一覧のとおり、電子メールのやりとりをした(証拠は同別紙記載のとおり)。
(2) 上記認定によれば、Cは、平成26年4月11日には、本件補助金業務に係る申請に必要な図面や資料等のデータ一式をBに提供している。Bは、同月23日には本件補助金業務に取り掛かる旨をCに伝えており、さらに、工程表において本件補助金業務に取り掛かるものとされている平成26年5月に入っても、Bは、Cら広島建設側に対し、前記資料等一式の過不足について特段の指摘もしていない。
そうすると、本件協定1項により広島建設の役割とされている「必要な図面及び書類の作成」はなされており、これらはすでに被告に提供されているというべきである。
被告代表者Bは、被告側が合意できない図面では本件補助金業務に取りかかれない、再三再四丁寧なミーティングを申し入れていた旨供述するが、本件事業が訪問介護サービスを前提とし、本件高齢者向け住宅に相談室の設置が不可欠であったことについて、本件事業の関係者間で共通認識ができていたことを示す的確な証拠はないといわざるを得ない。
その他、被告に帰責事由がないことを示す事情はうかがわれない。
(3) 以上によれば、被告に帰責事由がないとは認められない。
3 損害の有無及び内容について
証拠(証人C、甲10ないし18)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事業につき、広島建設に953万4980円及び有限会社若葉設計企画に280万円を支払ったことが認められる。
原告主張に係る損害は、建築確認申請と都市計画法上の許可に係る費用支出である(証人C、甲10ないし13、15、16)。前提事実によれば、建築確認申請自体は広島建設の役割、本件高齢者向け住宅の建築費用負担は原告の役割とされていたところ、被告が本件補助金業務を行わず、本件協定が解除された結果、本件事業は本件協定当事者では遂行できないこととなったのであるから、本件事業に関して原告が負担した上記費用支出は、被告が本件補助金業務を行わなかったことと相当因果関係のある損害と認められる。
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば、本件協定において合意されたのは、本件高齢者向け住宅の間取り及び仕様については、関係者全員で協議した後に、原告と広島建設との間で締結する工事請負契約書に記載する内容で確定すること(本件協定5項)、その工事請負契約は本件補助金業務に係る補助金をはじめ各種申請の後になされることとされていたこと(工程表)であり、本件協定上、建築確認申請等の際に本件高齢者向け住宅の図面が最終確定していることまでは予定されていなかったと認められる。被告の主張は採用できない。
4 結論
以上の次第で、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判決する。 民事第16部 (裁判官 川﨑学) 別紙(省略)
東京地方裁判所 平成28年(ワ)第12897号 平成29年10月30日
サブリース契約上の清掃業務契約及び代金回収業務契約の成立
判決
東京都(以下略)
原告 X
同訴訟代理人弁護士 川端啓之
東京都(以下略)
被告 Y1株式会社
(以下「被告Y1」という。)
同代表者代表取締役 Y2
東京都(以下略)
被告 Y3株式会社
(以下「被告Y3」という。)
同代表者代表取締役 Y4
上記両名訴訟代理人弁護士 田中宏明
主文
1 被告Y1は、原告に対し、168万4800円及びうち42万1200円に対する平成28年12月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を、うち42万1200円に対する平成29年1月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を、うち42万1200円に対する平成29年2月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を、うち42万1200円に対する平成29年3月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 被告Y1は、原告に対し、143万2759円及びこれに対する平成29年3月11日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
3 被告Y3は、原告に対し、110万9923円及びこれに対する平成28年5月8日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
4 被告Y3は、原告に対し、8万4780円及びこれに対する平成28年5月8日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
5 原告の被告Y3に対するその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は被告らの負担とする。
7 この判決は、1ないし4項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主文1項と同旨
2 主文2項と同旨
3 主文3項と同旨
4 被告Y3は、原告に対し、8万4780円及びこれに対する平成28年5月8日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、原告が
(1) 原告を代表取締役とする株式会社Aと被告Y3間において、平成27年、Aが所有し原告が居住していた別紙物件目録記載の土地及び建物(以下、土地と建物を併せて「本件不動産」といい、建物を「本件マンション」という。)を被告Y3が購入する売買契約の締結に向けて交渉がなされた際、本件マンションが日本語学校に通う外国人学生の寮などに使用されていたことから、居住者からの苦情処理など現場での管理業務が困難であったため、その管理業務の履行を誰がいくらの報酬で行うかが問題となり、原告、被告Y3及び上記本件不動産の売買契約を仲介した被告Y1の三者間において、平成27年5月19日、被告Y3が被告Y1に本件マンションの管理業務を委任し、その業務のうち現場での対応を要する業務を本件マンションに居住している原告に再委任して、被告らが原告に対し、1200万円の和解金(被告Y3負担分は357万6000円、被告Y1負担分は842万4000円)を、原告が行う管理業務に対する報酬の一部として支払うとの内容の和解契約(以下「本件和解契約」という。)が成立し、原告及び被告Y1は、被告Y1が原告に対して支払うべき上記842万4000円を、平成27年7月13日から平成29年2月まで毎月末日限り42万1200円ずつ分割して支払うことを合意したとして、被告Y1に対し、本件和解契約に基づく和解金支払請求権として、上記分割金のうち、平成28年11月支払分から平成29年2月支払分の4か月分である168万4800円及び上記期間の各月の支払日の翌日である平成28年12月から平成29年3月までの毎月1日から支払済みまで、1か月当たり42万1200円に対する年6%の割合による遅延損害金の支払を
(2) 上記(1)のとおり、被告Y3が被告Y1に対し、平成27年7月13日、本件マンションの賃料管理等の管理業務を委任し、被告Y1は、原告に対し、上記管理業務のうち苦情の処理など現場対応が必要な業務を、期間を5年間、報酬を当該月に本件マンションの賃借人から得られた賃料の4.86%の額(消費税相当額を含む。以下、消費税のかかる金員の金額については特に断らない限り同じ。)、報酬の弁済期を翌月10日に当月分を支払うと定めて再委任し(以下「本件再委任契約」という。)、原告は平成27年7月13日から平成28年2月末日までこの業務を履行したとして、被告Y1に対し、上記期間中に発生した本件再委任契約に基づく業務報酬請求権として、143万2759円及びこれに対する最終支払期の翌日である平成28年3月11日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を
(3)ア 被告Y3が原告に対し、本件建物の清掃業務を月額12万9600円と定めて請け負わせ(以下「本件清掃業務契約」という。)として、原告は、平成27年7月13日から平成28年2月末日までこの業務を行ったとして、被告Y3に対し、主位的に本件清掃業務契約に基づく報酬請求権として、予備的に事務管理に基づく費用償還請求権として、98万6612円(平成27年7月分の報酬は7万9412円、平成27年8月ないし平成28年2月分の報酬は月額12万9600円)及びこれに対する被告Y3に対する訴状送達日の翌日である平成28年5月8日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金を
イ 被告Y3が原告に対し、本件建物に設置されたプリペイド式のセントラル給湯・暖冷房システムであるヒーツ(HEATS:HousingHeating Total Systemの略称である。)の代金回収業務を月額1万6200円と定めて請け負わせ(以下「本件代金回収業務契約」という。)、被告は、この業務を、平成27年7月13日から平成28年2月末日まで行ったとして、被告Y3に対し、本件代金回収業務契約に基づく報酬請求権として、12万3311円(平成27年7月分の報酬9911円と平成27年8月ないし平成28年2月分の7か月分11万3400円の報酬の合計額)及びこれに対する被告Y3に対する訴状送達日の翌日である平成28年5月8日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を、
(4) 東京都水道局から原告に対し、平成27年11月末頃、本件マンション内で漏水が発生していることを告げられたため、原告が有限会社Bに対し、被告Y3が行うべき漏水調査及び修理を依頼し、その費用として、Bに8万4780円を支払ったとして、被告Y3に対し、事務管理に基づく費用償還請求権として、8万4780円及びこれに対する被告Y3に対する訴状送達日の翌日である平成28年5月8日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を
それぞれ求めた事案である。
2 前提事実(証拠の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1) Aは、平成2年5月15日までに、本件不動産を取得した。
(2) 原告は、被告Y1を仲介業者として、被告Y3に対し、平成27年5月19日、本件マンションを、4億4144万円で売った(以下「本件売買契約」という。)。
(3) 原告は、(2)の売買の際、本件マンションの管理人の業務を行っていた。
(4) 本件和解契約に基づく原告の被告Y1に対する分割金支払請求権の発生
ア 原告は、被告らとの間で、平成27年5月19日、次のとおりの合意(すなわち本件和解契約)をした。なお、後記(ウ)は、原告と被告Y1との間で、平成27年7月13日に合意された内容である。
(ア) 原告は、被告らに対し、本件マンションの管理運営等のアドバイスをする。
(イ) 被告らは、原告に対し、和解金として、1200万円(被告Y1が842万4000円、被告Y3が357万6000円、以下「本件和解金」という。)を、平成27年7月13日(本件マンションの引渡日)に支払う。
(ウ) 原告と被告Y1は、平成27年7月13日、本件和解金の支払方法を、平成27年7月13日を初回として、毎月末日限り、20回(1回につき、42万1200円)に分割して支払うことに変更した。
イ 平成28年11月末日から平成29年2月の各末日が経過した(この間に支払われるべき上記イの分割金の合計額は、168万4800円(42万1200円×4か月分=168万4800円)である。)。
(5) 本件再委任契約に基づく報酬請求権の発生
ア 被告Y3は、被告Y1に対し、平成27年7月13日、本件マンションの管理業務として、賃料滞納督促業務、賃借人苦情受付・処理業務、賃借人解約手続業務(解約の受付、退去立会い、敷金精算)、賃貸借契約更新手続業務、新規賃借人募集業務(以下、これらの業務を「基本管理業務」という。)及び賃貸管理運営上必要又は有益と思われる事項の提案業務を委任した(委任契約がなされたこと自体は当事者間に争いがない。委任業務の内容につき甲1)。
イ 被告Y1は、原告に対し、平成27年7月13日、上記被告Y3から委託を受けた本件マンションの管理業務のうち、基本管理業務の中で現地対応が必要な業務及び賃貸管理運営上必要又は有益と思われる事項の提案業務を、期間を5年間、報酬を本件マンションの賃料収入の4.86%(消費税込)、報酬の支払時期を当月分につき翌月10日限りと定めて委任した(本件再委任契約が締結されたこと自体は当事者間に争いがない。本件再委任契約で定められた業務内容、報酬、期間について甲8)。
ウ 原告は、平成27年7月13日から平成28年2月末日まで、本件再委託契約に基づく業務を履行した。
この間の報酬額は、次のとおりである(合計143万2795円)。
(ア) 平成27年7月分 11万8790円
(イ) 平成27年8月分 19万3817円
(ウ) 平成27年9月分 18万7790円
(エ) 平成27年10月分 19万7240円
(オ) 平成27年11月分 18万7790円
(カ) 平成27年12月分 19万1192円
(キ) 平成28年1月分 17万8070円
(ク) 平成28年2月分 17万8070円
(6) 漏水調査費用請求権
ア 原告は、東京都水道局から、平成27年11月末頃、本件マンションにおいて漏水が発生していることを指摘された。
イ 原告は、有限会社Bに対し、平成27年11月頃、漏水の有無及び漏水が認められる場合にはその原因調査を委任した。
ウ Bは、原告に対し、平成27年12月2日、調査費用の見積書を提出した。
エ 被告Y3は、原告に対し、平成27年12月末頃、漏水修理工事を希望することを告げた。
オ 原告は、Bに対し、平成27年12月末頃、漏水調査及び修理工事を、報酬を8万4780円と定めて請け負わせた。
カ Bは、平成28年1月14日、本件マンションの漏水調査及び修理を完了した。
キ 原告は、Bに対し、平成28年3月15日、オの報酬を支払った。
3 争点と当事者の主張
(1) 原告と被告Y3間において、本件清掃業務契約、本件代金回収業務契約の成否及び報酬金額(争点1)
(原告の主張)
ア 本件清掃業務契約について
原告が被告Y3に対し平成27年6月23日原告が引き続き本件マンションの清掃業務を行う場合の報酬を月額12万9600円(税込み)とする見積書を提出したところ、同被告が何ら異議を述べなかったことから、被告Y3は、原告に対し、平成27年7月13日までに、黙示に、本件マンションの清掃業務を、報酬を12万9600円(ただし、平成27年7月分は、7万9412円)と定めて、請け負わせた(以下「本件清掃業務請負契約」という。)。なお、被告Y3は、原告に対し、平成27年10月15日、4万0981円を支払ったが、原告は、被告Y3のために、本訴において請求する以外にも諸雑費(振込手数料、合鍵代、鍵修理代、鍵交換代)を支出しているため、これらの費用に充当する。
原告は、平成27年7月から平成28年2月まで、本件建物の清掃を行った。
イ 本件代金回収業務契約について
原告が被告Y3に対し平成27年6月8日ヒーツ代金回収業務の報酬が月額1万6200円であることを伝えたところ、被告Y3は何ら異議を述べなかったことから、被告Y3は、原告に対し、平成27年7月13日頃、黙示に、ヒーツ代金の回収業務を、報酬を月額1万6200円(ただし、平成27年7月分は9911円)と定めて委任した。
原告は、平成27年7月13日から平成28年2月末日まで、ヒーツ代金回収業務を行った。
(被告Y3の主張)
ア 本件清掃業務契約について
原告が見積書を提出したことは認め、その余は否認する。被告Y3は、原告が見積書提出直後に清掃業務の報酬を求めてきたのに対し、ただちに異議を述べた。また、被告Y3が原告に対し平成27年10月15日に支払った4万0981円は、振込手数料、合鍵代、清掃用手袋代、薬代、ごみ袋代、ごみ処理券費用、C号室敷金・家賃・共益費等清算金の合算額(振込手数料、C号室敷金・家賃・共益費等清算金については消費税を含めない。)であり、清掃費用についての合意を示すものではない。
また、原告が行ったと主張する清掃については、居住者や物件購入希望者から、あまりに汚れている、ひどすぎる等のクレームが被告Y3に対して入った。原告が清掃業務を行ったとは認められない。
イ 本件代金回収業務契約について
原告の主張は否認する。被告Y3は、原告に対し、異議を申し立てており、本件代金回収業務契約は成立していない。なお、原告は、回収されるヒーツ代金の月額が冬場は約30万円、夏場は約20万円と主張するようになったが、被告Y3は、原告から、当初、年間を通じて月額約30万円と聞いていた。
原告がヒーツの代金回収業務を行ったことは知らない。
(2) 本件マンションの清掃業務による事務管理の成否(争点2)
(原告の主張)
仮に、本件清掃業務請負契約が成立しなかった場合には、原告は、義務なくして、被告Y3のために、本件建物の清掃をしたこととなる(原告の清掃が被告Y3の利益に最もかなうものであったことは、原告が本件売買契約の前から清掃業務を行っていたのに対して被告Y3が改善を求めるなどしていないことからして明らかである。)。
(被告Y3の主張)
原告の主張は否認する。
原告が行ったと主張する清掃については、居住者や物件購入希望者から、あまりに汚れている、ひどすぎる等のクレームが被告Y3に対して入った。原告は、被告Y3の利益に最も適合する方法で清掃をしていない。 第3 当裁判所の判断
以下においては、特に断らない限り、証拠番号の枝番号を省略する。
1 認定事実
後掲各証拠(ただし、次の各認定事実に反する部分を除く)及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。
(1) 株式会社Dは、Aが本件マンションを所有していた平成27年5月まで、Aから本件マンションを賃借し、その管理業務を受託した上、本件マンションをサブリースに提供していた。原告は、Dから、本件マンションの管理、清掃、ヒーツ代金の回収及び送金の業務を依頼されて行っていた。このうち、ヒーツ代金回収業務についての報酬は、月額1万6200円であった(甲69、乙2(特約条項8項)、原告本人、弁論の全趣旨)。
(2) Aは、平成27年初頭頃までに、約50億円の債務を負った。この債務の債権者は、Aに対し、本件不動産を換価して債務を整理することを求めた。このため、Aは、本件不動産を売却することとしたが、同社の代表者である原告は、本件マンションに居住し(ただし、現在の原告の住所とは別の部屋であった。)、Aが得ていた本件マンションの賃料収入を主な収入源としており、本件マンションの売却によって住居及び収入を失うおそれがあったため、売却するにあたり、原告の居住を確保し、原告に管理者としての業務を行わせることを承認する買主を探した。
一方、被告Y1は、本件建物の部屋数が129室あること、そのうち60室ほどが外国人のための寮として提供されていることなどから、原告に本件マンションの現場において必要となる居住者からの苦情受付、処理などの管理業務を行ってもらう必要があると判断した(甲69、原告本人、弁論の全趣旨)。
その結果、Aは、被告Y3に対し、本件建物を売却することとした。
(3) 被告Y1は、原告に対し、被告Y3とA間の本件不動産売買契約締結に先立ち、平成27年4月14日、管理費等月額支出予算書案を提出した。この予算書案では、本件マンション全館の共用部日常清掃業務は週に3回行われる必要があることを前提に、その費用が月額8万円、ヒーツ代金回収・送金業務の手数料が月額1万5000円(ただし、いずれも消費税相当額を除く。)とされていた(甲44、原告本人、弁論の全趣旨)。
(4) 原告は、平成27年4月24日、被告Y1に対し、(3)の予算書に対し、特に清掃業務について、金額が不足であるとして、それまで、Dから受けていた報酬金額を基礎として、報酬額案を電子メールで送信した(甲45、原告本人、弁論の全趣旨)。この報酬額案では、ヒーツ代金回収業務の報酬額が被告Y1により提案された金額と同額の月額1万5000円(ただし、消費税相当額を除く。)とされた。また、清掃業務については、ごみ処理置場清掃業務及びごみの出し方に違反があった場合の調査報告業務報酬が月額8万円、本件マンション全館の日常清掃業務については毎日行う必要があるとの前提で、その報酬が5万円(ただし、いずれも、消費税相当額を除く。)とされた。
(5) 上記(3)及び(4)及び(4)の交渉を経て、原告と被告らは、平成27年5月19日、本件和解契約(前記第2(事案の概要等)2(前提事実)(4))を締結した。
その後、本件マンションの管理業務のうち、基本管理業務及び賃貸管理運営上必要又は有益と思われる事項の提案業務については、前記第2(事案の概要等)2(前提事実)(5)のとおり、被告Y3と被告Y1間で委任契約が締結され、また、被告Y1と原告間で本件再委任契約が締結された。一方、清掃業務及び本件代金回収業務については、契約書が作成されなかった。
(6) ただし、原告及び被告Y3は、合意の上、清掃業務について作業時間を管理するためのタイムカード打刻機を設置し、原告は、Eなる女性に対し、平成27年7月13日から平成28年2月末日にかけて、ごみ置き場清掃及びごみの出し方の違反者の調査、指導の業務を、基本給を月額8万円と定めて依頼した。Eは、作業時間をタイムカードで記録した。同様に、原告は、Fなる男子学生に対し、ごみ置き場以外の共用部分の清掃を、基本給を月額8万円と定めて依頼した。Fは、作業時間をタイムカードで記録した。(甲52ないし67、69、乙1の6枚目、)。
また、ヒーツには1000札しか使用できず、1000円札が溜まりすぎると故障してしまうところ、原告は、被告Y3に対し、平成27年7月13日から平成28年2月末日まで、当初はヒーツに1000円札が100枚たまる都度、後に毎月、ヒーツの代金を送金した。被告Y3は、原告に対し、原告が平成27年8月10日と同年9月15日にした送金金額(20万円)について異議を述べるなどしたが、被告Y1代表者は、原告に対し、平成27年12月2日、「ヒーツの件、納得していただけた模様です。」とのメールを送信した。
2 争点1(原告と被告Y3間における、本件清掃業務契約、本件代金回収業務契約の成否及び報酬金額)について
(1) 被告Y3に対する本件不動産の売主であるAの代表者たる原告が本件不動産を売却した後も本件マンションの管理人として本件マンションから収益を得ようとしたこと(前記1(2))を被告Y3が容易に容認するとは考えにくいこと、基本管理業務等と異なり、本件清掃業務契約及び本件代金回収業務契約については契約書が作成されていないこと(前記1(4))に照らすと、被告Y3と原告との間において本件清掃業務契約及び本件代金回収業務契約が締結されたと認定することには慎重さが必要ではある。
しかしながら、前記1(1)、(3)及び(6)の各認定事実に照らすと、原告は、被告Y1を通じ、本件マンションにおいては、従前から原告が清掃業務、ヒーツ代金回収業務を含めた管理業務を行っており、被告Y3に対してその時の費用を示し、最終的に、被告Y3と原告との合意の上、清掃業務についてはタイムカード打刻機を設置して作業時間を管理することとし、原告は、E及びFに対し、作業の基本給の金額を月額8万円と定めて委任したこと、E及びFはタイムカードを打刻していること、また、ヒーツ代金回収業務については被告Y3からも原告に対し被告Y1を通じて平成27年4月14日に月額1万5000円(ただし消費税相当額を除く。)の報酬で業務を委託する旨の見積書が出されており、また、ヒーツ代金の回収、送金が実際になされていることがそれぞれ認められるとともに、証拠(甲19ないし28)によれば、上記1(4)の範囲内の金額で、本件マンションの共用部の清掃業務及びヒーツ代金回収業務の報酬の請求がなされていることが認められる。これらの事実に被告らが被告らの各代表者の本人尋問を申請し、当裁判所から陳述書の提出を求めたにもかかわらずこれを提出せず、原告本人尋問の期日にも出頭しなかったことなど本件訴訟の経緯を併せ考えると、被告Y3が原告の作業状況を検証しつつ、後に、報酬金額を変更することが予定されていた可能性はあるものの、少なくとも、被告Y3は、原告に対し、上記報酬金額見直しまでの間、原告が被告Y1を通じて被告らに提示した前記1(4)記載の金額の限度で清掃業務、ヒーツ代金回収業務を行わせることを承諾したものと推認できる。
次に、前記1(6)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば、被告Y3は、少なくとも平成28年2月末日まで、原告の行ったヒーツ代金回収業務を履行として受け入れたものと推認される。また、証拠(甲51)によれば、被告Y3は、平成27年12月2日の時点で、E及びFらによる清掃の結果に不満を持っていたと推認されるが、証拠(甲52ないし67)及び弁論の全趣旨によれば、タイムカードによる作業時間管理は継続されており、この間は、清掃業務がなされていたものと推認せざるを得ない。乙1になされた記載のみでは、上記推認は妨げられない。他に上記推認を妨げる証拠はない。
(2) したがって、原告の主張する本件清掃業務契約及び本件代金回収業務契約が成立したことはいずれも認められる。その報酬は、次のとおりである。
ア 本件清掃業務契約に基づく報酬 98万6612円
計算式 7万9412円(甲20、平成27年7月分)+12万9600円×7か月分=98万6612円
イ 本件代金回収業務契約に基づく報酬 12万3311円
9911円(甲28、平成27年7月分)+1万6200円×7か月分=12万3311円
ウ 上記ア及びイの合計額 110万9923円
(3) よって、原告は、被告Y3に対し、本件清掃業務契約及び本件代金回収業務契約に基づく報酬請求権として、110万9923円の支払を請求できる。原告の前記第1(請求)3の請求には理由がある。
3 その余の原告の請求について
(1) 前記第2(事案の概要等)2(前提事実)(4)のことから、原告は、被告Y1に対し、本件和解契約に基づく和解金支払請求権として、前記第1(請求)1のとおりの請求をなしうる。
(2) 前記第2(事案の概要等)2(前提事実)(5)のことから、原告は、被告Y1に対し、本件再委任契約に基づく報酬請求権として、前記第1(請求)2のとおりの請求をなしうる。
(3) 前記第2(事案の概要等)2(前提事実)(6)のことから、原告は、被告Y3に対し、事務管理に基づく費用償還請求権として、前記第1(請求)4のとおりの請求をなしうる。
ただし、事務管理に基づく費用償還債務は商行為によって生じた債務ではないから、その債務の遅延損害金の利率に商法514条は適用できない。遅延損害金の利率は、民法404条により、年5%とされる。
第4 結論
以上のことから、訴訟費用について、原告と被告Y1との間では民訴法61条を、原告と被告Y3との間では同法64条ただし書、61条を、仮執行宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第23部
裁判官 中尾隆宏
別紙(省略)
東京地方裁判所 平成28年(ワ)第14389号 平成29年10月13日
本件は、原告が、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)にある各室の賃借人である株式会社ジョイント・プロパティ(以下「ジョイント・プロパティ」という。)との間で貸室27室(以下、併せて「本件各貸室」という。)を対象とする各賃貸借契約(以下「本件各賃貸借契約」という。)を締結した被告株式会社リブ・マックス(以下「被告リブ・マックス」という。)及び被告リブ・マックスの新設分割に伴い設立された被告株式会社リブマックスプロパティマネジメント(以下「被告リブマックスPM」という。)に対し、原告がジョイント・プロパティから本件各賃貸借契約の賃貸人の地位を承継したこと及び借地借家法32条1項に基づき賃料増額請求をした旨を主張して、被告らに対し、賃料額の確認を求め、また、借地借家法32条2項に基づき、平成29年2月28日現在の差額賃料合計797万6463円及びこれに対する同日までの確定利息44万3143円並びに同差額賃料に対する平成29年3月1日から支払済みまで年10%の割合による利息の各支払を求めた事案である。
東京地方裁判所 平成28年(ワ)第14389号 平成29年10月13日 東京都(以下略)
原告 株式会社ディーホールディングス
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 西中克己
同 上町俊郎
東京都(以下略)
被告 株式会社リブ・マックス
同代表者代表取締役 B
東京都(以下略)
被告 株式会社リブマックスプロパティマネジメント
同代表者代表取締役 B
被告ら訴訟代理人弁護士 齊藤宏和
同 松山太郎 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由
第1 請求
1 原告が被告らに対し賃貸中の別紙物件目録記載の建物に所在する別紙貸室目録の各貸室に係る各月額賃料は、同貸室目録記載の各改定(増額)日から同貸室目録記載の各改定賃料記載の各金額であることを確認する。
2 被告らは、連帯して、原告に対し、841万9606円及びうち797万6463円に対する平成29年3月1日から支払済みまで年10%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)にある各室の賃借人である株式会社ジョイント・プロパティ(以下「ジョイント・プロパティ」という。)との間で貸室27室(以下、併せて「本件各貸室」という。)を対象とする各賃貸借契約(以下「本件各賃貸借契約」という。)を締結した被告株式会社リブ・マックス(以下「被告リブ・マックス」という。)及び被告リブ・マックスの新設分割に伴い設立された被告株式会社リブマックスプロパティマネジメント(以下「被告リブマックスPM」という。)に対し、原告がジョイント・プロパティから本件各賃貸借契約の賃貸人の地位を承継したこと及び借地借家法32条1項に基づき賃料増額請求をした旨を主張して、被告らに対し、賃料額の確認を求め、また、借地借家法32条2項に基づき、平成29年2月28日現在の差額賃料合計797万6463円及びこれに対する同日までの確定利息44万3143円並びに同差額賃料に対する平成29年3月1日から支払済みまで年10%の割合による利息の各支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により明白に認められる事実である。)
(1) 原告は、別紙物件目録記載の建物(本件建物)を所有していたところ、本件建物に所在する各貸室について、ジョイント・プロパティに対して賃貸した。
(2) ジョイント・プロパティは、被告リブ・マックスとの間において、別紙貸室目録中の各貸室27室(本件各貸室。なお、本件各貸室のうち、個々の貸室を別紙貸室目録の番号に従い「本件貸室1」「本件貸室2」などという。)について、賃貸借期間開始日を同目録記載「賃貸借期間・開始日」とし、月額賃料(以下、月額賃料を単に「賃料」ということがある。)を同目録記載「現行賃料」の金額として、賃貸借(転貸借)契約(本件各賃貸借契約)を締結した(ただし、本件貸室9及び11の当初賃借人は、被告リブ・マックスの関連会社であるグッド・コミュニケーション株式会社であり、平成26年3月、同社の地位を被告リブ・マックスが承継した。)。
(3) 被告らは、本件各貸室において、サブリース事業、マンスリー(ウィークリー)マンション事業等を実施している。
(4) 原告は、平成26年12月19日、本件建物について、三菱UFJ信託銀行株式会社に対し、信託を原因として所有権を移転し、これに伴い、ジョイント・プロパティから本件各賃貸借契約の賃貸人の地位を承継し、被告リブマックスPMは、当該承継を承諾した。
(5) 原告は、本件各賃貸借契約の各更新に先立ち、被告リブ・マックスに対し、以下の日時に、いずれも更新日である別紙貸室目録記載の各改定日を始期として、同目録記載の改定賃料への増額を請求した。
ア 本件貸室1ないし9については、平成27年9月18日
イ 本件貸室10ないし16については、平成28年1月27日
ウ 本件貸室17ないし24については、平成28年3月9日
エ 本件貸室25ないし27については、平成29年1月11日
(6) 被告リブマックスPMは、原告からの前記(5)アの増額請求に対し、平成27年9月29日付け回答書(甲6)を原告に送付して、平成23年3月に本件建物の共用部において自殺案件(共用部からの転落による死亡事故。以下「本件死亡事故」という。)があり、重要事項告知義務があるものとして近傍類似の賃料と比較して格安の賃料にて借り上げた経緯があるとして、原告の増額請求には応じられない旨回答した。(甲6)。
2 争点
(1) 被告リブ・マックスの被告適格の有無(本案前の主張)
(被告らの主張)
被告リブ・マックスは、平成26年7月1日に、同社の新設分割に伴い設立した被告リブマックスPMに対し、ウィークリー事業不動産賃貸事業及びサブリース事業に係る権利義務を譲渡し、これにより、原告の有する本件各貸室についての権利義務も、同日をもって、被告リブマックスPMが承継した。
よって、原告の被告リブ・マックスに対する本件請求は、被告適格を欠き、不適法なものとしていずれも却下されるべきである。
(原告の主張)
会社分割の対象となる権利義務の存否及び帰属は民法等一般原則の定めに従うとも解されており、本件賃貸借契約においては、賃借人の変更は明示的に禁止され、又は、賃貸人の承諾なく賃借人を変更できる旨の定めはないから、民法等一般原則に従い、賃貸人の承諾なく、賃借人の変更は効力を生じない。
仮に、賃貸人の地位が会社分割により被告リブマックスPMに承継されたとしても、被告リブ・マックスは賃料債務を併存的に引き受け、かつこれを表示している。よって、被告リブ・マックスは、賃料支払債務を連帯して負う。
(2) 賃料増額請求が借地借家法32条1項の要件を充足するか否か
(原告の主張)
ア 直近合意時点
本件各貸室の現行賃料の直近合意時点は、当初賃貸借契約締結の日(ただし、本件貸室12は平成24年4月)である。
イ 現行賃料の不相当性
現行賃料は、後期(ア)ないし(オ)記載の直近合意時点から改定時期までの変動事由により、不相当になった。
また、本件各貸室の改定前賃料(別紙貸室目録記載の現行賃料)は、同貸室の新規適正賃料(同目録記載の改定賃料)に比べ、17室において30%も乖離しており、また、本件建物内にある本件各貸室以外の貸室の改定後賃料とも乖離している。本件各貸室の現行賃料は、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった。
(ア) 不動産価格の上昇
本件建物と同一需給圏内になる地価公示地点における最終合意時点と現在の価格変動に照らすと、各最終合意時点から現時点まで、本件建物の周辺地価においては、全体として10%前後の地価上昇がみられる。また、本件建物の近隣地区(C地区・本件建物の周囲3km四方圏内)におけるマンション売買(分譲)価格は、総じて20%~30%を超える上昇を示している。
(イ) 建設コストの変動
東京都における鉄筋コンクリート共同住宅の建築費指標に照らすと、建設コスト(工事原価)は15%前後の上昇率を示している。
(ウ) 周辺賃料の上昇
C・D地区における共同住宅賃料指数(シングルタイプ・18m2以上30m2未満。平成21年第1四半期を100)に照らすと、周辺賃料水準は10%近い上昇率を示し、改定時期以降も上昇傾向にある。
(エ) 本件死亡事故の影響の消失
本件死亡事故の影響を受けているのは、平成23年10月~12月までに契約した9室(本件貸室1ないし9)である。当該9室は、いずれも月額賃料を1室8万6000円として契約されているところ、本件死亡事故を理由として低額である賃料が定められた。一般的に事故物件であることを理由として募集賃料の減額割合は20%程度・2年間とされていることから、当該9室についてもいわゆる事故物件としての減額が20%以上見込まれたことは明らかである。よって、本件死亡事故から5年以上経過した現時点においては、その影響が消失していることは明白である。
(オ) 賃料を低額にする賃貸人の事情等の消失
本件各貸室は空室率が高い時期に締結される等当時の賃貸人の特殊な事情により締結されたものと想定することができるとしても、現時点における空室率は5%未満(甲28)と大幅に改善される等により、賃料を低額にする特殊な事情や動機は消失した。
ウ 相当賃料
被告らが実施するサブリース事業等は、サブリース事業等として応分のリスクを負担するものではなく、以下のとおり、極めて特殊なものであり、質的に管理業務と異なるところはない。被告らの適正な費用・収益は、PMフィー及び空室損失相当額に相当する月額賃料の84%を上回ることはない(甲10ないし13各16頁1-4.(4)必要経費欄参照)。したがって、本件では、1Kタイプで適正賃料が11万6000円ないし12万1000円とされていることから(甲10ないし13)、被告らの年間の適正費用・利益は、最大限その84%である9万7440円ないし10万1640円、月額にして8120円ないし8470円である。
(ア) 被告らの1か月又は2か月前の予告により何時でも解約が可能であり、相当の事業リスクは負担していないこと。
(イ) その態様においても、利用者とは1か月から数か月という短期間の賃貸借契約が締結されており、マンスリーマンションとして一般の賃貸借事業とは異なる態様で行われていること。
(ウ) 敷金・保証金・更新料等の負担はないこと。
(エ) 入居者には賃料保証会社の加入を義務づけ、定額の退去費用を負担させる等、賃料未回収その他のリスクを回避していること。
(オ) 本件建物一棟全部を対象としたサブリースではなく、本件建物の共用部分の保守管理は要せず、貸室に限った費用負担に限定され(その大部分は入居者負担である。)、さしたる費用も発生していないこと。
(被告らの主張)
ア 直近合意時点
本件各貸室の現行賃料の直近合意時点は、本件各貸室につき賃貸借契約の更新ないし賃料の変更合意がなされた日であり、本件貸室10は平成24年2月21日、本件貸室11は平成24年3月5日、本件貸室12は平成24年4月1日、本件貸室13ないし同16は平成24年4月30日、本件貸室17ないし24は平成24年5月27日、本件貸室1ないし7は平成25年10月31日、本件貸室8は同年11月17日、本件貸室9は同年12月16日である。
イ 現行賃料の不相当性
仮に、原告が前記(原告の主張)イ(ア)ないし(ウ)において主張する各価格等が上昇しているとしても、同上昇の事実をもって原告が請求する増額賃料の相当性が立証される訳ではない。
本件貸室10ないし24は、いずれも、本件死亡事故があった平成23年3月以前に賃貸借契約が締結されており、同契約締結に当たり、本件死亡事故は賃料額決定の要素となっていない。
本件貸室1ないし9は、本件各貸室のうち本件死亡事故より前に賃貸借契約が締結された本件貸室17ないし24と比較して、4000円が減額されたにとどまるのであり、同減額も、従前の賃貸借を踏まえた交渉の結果に過ぎないことからすれば、上記9室の賃貸借契約締結に当たり、事故物件の減額が行われていないことは明らかである。
ウ 相当賃料
転貸の収支は、事情変更とは無関係であり、相当賃料の算定に当たって考慮すべき事実ではない。そもそも、原告が基準とするところの適正費用・収益は、何をもって適正としているのかが不明であり、原告からは、そのような適正費用・収益を基に相当賃料を定める根拠も全く示されていない。 第3 当裁判所の判断
1 被告リブ・マックスの被告適格の有無(本案前の主張)(争点(1))
証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば、被告リブ・マックスは、平成26年7月1日、新設分割により被告リブマックスPMを設立し、同被告に対し、被告リブ・マックスが経営する事業のうち、サブリース事業及びウィークリー・マンスリーマンションの仕入事業に関する権利義務を被告リブマックスPMに承継させたこと、これにより、被告リブマックスPMは、原告と被告リブ・マックスとの間の本件各賃貸借契約に関する権利義務を承継したこと、その一方、被告リブ・マックスは、被告リブマックスPMが承継する一切の債務について、併存的に債務を引き受けたことが認められる。
被告リブ・マックスに対する本件訴えは、原告が、原告と被告リブ・マックスとの間における、本件各賃貸借契約に関する賃料額をめぐる権利義務の存否を確定する判決を求めるものであり、その法律関係は、原告と被告リブ・マックスとの間で決せられるべきものである上、上記のとおり、被告リブ・マックスは、被告リブマックスPMが承継する一切の債務について、併存的に債務を引き受けているのであるから、被告リブ・マックスに本件訴えの当事者適格がないとの被告らの主張は、採用することができない。
2 賃料増額請求が借地借家法32条1項の要件を充足するか否か(争点(2))
(1) 直近合意時点
直近合意時点とは、現実の合意がなされた時点を指すところ、証拠(甲2、22。枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、本件各貸室の現行賃料の直近合意時点は、本件貸室1ないし8は平成23年10月28日、本件貸室9は平成23年12月16日、本件貸室10は平成22年2月5日、本件貸室11は平成24年3月2日、本件貸室12は平成24年4月1日、本件貸室13ないし16は平成22年3月30日、本件貸室17ないし24は平成22年5月27日、本件貸室25ないし27は平成25年2月1日であると認められる。
被告らは、被告リブ・マックスが、ジョイント・プロパティとの間で、本件各物件の賃貸借契約を更新する際、賃貸条件を吟味した上でそのまま更新すべきかを検討している旨を指摘して更新時においても現実の合意がなされた旨を主張し、本件貸室11について取り交わされた契約変更合意書(甲2の11)及び本件貸室12について取り交わされた家賃等変更通知書(甲2の12)が、被告リブ・マックスとジョイント・プロパティとの間で、サブリースに供している本件各貸室の賃貸条件を検討して更新合意に至っていることを裏付けている旨指摘する。しかし、被告リブ・マックスとジョイント・プロパティとの間で、本件各貸室の賃貸期間満了に当たり、従前の契約条件と同一の条件で賃貸借契約を継続する旨合意したことを裏付ける確たる証拠が見当たらず、上記各書面によっても、各書面が対象とする貸室以外の貸室についての合意更新があると認めるには足りない。よって、直近合意時点に関する被告らの上記主張は採用できない。
(2) 現行賃料の不相当性
ア 原告は、直近合意時点から改定時期までに生じた変動事由(不動産価格、建設コスト及び周辺賃料の各上昇、本件死亡事故の影響及び賃料を低額にする賃貸人の事情等の各消失)を指摘し、また、本件各貸室の現行賃料と新規適正賃料や本件建物内にある本件各貸室以外の貸室の改定後賃料とも乖離しているとして、現行賃料が不相当になった旨主張するところ、証拠(甲16ないし21)及び弁論の全趣旨によれば、前記(1)において認定した本件各貸室に係る賃料の直近合意時点を基準とした場合、不動産価格、建設コスト及び周辺賃料の相場が、平成28年度においていずれも上昇していることが認められる。
イ しかし、不動産価格等の上昇についてみると、一般的に、上記価格等につき上昇傾向がみられることは、居室等の賃料額に影響を与え得る事由であるとはいえるものの、居室等の賃料額の増減に影響を与えうる事由は種々考えられるところであることに照らせば、上記相場の上昇傾向のみをもって、直近合意時点の賃料が増額請求時点までの間にいかなる影響を受けたかを具体的に把握することはできないというべきであるし、本件各貸室の現行賃料が、賃料増額請求時点において不相当となったとも認められない。
ウ また、本件死亡事故による影響についてみると、そもそも、本件貸室1ないし9の現行賃料を決定する際に、本件死亡事故の影響を踏まえて大幅な減額がなされたとまでは認められず、同事故の影響の消失を指摘して現行賃料が不相当になった旨をいう原告の主張は採用できない。
すなわち、本件貸室1ないし9の賃料額(いずれも8万6000円)について、20%以上の減額が見込まれたということは、元々の賃料額が10万7500円以上であったことを意味するが、上記各貸室に係る賃貸借契約締結当時、上記各貸室の賃料額がそうした水準にあったことを認めるに足りる証拠は見当たらず(なお、本件死亡事故直前において、類似の階層にあり、同一の貸室面積を持つ貸室(本件貸室17ないし24)につき合意された賃料額は9万円である。)、上記各貸室について20%以上の減額が見込まれたとは考えにくい。また、被告リブ・マックスは、本件死亡事故前である平成22年2月5日に1室(本件貸室10)を賃料11万5000円で、平成22年3月30日に4室(本件貸室13ないし16)を賃料11万円で、平成22年5月27日に8室(本件貸室17ないし24)を9万円で、それぞれジョイント・プロパティから賃借しているところ、上記のとおり、貸室の賃借数が増加し、しかも同一機会にまとまった数の貸室を賃借するごとに賃料が減額される傾向がみられることに照らすと、平成23年10月ないし同年12月までに契約された本件貸室1ないし9についての減額の影響が、貸室の賃借数の増加に伴うものである旨の被告らの主張を、むやみに排斥することはできないというべきである。
エ そして、本件各賃貸借契約が、空室率の高い時期に締結されたことなど、当時の賃貸人の特殊な事情により締結された旨をいう原告の同主張は、本件建物の空室率を含む賃貸人側の事情の変動を指摘するものにすぎず、経済事情の変動により現行賃料が不相当になったことを主張するものではないから、採用できない。
オ また、原告は、本件各貸室の現行賃料が、同貸室の新規適正賃料に比べて30%も乖離していること、また、本件建物内にある本件各貸室以外の貸室の改定後賃料とも乖離していることを指摘して、本件各貸室の現行賃料が、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった旨を主張し、本件各貸室の新規適正賃料を裏付ける証拠として、本件各貸室の調査報告書(甲10ないし14)を提出する。
しかし、各調査報告書は、いずれも平成28年7月31日時点の調査価格を示すにとどまり、直近合意時点以降における賃料を基準として、同賃料が不相当となったか否かの判断要素となる借地借家法32条1項所定の各要素に照らして算出された適正賃料を示すものではないばかりか、直近合意時点と賃料増額請求時点における、借地借家法32条1項所定の経済事情の変動や、これが本件各貸室の賃料に与えた影響、直近合意時点から賃料増額請求時点までの間における近傍同種の建物の借賃の増減、その増減を踏まえた本件各貸室の賃料との比較を示すものではないから、上記各調査報告書をもって、本件各貸室の現行賃料が不相当になったと認めることはできず、その他、本件各貸室の現行賃料が不相当になったことを認めるに足りる的確な証拠はない。
カ なお、原告は、相当賃料に係る主張において、被告らが実施するサブリース事業等が、応分のリスクを負担するものではなく、極めて特殊なものである旨を指摘するので、現行賃料の不相当性を認めるべき事情に当たるか否かについて念のため検討すると、証拠(甲2、22。枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、被告リブ・マックスが、ジョイント・プロパティとの間で、本件建物の一部の貸室を対象とした定額借上賃貸借契約(本件各賃貸借契約)を締結したこと、同契約において、被告リブ・マックスは、1か月前ないし2か月前の予告により同契約を解除できることや、被告は敷金・保証金・更新料を負担しないことなどが合意されたことが認められ、こうした契約内容等に照らせば、被告らが転貸事業を展開するに当たり一定のリスク軽減措置を組み込んだことは、本件各賃貸借契約締結時に前提とされ、各直近合意時点の賃料にもその旨が反映されていたというべきであるから、被告らの転貸事業が特殊であることを指摘して現行賃料が不相当になった旨をいう原告の主張は採用できない。
3 結論
よって、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 民事第37部 (裁判官 辻由起) 別紙(省略)
最高裁判所第一小法廷 平成25年(受)第1649号 平成26年09月25日
借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。
最高裁判所第二小法廷 平成18年(受)第192号 平成20年02月29日
1.賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約において、賃借人からの賃料減額請求の当否を判断するに際しては、同特約によって増額された賃料を基に、増額された日以降の経済事情の変動等を考慮するのではなく、同特約による改定前に当事者が現実に合意した賃料である賃貸借契約締結時の賃料を基にしなければならない。
2.強行法規たる借地借家法32条1項を根拠に、土地賃借人が賃貸人に対して請求した賃料減額の当否及び相当純賃料額は、直近の合意賃料、例えば賃貸借契約締結時の純賃料を基礎とし、かつ締結日から減額請求に至るまでの経済変動等の諸事情を考慮して決定されるべきであって、賃料自動改定特約の存在等は前記諸事情に含まれるにすぎないから、特約によって増額された純賃料をもとに、増額から減額請求までの間の事情のみに依拠した判断は許されない。
3.賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人からの賃料減額請求については、減額請求の直近合意賃料である賃貸借契約締結時の純賃料を基にして、同純賃料が合意された日から減額請求の日までの間の経済事情の変動等を考慮して判断すべきであって、自動増額特約によって増額された純賃料を基にして、増額前の経済事情の変動を考慮の対象から除外し、増額された日から減額請求の日までの間に限定して、その間の経済事情の変動等を考慮して判断することは許されない。
大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第2138号 平成20年04月30日
1 商業ビルの1フロアの建物賃貸借契約における賃料増額確認請求について,賃貸借契約を締結した時点から,借地借家法32条1項が規定する経済事情は,いずれも賃料を増額する方向に変動していなかったが,賃貸1 商業ビルの1フロアの建物賃貸借契約における賃料増額確認請求について,賃貸借契約を締結した時点から,借地借家法32条1項が規定する経済事情は,いずれも賃料を増額する方向に変動していなかったが,賃貸借契約当時に,賃貸人が賃借人の事情を配慮してほかのテナントの賃料よりも低額の賃料とし,賃貸人が3年後に賃料の増額を要請していたことを考慮して,賃貸人の同項に基づく賃料増額請求権を認めた事例
2 相当賃料額について,当事者双方から提出された私的鑑定,裁判所による鑑定の各内容の信用性を検討し,裁判所による鑑定の一部を修正して相当賃料額を認定した事例
1.商業ビルの1フロアの賃貸借契約における賃料増額請求について、借地借家法32条1項所定の経済事情の変動は認められないが、本件建物の現行賃料額は、賃貸人が賃借人の事情を考慮して、本件建物の他のテナントの賃料と比較して低額なものとし、契約の締結から3年後の賃料改定を要請していたことも認められるとして、賃貸人による賃料の増額請求が肯定された事例。
2.駅ターミナルに近接した商業ビル最上階全部を目的とする賃貸借契約につき、契約締結後に近隣の賃料相場が特に上昇したとはいえないとしても、賃貸人が賃借人の事情を配慮したうえで、当初の賃料をビル内の他のテナントに比して相当程度低額に設定していたなどの事実が認められる場合には、賃貸人は賃借人に対し、借地借家法32条1項に基づき、相当賃料額への増額を請求することができる。
3.商業用ビルの賃貸借契約においては、借地借家法32条1項にいう経済事情の変動等がなくても、賃料が他のテナントより低額であったこと等の契約当初の事情を考慮して賃料増額請求を認めるべきである。
主文
1 一審原告の控訴を棄却する。
2(1) 一審被告の控訴及び一審原告の当審における請求の拡張に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(2) 一審原告が一審被告に賃貸している原判決別紙物件目録記載の建物の賃料は、平成16年2月1日以降、月額77万8400円であることを確認する。
(3)一審被告は、一審原告に対し、953万5400円及びうち19万4600円については平成16年3月6日から、うち19万4600円については同年4月8日から、うち19万4600円については同年5月8日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月8日から、うち19万4600円については同年8月7日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月8日から、うち19万4600円については同年11月6日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については同17年1月8日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、うち19万4600円については同年4月8日から、うち19万4600円については同年5月7日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月8日から、うち19万4600円については同年8月6日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月8日から、うち19万4600円については同年11月8日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については同18年1月7日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、うち19万4600円については同年4月8日から、うち19万4600円については同年5月3日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月8日から、うち19万4600円については同年8月8日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月7日から、うち19万4600円については同年11月8日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については同19年1月6日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、うち19万4600円については同年4月7日から、うち19万4600円については同年5月8日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月7日から、うち19万4600円については同年8月8日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月6日から、うち19万4600円については同年11月8日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については平成20年1月8日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、各支払済みまで各年1割の割合による各金員を支払え。
(4) 一審原告のその余の請求(当審で拡張した請求を含む。)を棄却する。
3 訴訟費用は、1、2審を通じてこれを5分し、その2を一審原告の、その余は一審被告の負担とする。 事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 一審原告
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 一審原告が一審被告に賃貸している原判決別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の賃料は、平成16年2月1日以降、月額116万7600円であることを確認する。
(3) 一審被告は、一審原告に対し、2860万6200円及びうち58万3800円については平成16年3月6日から、うち58万3800円については同年4月8日から、うち58万3800円については同年5月8日から、うち58万3800円については同年6月8日から、うち58万3800円については同年7月8日から、うち58万3800円については同年8月7日から、うち58万3800円については同年9月8日から、うち58万3800円については同年10月8日から、うち58万3800円については同年11月6日から、うち58万3800円については同年12月8日から、うち58万3800円については同17年1月8日から、うち58万3800円については同年2月8日から、うち58万3800円については同年3月8日から、うち58万3800円については同年4月8日から、うち58万3800円については同年5月7日から、うち58万3800円については同年6月8日から、うち58万3800円については同年7月8日から、うち58万3800円については同年8月6日から、うち58万3800円については同年9月8日から、うち58万3800円については同年10月8日から、うち58万3800円については同年11月8日から、うち58万3800円については同年12月8日から、うち58万3800円については同18年1月7日から、うち58万3800円については同年2月8日から、うち58万3800円については同年3月8日から、うち58万3800円については同年4月8日から、うち58万3800円については同年5月3日から、うち58万3800円については同年6月8日から、うち58万3800円については同年7月8日から、うち58万3800円については同年8月8日から、うち58万3800円については同年9月8日から、うち58万3800円については同年10月7日から、うち58万3800円については同年11月8日から、うち58万3800円については同年12月8日から、うち58万3800円については同19年1月6日から、うち58万3800円については同年2月8日から、うち58万3800円については同年3月8日から、うち58万3800円については同年4月7日から、うち58万3800円については同年5月2日から、うち58万3800円については同年6月7日から、うち58万3800円については同年7月6日から、うち58万3800円については同年8月7日から、うち58万3800円については同年9月7日から、うち58万3800円については同年10月5日から、うち58万3800円については同年11月7日から、うち58万3800円については同年12月7日から、うち58万3800円については平成20年1月7日から、うち58万3800円については同年2月7日から、うち58万3800円については同年3月7日から、各支払済みまで各年1割の割合による各金員を支払え。
2 一審被告
(1) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
(2) 同取消しに係る一審原告の請求を棄却する。
第2 事案の概要 1 事案の骨子及び訴訟経過
本件は、一審原告が、大阪市A区〈中略〉171番地1・171番地3所在の鉄骨鉄筋コンクリート造地下3階・地上9階建て、延床面積5399.04m2の「ジュピタービル」という名称のビル(以下「本件ビル」という。)のうちの9階部分である本件建物を、平成12年11月に賃料月額58万3800円で一審被告に賃貸したところ、一審被告に対し、賃料増額改訂の特約又は借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求により増額された平成16年2月1日以降の相当賃料額の確認を求めるとともに、既に支払われた賃料と相当賃料額との差額及びこれに対する支払期後から支払済みまで同条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求めた事案である。
原審は、賃料増額改訂の特約を認めるに足りる証拠はないが、本件建物の賃料は経済事情の変動等により不相当になったといえるから、一審原告は、借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求権を有するところ、本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額は月額89万2000円であるとして、一審原告の請求のうち、本件建物の平成16年2月1日以降の賃料を月額89万2000円と確認し、これと既に支払われた賃料との差額及びこれに対する支払済みまで同条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求める限度で認容し、その余を棄却した。
そのため、一審原告及び一審被告の双方が本件各控訴を提起した。
2 前提となる事実
次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の1のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決4頁23行目から同24行目にかけての「別紙物件目録記載の物件」を「本件建物(契約面積321.09m2、97.3坪)」と改める。
(2) 原判決5頁6行目の「原告において」を「一審原告と一審被告の協議の上」と改め、同7行目の「5条」の次に「、特約事項」を加える。
(3) 原判決5頁12行目から同16行目までを次のとおり改める。
「 本件賃貸借契約においては、経費の分担として、一審被告が、共同管理費として月額68万1100円(1坪当たり7000円)を負担する(本件契約書11条1項)ほか、経常販促費として月額9万7300円(1坪当たり1000円)を負担することになっており、一審被告が、一審原告及び本件ビルの全入店者をもって構成するテナント会に入会することが定められている(本件契約書27条)。(乙1、3)」
(4) 原判決5頁25行目の「同16年」から6頁初行の「乙2)」までを「平成16年2月1日以降の本件建物の賃料を月額116万7600円に増額する旨の意思表示をした(甲4、乙2、以下「本件増額請求」という。)が」と改める。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 賃料増額改訂の特約の有無
ア 一審原告の主張
原判決6頁9行目から同11行目までのとおりであるから、これを引用する。
イ 一審被告の主張
原判決6頁13行目から同15行目までのとおりであるから、これを引用する。
(2) 共同管理費の大部分が賃料に該当するか否か
ア 一審被告の主張
原判決7頁8行目末尾に改行の上、次のとおり加えるほかは原判決6頁19行目から7頁8行目までのとおりであるから、これを引用する。
「 共同管理費は、本件賃貸借契約を締結してから現在まで月額68万1100円の定額のままであり、実費の精算を求められたり、余剰金の返還を受けたこともなく、テナント会においての決議は、各テナントが共同管理費の使途内訳について関心がないため、形骸化している。そのため、本件建物の共同管理費は、管理業務の実費とはいえず、使用収益の対価と見るべきである。」
イ 一審原告の主張
原判決7頁10行目から同25行目までのとおりであるから、これを引用する。
(3) 借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求の当否
ア 一審原告の主張
借地借家法32条1項の要件の充足を検討するに際しては、賃貸借契約が締結されるに至った経緯も考慮される。
一審原告は、従来から、仲介業者等に対して、入店に際して一審原告が希望する条件をパンフレット(甲15)で示しており、入店希望者は、仲介業者からその情報を入手して、入店希望を申し入れ、交渉の上で賃料等の金額を決定することになっており、一審被告としても、当然、本件ビルの他のテナントの賃料相場を認識していたといえるところ、本件賃貸借契約を締結するに際して、一審被告から、仲介業者の株式会社アルファ(以下「アルファ社」という。)を介して、賃料を共益費込みで1坪当たり1万3000円としてほしいとの要望がなされた。一審原告としては、本件ビルの他のテナントの共同管理費が1坪当たり7000円であり、一審被告の要望では賃料が共同管理費を下回ることになるため、当初、一審被告の要望を拒否していた。しかしながら、その後も、アルファ社を介して一審被告から入店への意欲が示された。そのため、一審原告は、一審被告が本件ビルの近辺にある大型複合商業ビルである「サターンビル」において店舗を構えていたところ、この店舗が経営不振に陥り、本件建物へ移転することになり、移転に関する費用が必要になることや、本件建物での営業も同様に経営不振になるかもしれないという将来性に対する危惧等から、営業基盤が確立されるまでの3年間は、破格の賃料を要求しているという一審被告の事情を考慮して、3年間という暫定的な期間であれば、一審被告の要望を受け入れることにした。
そして、一審原告は、一審被告に対して、3年後には適正な賃料に改定することを要請し、本件契約書の調印の際にも、一審原告の代表者自らが一審被告に再確認をしているし、アルファ社からも、本件建物の当初賃料額が一審被告の事情を特別に配慮したものであることや3年後の賃料改定のことを記載した報告書(甲13)が提出されたのである。
このように、一審被告の事情を考慮して特別に当初の3年間という期間限定で破格の条件で賃料を定めたことは明らかであるから(社会通念上、商業施設の貸主が、このような破格の条件での賃料が長期間継続されることを前提とする契約を締結するはずはない。)、本件増額請求は、借地借家法32条1項の要件を充足している。
イ 一審被告の主張
本件賃貸借契約の締結から平成16年2月までの3年間で、借地借家法32条1項が規定する土地若しくは建物に対する租税その他の負担が増加したという事情もなければ、土地若しくは建物の価格の上昇といった経済的事情の変動もない。また、同項が規定する「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」とは、相当期間適時適正な賃料改定が行われてこなかったために近傍同種の建物の賃料と比較して不相当となったような場合を予定しているところ、本件賃貸借契約の締結からわずか3年しか経過しておらず、かつ、その3年間で周辺のテナントビルの賃料相場が急激に上昇したといった事情もないから、本件建物の賃料が「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」にも当たらない。
また、一審被告は、本件賃貸借契約の締結に至る条件交渉において、本件ビルの他のテナントの賃料等について何ら説明を受けておらず、甲15のパンフレットも含めて入店条件等の記載された資料も一切受け取っていない。一審被告は、「サターンビル」において営業していたフランチャイズ店が独立することになったため、直営店をA近辺で出店するべく適当な物件を探しており、この店舗の賃料が共益費込みで月額1坪当たり1万3000円であったことから、アルファ社を介して、一審原告に賃料希望額を提示したにすぎず、「サターンビル」の店舗が営業不振であったという事実もないし、営業基盤が確立する3年間は破格の賃料を希望したという事実もない。
そもそも、上記(2)の一審被告の主張のとおり本件賃貸借契約における実質的な賃料は、本件契約書上の賃料と共同管理費を併せたものであり、この実質的な賃料は、当時の賃料相場からみても相当なものであった。
しかも、一審被告は、賃貸借契約書案の5条(賃料等の変更)の条項が「甲において変更することができる」となっているのを、特約条項として「甲乙協議の上」に変更してほしいと要請し、これを一審原告が了承して本件契約書の特約条項になっているのであるから、これに反する特段の合意など存在しない。
したがって、本件増額請求は、借地借家法32条1項の要件を充足しない。
(4) 相当賃料額
ア 一審原告の主張
次のとおり補正するほかは、原判決8頁2行目から同23行目までのとおりであるから、これを引用する。
(ア) 原判決8頁2行目から同3行目までを次のとおり改める。
「 本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額は、月額116万7600円であり、これは、不動産鑑定士乙山二郎の鑑定評価書(甲3、以下「乙山鑑定」という。)により裏付けられる。」
(イ) 原判決8頁4行目の「鑑定」から同5行目の「〔以下「一審被告側鑑定」という。〕)」までを「不動産鑑定士丙川三郎の鑑定評価書(乙5、以下「丙川鑑定」という。)」と改める。
(ウ) 原判決8頁23行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「 鑑定人甲野一郎の鑑定書(以下「甲野鑑定」という。)は、〈1〉差額配分法による賃料を算定する際に、折半法を採用していること、〈2〉スライド法を適用すべきではないのにそれを適用し、スライド指数を本件ビルの周辺地域の商業ビルの賃料動向ではなく、大阪市消費者物価指数の総合とB・A地区の事務所賃料の推移の加重平均としていること、〈3〉利回り法の継続賃料利回りを0.53%と極めて低い数値にしていること、〈4〉賃貸事例比較法を適用していないことなどから不当であり、採用できない。」
イ 一審被告の主張
次のとおり補正するほかは、原判決8頁25行目から9頁10行目までのとおりであるから、これを引用する。
(ア) 原判決中「原告側鑑定」をすべて「乙山鑑定」と改める。
(イ) 原判決9頁10行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「 甲野鑑定は、〈1〉差額配分法、スライド法及び利回り法による各試算賃料を8対1対1と配分して賃料額を算定しているが、この配分比には根拠がないこと、〈2〉鑑定による賃料額に共同管理費を加算した結果が、TKC経営指標による平均賃料比率のやや上方に位置するとして、鑑定の妥当性を根拠付けようとしているが、鑑定に当たっては、共同管理費を賃料に含めておらず自己矛盾を来していること、〈3〉鑑定による賃料額に共同管理費を含めた賃料の1坪当たりの単価が、鑑定評価書中の「試算賃料算出表1」のB、D、Eの賃貸事例のそれと比較して違和感がないとしているが、これらの賃貸事例は、本件賃貸借契約と類似しておらず、不当であることなどから、採用できない。」 第3 当裁判所の判断
1 本件賃貸借契約の締結に至る経緯等
前提となる事実、証拠(甲2ないし6、10ないし16、乙1ないし5、鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 本件ビルは、2棟からなる登記簿上一棟の建物のうち西側に位置する建物(家屋番号 〈住所略〉171番1の4)であり、昭和63年11月に新築された鉄骨鉄筋コンクリート造地下3階付9階建ての飲食ビル(ただし、地下3階は、一部倉庫として賃貸に供されている部分もあるが、基本的には機械室・搬入路等の共用スペースである。)である。
本件ビルは、A1駅の外、B1駅、B2駅、B3駅が集積する駅ターミナルに近接しており、太陽百貨店等の大型複合商業ビルが建ち並ぶ高度商業地域に位置しており、3階部分で南側に隣接する太陽百貨店の遊歩道と、地下2階部分で地下街(駅等の連絡通路)とそれぞれ連結しているとともに、地下3階部分においても、唯一の搬入路として太陽百貨店側の車両搬入路と連結しており、その使用料を一審原告が支払っている。また、一棟建物(全体ビル)である二棟間では、2階、地下1階、地下2階で連結している。
本件建物は、本件ビルの最上階である9階に位置し、天井高が約5mとほかの階(約3.6m)に比べて相当高くなっている。
(2) 一審原告が昭和62年に本件ビルの賃借希望者向けに作成したパンフレット(甲15)には、出店の条件として〈1〉店舗内装工事は入店者の負担とする、〈2〉経常販促費として売上高の1%を負担する、〈3〉9階の保証金を1坪当たり170万円、固定家賃を1坪当たり2万円とする、〈4〉共同管理費として、共同部分・施設に要する費用で空調冷暖房・水道・光熱・給排水・衛生処理・保安設備・清掃・昇降機・植栽管理・屋外照明等々の費用の実費を契約面積につき負担するなどと記載されている。
(3) 一審被告は、平成12年7月ころ、仲介業者であるアルファ社を介して、一審原告に対して、一審被告の会社概要、印鑑証明書及び登記簿謄本をファクシミリで送信するなどして本件建物への入店を希望した。
一審被告は、本件ビルの近辺にある「サターンビル」という名称の大型複合商業ビル内に店舗を構えており、そこから本件建物に移転することを企図していたが、「サターンビル」での店舗の賃料が共益費込みで月額1坪当たり1万3000円であったため、アルファ社を介して、一審原告に対して、本件建物の賃料の希望額として共益費込みで月額1坪当たり1万3000円を提示した。
一審原告としては、当時、本件ビルの他のテナントから共同管理費として月額1坪当たり7000円を徴収しており、一審被告に対する共同管理費も同じ金額になるため、一審被告の希望額では賃料が月額1坪当たり6000円となり、当時の他のテナントの賃料(契約日、面積、保証金額等はそれぞれ異なるものの月額1坪当たり1万円ないし5万円程度)と比較しても相当低額になるため、一審被告の希望賃料額を拒否していたが、一審被告には、他のテナントの賃料や保証金額等の賃貸条件の情報を開示しなかった。
その後も、一審被告は、アルファ社を介して入店を希望し、一審原告と賃料額等について交渉をしたが、最終的には、一審原告は、本件ビルの近辺の大型複合商業ビルから移転することで、本件建物での営業が軌道に乗るまでに費用や時間を要することなど一審被告の抱える諸事情を配慮し、3年後に賃料を他のテナントの賃料水準程度に増額してもらえばよいであろうという見込みのもとで、一審被告の賃料希望額に応じることにした。
他方、一審被告としては、一審原告に提示していた賃料希望額が、本件ビルの近辺の大型複合商業ビルの共益費込みの1坪当たりの賃料と同額であったこと、アルファ社から、賃料と共同管理費はテナント会や経理上の都合で便宜的に区分したものであると報告を受けていたこと、本件ビルの他のテナントの賃料相場を知らなかったことから、他のテナントと比較して特に低額な賃料に応じてもらったという認識を持っていなかった。
(4) 一審原告は、平成12年10月ころ、アルファ社を介して一審原告に契約書案を送付した。この契約書案の5条には「賃料等は、原則として3年毎に経済情勢等の変動に応じ、甲(一審原告)において変更することができる。」との規定が、9条には、「甲が経済情勢の変動その他に鑑み必要と認めて出店保証金の増額を請求した場合(中略)不足の場合は乙は1ケ月以内にこれを補充する。」との規定が、13条4項には、「乙はその責任において従業員を派遣し、(中略)甲の要求があったときは直ちに従業員を変更する」との規定があり、ほかに、6条として「乙は店舗における売上総額をすべてレジスターに登録し、登録後の売上現金を毎日甲に引き渡すものとする」との規定があった。一審被告は、これらの規定につき、アルファ社を介して、5条、9条、13条4項については、いずれも一審原告と一審被告の協議の上、変更できるものとする、一審被告が売上総額をすべてレジスターに登録し、売上金内訳票と売上レシートを毎日一審原告に提出し、登録後の売上現金は一審被告が保管し、翌月7日までに賃料及び共同管理費等を一審原告指定の銀行口座に振り込むなどという内容に変更するよう要請したところ、一審原告は、これらの変更に応じた。
また、一審原告は、アルファ社を介して、一審被告に対して3年後に賃料を改定することを要請していたが、アルファ社は、一審原告に対し、同年11月24日付けの報告書(甲13)によって、一審被告の代表取締役及び専務取締役と面談して得た感触としては、一審被告としては、3年後について予測をすることは困難であり、移転に伴う問題や店舗の立ち上げ等数多くの乗り越えなければならない問題があり、3年後に賃料の改定の申出があった場合には、その時点での運営状況及び近隣の経済情勢を鑑み信頼関係を前提に一審原告と協議して紳士的に決定させていただきたいという意向である旨報告した。
そして、一審原告と一審被告は、同年11月29日、特約事項として「本契約第5条(賃料等の変更)、本契約第9条(出店保証金額の変更)、本契約第13条(乙の義務)第〈4〉項「従業員の変更」は甲・乙協議の上変更できるものとする」と付加した本件契約書(乙1)を作成し、同年10月30日付けで上記の一審被告の変更案を入れた覚書(甲2)を作成したが、3年後に賃料を増額する旨を合意した文書は何ら作成されていない。
(5) 一審原告は、平成15年11月20日ころ、一審被告に対し、本件契約書の5条に基づき、本件増額請求をした。
本件賃貸借契約が締結された平成12年11月から平成16年2月までの間、地価は下落傾向であり、本件建物やその敷地の公租公課が増額したということはなく、本件ビルの他のテナントの賃料や周辺の賃料相場が特に上昇したということもない。また、一審被告の売上額は、平成12年12月から平成13年3月までは月平均の*万円程度であったが、毎年次第に減少し、平成15年4月から平成16年3月までは月平均*万円程度になっていた。
2 争点(1)(賃料増額改訂の特約の有無)について
一審原告は、一審被告の経営事情等を配慮して営業基盤が確立するまでの当初の3年間に限って破格の条件での賃料にしたので、一審被告との間で3年後に賃料を増額することを合意した旨主張する。
確かに、上記1認定事実によれば、本件建物の賃料額は、当時の本件ビルの他のテナントの賃料に比べて相当低額であり、一審原告が、一審被告の経営事情等に配慮してその希望額に応じたという経緯ではあるものの、他方、一審被告としては、一審原告から本件ビルの他のテナントの賃料額について知らされていなかったため、それについての認識を持っておらず(なお、一審被告が出店条件を記載したパンフレット(甲15)を受け取ったことを認めるに足りる証拠はなく、仮に受け取ったとしてもこのパンフレットが昭和62年当時のものであって、それに記載された出店条件が平成12年当時に当てはまるとは考え難いことから、このパンフレットによって一審被告が、当時の本件ビルの他のテナントの賃料相場を認識していたと認めることはできない。)、本件ビルの周辺にある大型複合商業ビル内の店舗の共益費込みの賃料額が月額1坪当たり1万3000円であったことから、本件建物の賃料が他のテナントと比較して相当低額であるとは認識していなかったことが認められる。
このように一審原告と一審被告との間には本件建物の適正賃料額についての認識がそもそも一致していなかったといわざるを得ず、このことは、契約書案の5条が「賃料等は、原則として3年毎に経済情勢等の変動に応じ、甲において変更することができる。」と貸主に賃料等の変更請求権があるという有利な条項となっていたところ、一審被告の要望により、特約事項として、当該条項を「一審原告と一審被告の協議の上変更できるものとする」と改められたことやその他の契約条項についても一審被告の希望に従って変更がされていることに表れているといえる。
また、アルファ社の報告書(甲13)の文面も、一審被告が、3年後に一審原告から賃料改定の申出があった場合、その時点での運営状況及び近隣の経済情勢を考慮して協議の上決定していくという意向が記載されているにとどまり、3年後に増額することを約束したという文面にはなっていない。
以上によれば、一審原告と一審被告との間で本件建物の賃料を3年後に増額する旨の合意があったことを認めることはできない。
3 争点(2)(共同管理費の大部分が賃料に該当するか否か)について
一審被告は、本件建物の共同管理費の大部分が賃料である旨主張する。
確かに、上記1認定のとおり、一審被告は、本件建物の賃料額を決定するに当たり、共同管理費を含めた金額を実質的な賃料として交渉をしており、仲介業者であるアルファ社から、賃料と共同管理費に区分されるのは、テナント会や経理上の都合による便宜的なものであると説明されている。また、証拠(甲3、乙3、5)及び弁論の全趣旨によれば、本件建物の共同管理費は、丙川鑑定(乙5)が参考資料として大阪市内の店舗の賃貸事例として掲げている共益費と管理費の合計額と比較してかなり高額であり、本件賃貸借契約を締結してから月額1坪当たり7000円と定額で推移し、実費精算がされたことがなかったことが認められる。
しかしながら、証拠(甲3、乙1、3、5、鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば、〈1〉本件契約書上は、賃料は月額58万3800円と明確に定められ、共同管理費と区別されていること、〈2〉共同管理費は、警備費用(人員警備及び機械警備)、設備管理費用(設備管理費用、エレベーター管理費用、電気設備保守料、消防設備点検料、空気環境測定料及び水質検査料)、清掃費用(全館共用部分の日常清掃、定期清掃、塵芥処理費用、貯水槽清掃費用、防虫防鼠作業料、共用雑排水通管清浄)、特別修繕費等に使用されており、その明細や領収証は明らかにされていないものの、毎年、一審原告から、一審被告を含むテナント会に対して、管理業務予算案が示されて決議され、その実績が報告されて承認を受けていること、〈3〉本件ビルは、4階に一審原告の事務室やイベントホールがある以外はすべて飲食店業者が入居し、出店しているすべての店舗がテナント会を構成して、共同管理費の予算の決議や決算の承認を行うことになっているのに対し、丙川鑑定が参考資料として掲げる大阪市内の店舗の賃貸事例がこのようなビル全体が商業施設である賃貸借であるのかどうか不明である上、甲野鑑定が参考資料として掲げる大規模複合商業ビルの共益費が月額1坪当たり6100円ないし1万円であって本件建物の共同管理費と差異がないことが認められ、これらの事実によれば、本件建物の共同管理費の大部分が実質的な賃料であると認めることはできない。
4 争点(3)(借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求の当否)について
借地借家法32条1項は、土地又は建物の賃貸借契約が長期間に及ぶことが多いため、事情の変更に応じて不相当になった賃料を調整し、当事者の衡平を図ることを目的としたものであるから、同項に基づく賃料増額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が現実に合意した賃料のうち直近のものを基にして、それ以降の同項所定の経済事情の変動等のほか、賃貸借契約の締結経緯、賃料額決定の要素とした事情等の諸般の事情を総合的に考慮すべきである。
上記1認定事実によれば、本件賃貸借契約が締結された平成12年11月から本件増額請求において賃料改定時とされた平成16年2月までの約3年間で、同項所定の土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増加、土地若しくは建物の価格の上昇といった経済的事情の変動もなければ、本件ビルの他のテナントの賃料や周辺の賃料相場が特に上昇したという事情も認められない。
しかしながら、上記1認定事実によれば、本件建物の現行賃料額は、本件ビルの他のテナントの賃料と比較して相当低額であり、このような低額になったのは、一審被告が本件ビルの近辺のビルの店舗から本件建物に移転することから、本件建物での営業が軌道に乗るまでに費用や時間等を要するという諸事情を一審原告が配慮したためであり、一審被告としても、本件ビルの他のテナントの賃料相場についての認識はなかったとはいえ、一審原告が当初は一審被告の希望する賃料額を拒否していたが、その後の交渉によって希望どおりの条件で賃料額が決定したことや一審原告が3年後の賃料改定を要請していたことなどから、本件建物の現行賃料額が本件ビルの他のテナントの賃料と比較して低額であり、一審原告が一審被告が当時抱えていた諸事情を配慮してその希望額に応じたことを認識できたと認められる。
このような現行賃料額決定の経緯等を考慮すると、本件増額請求は、借地借家法32条1項の要件を充足すると認めるのが相当である。
もっとも、相当賃料額を判断するに際しては、現行賃料が合意されてから賃料を増額する要因となる経済事情の変動がないことや一審原告と一審被告との間では、本件建物の適正賃料額についての認識が一致しておらず、そのため、3年後の賃料改定の際に、本件ビルの他のテナントの賃料水準にするという一致した認識もなかったとことを十分考慮する必要がある。
5 争点(4)(相当賃料額)について
(1) 乙山鑑定について
一審原告は、本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額を月額116万7600円(1坪当たり1万2000円)と主張する。
そして、乙山鑑定(甲3)は、本件建物の平成16年2月1日以降の本件建物の適正賃料額について、差額配分法によると月額137万1000円、賃貸事例比較法によると月額145万9000円、中小企業庁編の経営指標の小売飲食店の売上高に占める支払家賃比率が7%であり、一審被告の平成16年4月から平成17年3月までの平均売上額にこの家賃比率を乗じた額が148万円になるとして、これらの配分比を差額配分法を9、賃貸事例比較法を0.5、売上に占める家賃比率による賃料を0.5として、月額138万1000円と評価している。
しかしながら、乙山鑑定は、差額配分法における差額配分比を、居住用借家の継続賃料と異なり商業施設での継続賃料の場合は、貸主に帰属する割合を70%とする3分の1法が適用され、一審原告が平成15年度にテナントの売上向上のためにイベントを開催するなどして2600万円を支出していることから80%としているが、一審被告の負担する共同管理費が年間817万3200円に上り、借主である一審被告も本件ビル全体の維持管理費用として相当な負担をしていることを考慮すれば、差額配分比を3分の1法や80%とすることは、衡平を欠くといえる。
また、証拠(甲3、5、6、9)によれば、乙山鑑定は、一審原告と一審被告との間で、本件建物においての一審被告の当初の売上予測がつかないことなどから、本件ビルの他のテナントの賃料と比較して特別に低廉な賃料にする代わりに、3年後の賃料改定時期には、本件ビルの他のテナントの賃料水準にする旨の合意をしたことを前提とするものであり、そのため、本件ビルの他のテナントで本件建物と同規模の広さで営業時間等も類似した賃貸事例を収集して賃貸事例比較法を採用していることが認められるが、上記2、4認定説示のとおり、一審原告と一審被告との間では、賃料増額の合意の事実が認められないばかりか、3年後の賃料改定の際に他のテナントの賃料水準にするという認識も一致しておらず、しかも、一審被告は、本件ビルの他のテナントの賃料相場を知らなかったのであるから、本件建物の継続相当賃料額を算定するに当たって賃貸事例比較法を直接的に採用すると、上記のような本件賃貸借契約の個別事情を反映せず、一審被告にとって不測の事態を招くことになって当事者間の衡平を欠く結果になる。そのため、賃貸事例比較法を直接的に採用することはできない。
さらに、中小企業庁編の経営指標の小売飲食店の売上高に占める支払家賃比率を適用して一審被告の売上額から賃料を算定している点については、現行賃料額を決定するに当たって、このような算定方法を用いたのではないし、上記1認定事実によれば、一審被告としては、本件建物での営業をするに当たって、共同管理費も含めた金額によって採算を検討したものと推測できるから、一審被告の売上高に支払賃料比率を乗じて賃料額を算定するという手法を採用することはできない。
以上のように、本件にあっては賃料増額事由の中核となるべき経済・社会的要因に基本的な変化が生じていないのに、乙山鑑定が、差額配分法、賃貸事例比較法を採用し、支払家賃比率を参考に両試算賃料の開差を調整する手法を採用し、一方、現行賃料の合意後の経済・社会的要因をもっとも如実に反映するスライド法を考慮しなかったのは、契約当事者間に、賃借人の意向を容れて現行賃料が他のテナントよりも著しく低く設定され、本件増額請求時には賃料を他のテナントの水準まで引き上げるという合意がなされたことを前提としており、当裁判所がその前提をそのまま採用できないことは記述のとおりであるから、現行賃料の合意時から本件増額請求時までの経済・社会的要因の推移を捨象し、現行賃料の倍額を超える賃料をもって適正賃料とする乙山鑑定を採用することはできない。
(2) 丙川鑑定について
丙川鑑定(乙5)は、本件建物の平成16年2月1日以降の適正賃料額について、差額配分法によると月額88万5000円、スライド法によると月額54万9000円になるとし、スライド法を重視して月額61万6000円と評価している。しかしながら、丙川鑑定がスライド法を重視したのは、差額配分法による経済賃料と現行賃料との差額には共同管理費のうちの実質賃料部分が反映されていないという認識に基づくものであると認められるところ、上記3認定説示のとおり、本件建物の共同管理費の大部分が賃料であるとは認められないから、この点を理由にスライド法による試算賃料に偏した調整をなした丙川鑑定を採用することはできない。
(3) 甲野鑑定について
ア 甲野鑑定は、本件建物の平成16年2月1日時点での適正賃料額について、差額配分法によると月額97万3479円、スライド法によると月額54万6437円、利回り法によると月額58万3047円になり、賃貸事例比較法については直接的に適用ができないとした上で、各評価方式による各試算額を8対1対1の割合として、月額89万2000円と評価している。
イ 甲野鑑定が賃貸事例比較法を直接的に適用していない点については、上記(1)に認定説示した諸事情に照らして合理性があるといえる。
甲野鑑定の差額配分法による賃料の試算過程は、特に不合理な点はなく、差額配分比につき折半法を採用している点も、上記のとおり、借主である一審被告も本件ビル全体の維持管理費用を相当負担していることを考慮すれば、衡平の原則に適うものといえる。
また、甲野鑑定は、スライド指数について、大阪市の消費者物価総合指数と株式会社ベータ調査によるB・A地区の事務所の平均実質賃料推移統計を1対2の割合で加重平均して求めている。
この点、一審原告は、これらの統計数値は、本件建物のような高度商業地に存在する百貨店に隣接した大店舗等に関する統計数値でないので、これらによって変動率を求めるのは不当であり、そもそも本件建物のような高度商業地にある商業施設の継続賃料についてスライド法を適用することは不合理である旨主張する。確かに、スライド法における変動率は、現行賃料を定めた時点から賃料改定時点までの間における経済情勢等の変化に即応する変動分を表すものであり、変動率を求める場合の各種指数は、対象不動産の地域性、用途等の特性を反映したものである必要はあるが、他方で、それを過度に要求すると用いるべき統計資料が存在しないことになる。スライド法は、現行賃料を合意した時点以降の経済状況を反映させて継続賃料を算定するものであり、上記4認定説示のとおり、本件増額請求による相当賃料額を判断するに当たっては、現行賃料が合意されてから賃料を増額する要因となる経済事情の変動がないことを十分考慮する必要があり、これからするとスライド法を適用する合理性は否定できないところ、甲野鑑定で用いた統計数値は、可能な限り本件建物の特性を反映したものといえ、ほかに、甲野鑑定のスライド法による賃料試算過程に不合理な点はない。
ところで、甲野鑑定は、利回り法について、継続賃料利回りを本件賃貸借契約締結当時の本件建物の基礎価額に対する純賃料の割合として0.53%としているところ、一審原告は、商業施設の継続賃料利回りとして極めて低く、不合理である旨主張している。
確かに、継続賃料利回りが0.53%というのは、商業施設の利回りとしては考え難く、これは、現行賃料額が本件建物の経済価値を反映しない低水準の賃料額であったことに起因するものであり、スライド法によって本件賃貸借契約の個別事情を反映することができることを考慮すると、継続賃料利回りを本件賃貸借契約締結当時の本件建物の基礎価額に対する純賃料の割合のみによって算定することには疑問がある。不動産鑑定評価基準においても、継続賃料利回りは、現行賃料を定めた時点における基礎価格に対する純賃料の割合を標準とし、契約締結時及びその後の各賃料改訂時の利回り、基礎価格の変動の程度、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における対象不動産と類似の不動産の賃貸借等の事例又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借等の事例における利回りを総合的に比較考量して求めるものとされているから、本件ビルの他のテナントの賃貸事例や高度商業地の賃貸事例の利回りを考慮する必要性があり、その意味で甲野鑑定の継続賃料利回りは採用できない。そして、高度商業地域の賃貸事例の利回りが6%程度であること(甲9)に加えて本件賃貸借契約締結時点からの本件建物の基礎価格が25%程度減価していること(鑑定の結果)を総合考慮すると、継続賃料利回りを2%と認めるのが相当であり、これによって試算すると、月額79万2692円になる。
ウ 甲野鑑定は、差額配分法、スライド法、利回り法の比率を8対1対1の割合で加重平均して本件建物の平成16年2月1日時点の賃料額を評価しているが、その理由として述べるところは、現行の賃料額が適正でないということに集約される。
確かに、本件建物の現行賃料額は、当時の本件ビルの他のテナントと比較しても相当低い水準であり、現に差額配分法による本件建物の試算額や現行賃料を定めた時点における基礎価格に対する純賃料の割合が0.53%であることなどを考慮しても、現行賃料額が本件建物の経済価値を反映した賃料水準を下回るものであったことは否定できない。
しかしながら、借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求においての相当賃料額を判断するに当たっては、直近合意賃料を基にして、それ以降の同項所定の経済事情の変動等のほか、賃貸借契約の締結経緯、賃料額決定の要素とした事情等の諸般の事情を総合的に考慮すべきであるところ、現行賃料を合意する際、一審被告には本件ビルの他のテナントの賃料相場の認識がなく、一審原告と一審被告との間に3年後に他のテナントの賃料水準に改訂するという認識が一致していたわけではなかったこと、現行賃料を合意した後に賃料の増額要因となるような経済事情の変動がないことを総合考慮すると、現行の賃料額が本件建物の経済価値を反映した賃料水準を下回るという理由で、差額配分法を重視するということは相当ではなく、本件建物の経済価値を反映した賃料水準にするのは、今後の経済情勢の変動を踏まえて、段階的に行われるべきものと解される。
差額配分法、スライド法、利回り法は、継続賃料を算定するに当たってそれぞれ長所と短所を有するところ、本件増額請求による本件建物の相当賃料額をめぐる上記の諸事情を総合すると、各方式による試算額をほぼ均等に考慮するのが相当である。
以上によれば、本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額を、上記の各試算額のほぼ平均値である1坪当たり月額8000円(月額77万8400円)と認めるのが相当である。
6 以上によれば、一審原告の請求は、本件建物の平成16年2月1日以降の賃料が月額77万8400円であることの確認を求め、これと現行賃料との差額の支払及び差額分に対する年1割の割合による利息の支払を求める限度(一審原告の当審における拡張部分を含めて)で理由があるが、その余は理由がなく、これと結論を一部異にする原判決は相当でないから、一審被告の控訴は一部理由があり、一審原告の控訴は理由がない。なお、仮執行宣言については、相当でないのでこれを付さない。
よって主文のとおり判決する。 第6民事部 (裁判長裁判官 渡邉安一 裁判官 安達嗣雄 裁判官 明石万起子)
平成26年9月25日/最高裁判所第一小法廷/判決/平成25年(受)1649号
借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。
1 本件は,建物の賃貸人であるX1(なお,訴訟係属中にその地位をX2が承継し,引受人として当事者となった。)が,賃借人であるYに対し,借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求をした上,増額された賃料額の確認等を求めた事案である。
X1とYとの間には,本件訴訟に先立つ訴訟(以下「前件訴訟」という。)があり,前件訴訟においては,Yが,当時月額300万円であった上記建物の賃料(以下「本件賃料」という。)につき,平成16年4月1日以降月額240万円に減額する旨の意思表示をした上,本訴として,同日以降の本件賃料が同額であることの確認等を求め,X1が,平成17年8月1日以降の本件賃料を月額320万2200円に増額する旨の意思表示をした上,反訴として,同日以降の本件賃料が同額であることの確認等を求めていた。そして,前件訴訟の第1審は,本訴につき,本件賃料が平成16年4月1日以降月額254万5400円である旨を確認する一方,反訴については請求を棄却する旨の判決をし,この判決に対するX1の控訴が棄却され,上記判決は確定した(以下,この確定判決を「前訴判決」という。)。
本件訴訟は,X1が,前件訴訟の第1審係属中に,平成19年7月1日以降の本件賃料を月額360万円に増額する旨の意思表示(以下「本件賃料増額請求」という。)をしていたことから,前訴判決確定後,改めて提訴し,同日以降の賃料が同額であることの確認等を求めたものである。
主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由
上告代理人石井義人ほかの上告受理申立て理由(第4を除く。)について
1 原審の確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
(1) 承継前被上告人は、昭和48年10月16日、第1審判決別紙1物件目録記載の建物部分(以下「本件建物部分」という。)につき、当時の所有者であるAとの間で、期間を昭和49年1月1日から20年間とし、賃料を月額60万円とする旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し、その頃、本件建物部分の引渡しを受けた。
(2) その後、本件賃貸借契約について、賃貸人の地位の移転及び賃料(以下「本件賃料」という。)の改定が繰り返され、平成6年1月1日以降の本件賃料は月額300万円とされていたところ、承継前被上告人は、平成16年3月29日、当時の賃貸人であるBに対し、本件賃料を同年4月1日から月額240万円に減額する旨の意思表示をした(以下、同日の時点を「基準時1」という。)。
そして、承継前被上告人は、平成17年6月8日、同年2月9日に本件賃貸借契約の賃貸人の地位を承継した上告人X1を被告として、「本件賃料が平成16年4月1日から月額240万円であること」の確認等を求める訴訟(以下「前件本訴」という。)を提起した。
(3) 他方、上告人X1は、平成17年7月27日、承継前被上告人に対し、本件賃料を同年8月1日から月額320万2200円に増額する旨の意思表示をした(以下、同日の時点を「基準時2」という。)。
そして、上告人X1は、平成17年9月6日、前件本訴に対し、「本件賃料が平成17年8月1日から月額320万2200円であること」の確認等を求める反訴(以下「前件反訴」といい、前件本訴と併せて「前件訴訟」という。)を提起した。
(4) さらに、上告人X1は、前件訴訟が第1審に係属中の平成19年6月30日、承継前被上告人に対し、本件賃料を同年7月1日から月額360万円に増額する旨の意思表示をした(以下、この意思表示を「本件賃料増額請求」といい、同日の時点を「基準時3」という。)。
これに対し、承継前被上告人は、本件賃料増額請求により増額された本件賃料の額の確認請求を前件訴訟の審理判断の対象とすることは、その訴訟手続を著しく遅滞させることとなるとして、裁判所の訴訟指揮により、上告人X1が、前件訴訟における反訴の提起ではなく、別訴の提起によって上記確認請求を行うよう促すことを求める旨記載した上申書を裁判所に提出した。
(5) 結局、上告人X1は、前件訴訟において、本件賃料増額請求により増額された本件賃料の額の確認請求を追加することはなかった。そして、前件訴訟の第1審は、平成20年6月11日、前件本訴につき、「本件賃料が平成16年4月1日から月額254万5400円であること」を確認するなどの限度で承継前被上告人の請求を認容し、前件反訴についてはその請求を全部棄却する旨の判決をした。
上記判決に対し上告人X1が控訴したが、控訴審は、平成20年10月9日に口頭弁論を終結した上(以下、この口頭弁論の終結時点を「前件口頭弁論終結時」という。)、同年11月20日、上告人X1の控訴を棄却し、上記判決は、同年12月10日に確定した(以下、確定した上記判決を「前訴判決」という。)。
2 本件は、上告人X1及び平成23年4月28日に同上告人から本件賃貸借契約の賃貸人の地位を承継した上告人X2が、承継前被上告人に対し、本件賃料増額請求により増額された本件賃料の額の確認等を求める事案である。本件賃料増額請求が前件口頭弁論終結時以前にされていることから、本件訴訟において本件賃料増額請求による本件賃料の増額を主張することが、前訴判決の既判力に抵触し許されないか否かが争われている。なお、被上告人は、原審の口頭弁論終結後である平成25年3月21日、承継前被上告人を吸収合併し、本件訴訟の訴訟手続を承継した。
3 原審は、前記事実関係の下で、次のとおり判断し、上告人らの請求を棄却した。
賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の訴訟物は、当事者が請求の趣旨において特に期間を限定しない限り、形成権である賃料増減請求権の行使により賃料の増額又は減額がされた日から事実審の口頭弁論終結時までの期間の賃料額であると解されるところ、前件訴訟において、承継前被上告人は、基準時1から前件口頭弁論終結時までの賃料額の確認を求め、上告人X1は、基準時2から前件口頭弁論終結時まで(ただし、終期については基準時3と解する余地がある。)の賃料額の確認を求めたものと解されるから、本件訴訟において、上告人らが、本件賃料増額請求により本件賃料が前件口頭弁論終結時以前の基準時3において増額された旨主張することは、前訴判決の既判力に抵触し許されない。
4 しかし、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1) 借地借家法32条1項所定の賃料増減請求権は形成権であり、その要件を満たす権利の行使がされると当然に効果が生ずるが、その効果は、将来に向かって、増減請求の範囲内かつ客観的に相当な額について生ずるものである(最高裁昭和30年(オ)第460号同32年9月3日第三小法廷判決・民集11巻9号1467頁等参照)。また、この効果は、賃料増減請求があって初めて生ずるものであるから、賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟(以下「賃料増減額確認請求訴訟」という。)の係属中に賃料増減を相当とする事由が生じたとしても、新たな賃料増減請求がされない限り、上記事由に基づく賃料の増減が生ずることはない(最高裁昭和43年(オ)第1270号同44年4月15日第三小法廷判決・裁判集民事95号97頁等参照)。さらに、賃料増減額確認請求訴訟においては、その前提である賃料増減請求の当否及び相当賃料額について審理判断がされることとなり、これらを審理判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が現実に合意した賃料のうち直近のもの(直近の賃料の変動が賃料増減請求による場合にはそれによる賃料)を基にして、その合意等がされた日から当該賃料増減額確認請求訴訟に係る賃料増減請求の日までの間の経済事情の変動等を総合的に考慮すべきものである(最高裁平成18年(受)第192号同20年2月29日第二小法廷判決・裁判集民事227号383頁参照)。したがって、賃料増減額確認請求訴訟においては、その前提である賃料増減請求の効果が生ずる時点より後の事情は、新たな賃料増減請求がされるといった特段の事情のない限り、直接的には結論に影響する余地はないものといえる。
また、賃貸借契約は継続的な法律関係であり、賃料増減請求により増減された時点の賃料が法的に確定されれば、その後新たな賃料増減請求がされるなどの特段の事情がない限り、当該賃料の支払につき任意の履行が期待されるのが通常であるといえるから、上記の確定により、当事者間における賃料に係る紛争の直接かつ抜本的解決が図られるものといえる。そうすると、賃料増減額確認請求訴訟の請求の趣旨において、通常、特定の時点からの賃料額の確認を求めるものとされているのは、その前提である賃料増減請求の効果が生じたとする時点を特定する趣旨に止まると解され、終期が示されていないにもかかわらず、特定の期間の賃料額の確認を求める趣旨と解すべき必然性は認め難い。
以上の事情に照らせば、賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずると解するのが相当である。
(2) 本件についてこれをみると、前記事実関係によれば、前件本訴及び前件反訴とも、請求の趣旨において賃料額の確認を求める期間の特定はなく、前訴判決の前件本訴の請求認容部分においても同様であり、前件訴訟の訴訟経過をも考慮すれば、前件訴訟につき承継前被上告人及び上告人X1が特定の期間の賃料額について確認を求めていたとみるべき特段の事情はないといえる。
そうであれば、前訴判決の既判力は、基準時1及び基準時2の各賃料額に係る判断について生じているにすぎないから、本件訴訟において本件賃料増額請求により基準時3において本件賃料が増額された旨を主張することは、前訴判決の既判力に抵触するものではない。
5 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上の見地を踏まえて本件賃料増額請求の当否等を審理させるため、本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官金築誠志の補足意見がある。
裁判官金築誠志の補足意見は、次のとおりである。
賃料増減額確認請求訴訟の訴訟物は、当事者が請求の趣旨において特に期間を限定しない限り、形成権である賃料増減請求権の行使により賃料の増額又は減額がされた日から事実審の口頭弁論終結時までの期間の賃料額であるとする原審の見解(以下、この見解を「期間説」という。)は、同訴訟が継続的な法律関係である賃貸借契約の要素としての賃料額の確認を求めるものであること、既判力の基準時までの期間の法律関係が確定され紛争解決の目的により資すること、確認の利益も現在の法律関係を確認の内容として含み問題が少ないことなどからすると、自然な考え方であるように思われるかもしれない。
しかし、訴訟物をいかなる形で設定するかは処分権主義に服するものであるから、第一義的には原告の意思によることになるところ(したがって、原告が期間を特定して賃料額の確認を求めた場合は、確認の利益が認められる限り、適法である。)、前件訴訟でも採られているような賃料増減額確認請求訴訟において一般的に見られる形の請求(増減請求時「から」あるいは「以降」の賃料額の確認を求め、特に期間を限定していない請求。以下「一般的形態の請求」という。)をした場合、通常、原告が期間説を念頭に置いて訴えを提起しているものと理解すべきかどうかは、甚だ疑問である。また、裁判所も、期間説に従って訴訟指揮をしているのが通常かというと、そうとはいえないように思われる。実務は、常に意識的ではないかもしれないが、賃料増減請求が効果を生じた時点の賃料額が訴訟物という考え方(以下、この考え方を「時点説」という。)の下に運用されていることが多かったのではないかと推察される。現に、前件訴訟においても、法廷意見にあるとおり、第1審係属中に本件賃料増額請求がなされたが、賃借人から、同請求により増額された賃料額の確認請求を前件訴訟の対象とすることは訴訟手続を著しく遅滞させることになるとして、裁判所の訴訟指揮により別訴を提起するよう促すことを求める旨記載した上申書が提出され、結局、本件賃料増額請求により増額された賃料額の確認請求が追加されることはなかった。そして、前件訴訟の請求を本件賃料増額請求時までの期間に限定するよう裁判所が促した事実等もうかがわれないのである。こうした前件訴訟の経過は、一般的形態の請求の訴訟物は口頭弁論終結時までの期間の賃料額であって、本件賃料増額請求が前訴判決の既判力によって遮断されるなどとは、裁判所を含めて考えていなかったことを示しているように思われる。賃料増減額確認請求の理由の有無は、現行賃料が合意等により定まった時から、増減請求時までの事情に基づいて判断され、請求後の事情は考慮されないのであるから、請求後の期間が、争いの対象として当事者に意識されることは、少ないのではなかろうか。また、一般的形態の請求に対する判決の主文において、賃料額を確認した期間の終期として口頭弁論終結日が記載された例のあることを寡聞にして知らないが、確認判決において確認された内容の基本的な要素が明示されないというのは通常あり得ないことで、このことも、上記のような実務における一般的な意識の有り様を裏付けているのではないだろうか。
一旦定まった賃料額は、別個の合意の存在や賃料増減請求が効果を生じたことが認められない限り、契約当事者を拘束し続けるのであるから、継続的契約たる賃貸借契約の要素である以上期間のあるものとして確認しなければ意義が薄いということはないであろう(なお、請求の趣旨や判決主文で、増減請求の日「から」あるいは「以降」の賃料額の確認を求める旨記載するのは、その日が始点という性格を有することを示しているだけのものと理解できると思う。)。確認の利益の点については、過去の法律関係であっても、紛争の解決に資する確認の利益が認められるものであれば、確認の対象とすることが許されると解されているが、上記のように、一旦定まった賃料額は、別の合意等が認められない限り継続的に当事者を拘束するのであるから、時点説を採っても、確認の利益は肯定されるであろう。紛争解決機能の点についても、賃料増減請求の効果が生じた始点での賃料額について既判力が生じていれば、それに引き続く期間の賃料額に形式的には既判力が及んでいないとしても、上記と同様の理由から、実質的にその機能に差が生じるようなことはほとんど考えられないのではないかと思う。
このように、理論的には、期間説を採るべき必然性はなく、時点説を採ることに支障はないと考えるが、さらに、期間説の難点として、賃料増減額確認請求訴訟の係属中に新たな増減請求がされた場合に、手続上煩わしい問題が生じる可能性があるように思う。増額訴訟中更に増額請求がされた場合や減額訴訟中更に減額請求がされた場合は、前の請求について後の請求時までに期間を限定することになるであろうから、審理の状況に従って、後の請求に係る賃料額確認を、前の請求に係る訴訟の中で処理するか、別訴にしてもらうか、いずれの方法を採ることも困難ではないであろうが、例えば、減額確認請求訴訟中に増額請求がされたような場合は、原告の意思に反して終期を付すように求めることはできないであろう。その結果、遮断効を避けるための反訴の提起を許さざるを得ないことになれば、審理の長期化要因となることは避けられない。その点、時点説は、新たな増減請求がされても、特段の措置を講ずることなく別訴にまわすことができ、審理の複雑化を避けることができる。また、賃料増減額確認請求訴訟は、調停前置であるが、最初の増減請求の結果の賃料額が決まらない限り、新たな増減請求について調停を進めることは困難であろうから、提起を許さざるを得ない上記の反訴のようなものについては調停前置が機能しないおそれがあるのではなかろうか。
以上の次第で、時点説が、実務の運用上、簡明、便宜であって、理論的にも問題はなく、これを採用することが相当と考えるものである。 (裁判長裁判官 横田尤孝 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 白木勇)
平成20年2月29日/最高裁判所第二小法廷/判決/平成18年(受)192号
賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約
強行法規たる借地借家法32条1項を根拠に、土地賃借人が賃貸人に対して請求した賃料減額の当否及び相当純賃料額は、直近の合意賃料、例えば賃貸借契約締結時の純賃料を基礎とし、かつ締結日から減額請求に至るまでの経済変動等の諸事情を考慮して決定されるべきであって、賃料自動改定特約の存在等は前記諸事情に含まれるにすぎないから、特約によって増額された純賃料をもとに、増額から減額請求までの間の事情のみに依拠した判断は許されない。
1 本件は,建物賃貸借契約の賃借人である原告(反訴被告,被控訴人,上告人兼申立人)が賃貸人である被告(反訴原告,控訴人,被上告人兼相手方)に対し賃料減額請求の意思表示をしたとして減額された賃料の確認を求める事案である。
2 事実関係の概要は,次のとおり
(1) 原告と被告は,平成3年12月24日,被告の所有地に,原告が指定した仕様に基づく施設及び駐車場を建設し,レジャー,スポーツ及びリゾートを中心とした15年間の継続事業を展開することを内容とする協定を結んだ。
(2) 原告と被告は,平成4年12月1日,前記(1)の協定を実施するため,被告が原告に対し3棟の建物(ただし,被告がその所有地に工事代金4億5880万円で建築したもの。以下,これらを「本件建物」と総称し,各建物を「建物1」などという。)を賃貸する旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し,被告は,そのころ,原告に対し本件建物を引き渡した。本件賃貸借契約の内容は,一定期間経過後は純賃料額を一定の金額に自動的に増額する旨の賃料自動増額特約(イ(ア)記載のもの。以下「本件自動増額特約」という。)が含まれている。
主文
原判決中、上告人の本訴請求に関する部分を破棄する。
前項の部分につき、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由
上告代理人四宮章夫、同松丸知津の上告受理申立て理由について
1 本件本訴請求は、被上告人の所有に係る建物を賃借した上告人が、賃貸人である被上告人に対し、賃料減額請求により減額された賃料の額の確認を求めるものである。本件反訴請求について、その一部を却下し、その余を棄却した原判決に対する不服申立てはない。
2 原審の確定した事実関係の概要は次のとおりである。
(1) 上告人、被上告人、A、B及びCは、平成3年12月24日、被上告人の所有地に、上告人が指定した仕様に基づく施設及び駐車場を建設し、レジャー、スポーツ及びリゾートを中心とした15年間の継続事業を展開することを内容とする協定を結んだ。
(2) 上告人と被上告人は、平成4年12月1日、前記(1)の協定を実施するため、被上告人が上告人に対し第1審判決別紙物件目録記載1~3の各建物(ただし、被上告人がその所有地に工事代金4億5880万円で建築したもの。以下、これらを「本件建物」と総称し、各建物を同目録の番号により「建物1」などという。)を賃貸する旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し、被上告人は、そのころ、上告人に対し本件建物を引き渡した。本件賃貸借契約の内容は次のとおりであり、一定期間経過後は純賃料額を一定の金額に自動的に増額する旨の賃料自動増額特約(イ(ア)記載のもの。以下「本件自動増額特約」という。)が含まれている。
ア 期間 平成4年12月1日から15年間
イ 賃料 次の(ア)の約定純賃料及び(イ)の償却賃料の合計額を月額賃料とする。
(ア) 約定純賃料(月額)
a 平成4年12月1日~平成7年11月30日 360万円
b 平成7年12月1日~平成9年11月30日 369万円
c 平成9年12月1日~平成14年11月30日 441万4500円
d 平成14年12月1日~平成19年11月30日 451万9500円
(イ) 償却賃料
a 建物2及び3に係る各該当年度の不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の合計額の12分の1の相当額
b 上告人が被上告人に対し無利息で預託する後記ウの建設協力金相当額
ウ 上告人は、被上告人に対し、本件建物の建設協力金として、建物1につき7500万円、建物2及び3につき3億2760万円を預託する。
被上告人は、上告人に対し、建物1の建設協力金7500万円につき、3年間据え置いた後、20%相当額を控除した金額を平成7年12月から144回に分割して返還し、建物2及び3の建設協力金3億2760万円については、6か月間据え置いた後、平成5年6月から174回に分割して返還する。
エ 賃料の改定
消費者物価指数の変動及び経済情勢の変動が予期せざる程度に及び、本件建物の約定純賃料が著しく不相当となった場合は、上告人及び被上告人で協議の上、これを改定することができる。
(3) 本件賃貸借契約後、本件建物の所在する大阪府下の不動産市況は下降をたどり、不動産の価格も下落し続けている。
(4)ア 上告人は、平成9年6月27日ころ、被上告人に対し、同年7月1日をもって本件建物の約定純賃料を減額する旨の意思表示をした(以下「第1減額請求」という。)。
イ 上告人は、平成13年11月26日、被上告人に対し、同年12月1日をもって本件建物の約定純賃料を減額する旨の意思表示をした(以下「第2減額請求」といい、第1減額請求を併せて「本件各減額請求」という。)。
3 原審は、次のとおり判示して、上告人の請求を棄却すべきものとした。
事情の変更があるときに、当事者の一方の請求により約定賃料額の増減を認めることとする借地借家法32条の法意からすれば、ここにいう事情の変更とは、増減を求められた額の賃料の授受が開始された時から請求の時までに発生したものに限定すべきことは、事の性質上、当然である。
また、本件においては、経済事情の変動等のほか、本件自動増額特約が、15年間にわたる将来の経済変動をある程度予測した上で定められたものであり、上告人と被上告人との共同事業の中核として当事者に対する拘束性の強いものと評価されるという特別の事情を、本件各減額請求の当否及び相当純賃料の額の算定においてしんしゃくすべきである。
平成9年6月27日ころにされた第1減額請求については、請求時の賃料額である月額369万円の約定純賃料の授受が開始された平成7年12月1日から第1減額請求の日ころまでに発生した経済事情の変動等を考慮すべきであるが、この期間における経済事情の変動等のほか、前記特別の事情にもかんがみると、第1減額請求の時の約定純賃料額369万円が不相当になったということはできない。
また、平成13年11月26日にされた第2減額請求については、請求時の賃料額である月額441万4500円の約定純賃料の授受が開始された平成9年12月1日から第2減額請求の日までに発生した経済事情の変動等を考慮すべきところ、この期間における経済事情の変動等のほか、前記特別の事情にもかんがみると、第2減額請求の時の約定純賃料額441万4500円が不相当になったということはできない。
4 論旨は、原審は借地借家法32条1項の規定の解釈を誤ったというものであるので、この点について判断する。
借地借家法32条1項の規定は、強行法規であり、賃料自動改定特約によってその適用を排除することはできないものである(最高裁昭和28年(オ)第861号同31年5月15日第三小法廷判決・民集10巻5号496頁、最高裁昭和54年(オ)第593号同56年4月20日第二小法廷判決・民集35巻3号656頁、最高裁平成14年(受)第689号同15年6月12日第一小法廷判決・民集57巻6号595頁参照)。そして、同項の規定に基づく賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が現実に合意した賃料のうち直近のもの(以下、この賃料を「直近合意賃料」という。)を基にして、同賃料が合意された日以降の同項所定の経済事情の変動等のほか、諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、賃料自動改定特約が存在したとしても、上記判断に当たっては、同特約に拘束されることはなく、上記諸般の事情の一つとして、同特約の存在や、同特約が定められるに至った経緯等が考慮の対象となるにすぎないというべきである。
したがって、本件各減額請求の当否及び相当純賃料の額は、本件各減額請求の直近合意賃料である本件賃貸借契約締結時の純賃料を基にして、同純賃料が合意された日から本件各減額請求の日までの間の経済事情の変動等を考慮して判断されなければならず、その際、本件自動増額特約の存在及びこれが定められるに至った経緯等も重要な考慮事情になるとしても、本件自動増額特約によって増額された純賃料を基にして、増額前の経済事情の変動等を考慮の対象から除外し、増額された日から減額請求の日までの間に限定して、その間の経済事情の変動等を考慮して判断することは許されないものといわなければならない。本件自動増額特約によって増額された純賃料は、本件賃貸契約締結時における将来の経済事情等の予測に基づくものであり、自動増額時の経済事情等の下での相当な純賃料として当事者が現実に合意したものではないから、本件各減額請求の当否及び相当純賃料の額を判断する際の基準となる直近合意賃料と認めることはできない。
しかるに、原審は、第1減額請求については、本件自動増額特約によって平成7年12月1日に増額された純賃料を基にして、同日以降の経済事情の変動等を考慮してその当否を判断し、第2減額請求については、本件自動増額特約によって平成9年12月1日に増額された純賃料を基にして、同日以降の経済事情の変動等を考慮してその当否を判断したものであるから、原審の判断には、法令の解釈を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。
5 以上によれば、上記と同旨をいう論旨は理由があり、原判決中、上告人の本訴請求に関する部分は破棄を免れない。そこで、本件各減額請求の当否等について更に審理を尽くさせるため、上記の部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 津野修 裁判官 今井功 裁判官 古田佑紀)
大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第2138号 平成20年04月30日
借地借家法32条1項に基づき、相当賃料額への増額を請求することができる
駅ターミナルに近接した商業ビル最上階全部を目的とする賃貸借契約につき、契約締結後に近隣の賃料相場が特に上昇したとはいえないとしても、賃貸人が賃借人の事情を配慮したうえで、当初の賃料をビル内の他のテナントに比して相当程度低額に設定していたなどの事実が認められる場合には、賃貸人は賃借人に対し、借地借家法32条1項に基づき、相当賃料額への増額を請求することができる。
商業用ビルの賃貸借契約においては、借地借家法32条1項にいう経済事情の変動等がなくても、賃料が他のテナントより低額であったこと等の契約当初の事情を考慮して賃料増額請求を認めるべきである。
主文
1 一審原告の控訴を棄却する。
2(1) 一審被告の控訴及び一審原告の当審における請求の拡張に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(2) 一審原告が一審被告に賃貸している原判決別紙物件目録記載の建物の賃料は、平成16年2月1日以降、月額77万8400円であることを確認する。
(3) 一審被告は、一審原告に対し、953万5400円及びうち19万4600円については平成16年3月6日から、うち19万4600円については同年4月8日から、うち19万4600円については同年5月8日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月8日から、うち19万4600円については同年8月7日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月8日から、うち19万4600円については同年11月6日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については同17年1月8日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、うち19万4600円については同年4月8日から、うち19万4600円については同年5月7日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月8日から、うち19万4600円については同年8月6日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月8日から、うち19万4600円については同年11月8日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については同18年1月7日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、うち19万4600円については同年4月8日から、うち19万4600円については同年5月3日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月8日から、うち19万4600円については同年8月8日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月7日から、うち19万4600円については同年11月8日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については同19年1月6日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、うち19万4600円については同年4月7日から、うち19万4600円については同年5月8日から、うち19万4600円については同年6月8日から、うち19万4600円については同年7月7日から、うち19万4600円については同年8月8日から、うち19万4600円については同年9月8日から、うち19万4600円については同年10月6日から、うち19万4600円については同年11月8日から、うち19万4600円については同年12月8日から、うち19万4600円については平成20年1月8日から、うち19万4600円については同年2月8日から、うち19万4600円については同年3月8日から、各支払済みまで各年1割の割合による各金員を支払え。
(4) 一審原告のその余の請求(当審で拡張した請求を含む。)を棄却する。
3 訴訟費用は、1、2審を通じてこれを5分し、その2を一審原告の、その余は一審被告の負担とする。 事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 一審原告
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 一審原告が一審被告に賃貸している原判決別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の賃料は、平成16年2月1日以降、月額116万7600円であることを確認する。
(3) 一審被告は、一審原告に対し、2860万6200円及びうち58万3800円については平成16年3月6日から、うち58万3800円については同年4月8日から、うち58万3800円については同年5月8日から、うち58万3800円については同年6月8日から、うち58万3800円については同年7月8日から、うち58万3800円については同年8月7日から、うち58万3800円については同年9月8日から、うち58万3800円については同年10月8日から、うち58万3800円については同年11月6日から、うち58万3800円については同年12月8日から、うち58万3800円については同17年1月8日から、うち58万3800円については同年2月8日から、うち58万3800円については同年3月8日から、うち58万3800円については同年4月8日から、うち58万3800円については同年5月7日から、うち58万3800円については同年6月8日から、うち58万3800円については同年7月8日から、うち58万3800円については同年8月6日から、うち58万3800円については同年9月8日から、うち58万3800円については同年10月8日から、うち58万3800円については同年11月8日から、うち58万3800円については同年12月8日から、うち58万3800円については同18年1月7日から、うち58万3800円については同年2月8日から、うち58万3800円については同年3月8日から、うち58万3800円については同年4月8日から、うち58万3800円については同年5月3日から、うち58万3800円については同年6月8日から、うち58万3800円については同年7月8日から、うち58万3800円については同年8月8日から、うち58万3800円については同年9月8日から、うち58万3800円については同年10月7日から、うち58万3800円については同年11月8日から、うち58万3800円については同年12月8日から、うち58万3800円については同19年1月6日から、うち58万3800円については同年2月8日から、うち58万3800円については同年3月8日から、うち58万3800円については同年4月7日から、うち58万3800円については同年5月2日から、うち58万3800円については同年6月7日から、うち58万3800円については同年7月6日から、うち58万3800円については同年8月7日から、うち58万3800円については同年9月7日から、うち58万3800円については同年10月5日から、うち58万3800円については同年11月7日から、うち58万3800円については同年12月7日から、うち58万3800円については平成20年1月7日から、うち58万3800円については同年2月7日から、うち58万3800円については同年3月7日から、各支払済みまで各年1割の割合による各金員を支払え。
2 一審被告
(1) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
(2) 同取消しに係る一審原告の請求を棄却する。
第2 事案の概要
1 事案の骨子及び訴訟経過
本件は、一審原告が、大阪市A区〈中略〉171番地1・171番地3所在の鉄骨鉄筋コンクリート造地下3階・地上9階建て、延床面積5399.04m2の「ジュピタービル」という名称のビル(以下「本件ビル」という。)のうちの9階部分である本件建物を、平成12年11月に賃料月額58万3800円で一審被告に賃貸したところ、一審被告に対し、賃料増額改訂の特約又は借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求により増額された平成16年2月1日以降の相当賃料額の確認を求めるとともに、既に支払われた賃料と相当賃料額との差額及びこれに対する支払期後から支払済みまで同条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求めた事案である。
原審は、賃料増額改訂の特約を認めるに足りる証拠はないが、本件建物の賃料は経済事情の変動等により不相当になったといえるから、一審原告は、借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求権を有するところ、本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額は月額89万2000円であるとして、一審原告の請求のうち、本件建物の平成16年2月1日以降の賃料を月額89万2000円と確認し、これと既に支払われた賃料との差額及びこれに対する支払済みまで同条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求める限度で認容し、その余を棄却した。
そのため、一審原告及び一審被告の双方が本件各控訴を提起した。
2 前提となる事実
次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の1のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決4頁23行目から同24行目にかけての「別紙物件目録記載の物件」を「本件建物(契約面積321.09m2、97.3坪)」と改める。
(2) 原判決5頁6行目の「原告において」を「一審原告と一審被告の協議の上」と改め、同7行目の「5条」の次に「、特約事項」を加える。
(3) 原判決5頁12行目から同16行目までを次のとおり改める。
「 本件賃貸借契約においては、経費の分担として、一審被告が、共同管理費として月額68万1100円(1坪当たり7000円)を負担する(本件契約書11条1項)ほか、経常販促費として月額9万7300円(1坪当たり1000円)を負担することになっており、一審被告が、一審原告及び本件ビルの全入店者をもって構成するテナント会に入会することが定められている(本件契約書27条)。(乙1、3)」
(4) 原判決5頁25行目の「同16年」から6頁初行の「乙2)」までを「平成16年2月1日以降の本件建物の賃料を月額116万7600円に増額する旨の意思表示をした(甲4、乙2、以下「本件増額請求」という。)が」と改める。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 賃料増額改訂の特約の有無
ア 一審原告の主張
原判決6頁9行目から同11行目までのとおりであるから、これを引用する。
イ 一審被告の主張
原判決6頁13行目から同15行目までのとおりであるから、これを引用する。
(2) 共同管理費の大部分が賃料に該当するか否か
ア 一審被告の主張
原判決7頁8行目末尾に改行の上、次のとおり加えるほかは原判決6頁19行目から7頁8行目までのとおりであるから、これを引用する。
「 共同管理費は、本件賃貸借契約を締結してから現在まで月額68万1100円の定額のままであり、実費の精算を求められたり、余剰金の返還を受けたこともなく、テナント会においての決議は、各テナントが共同管理費の使途内訳について関心がないため、形骸化している。そのため、本件建物の共同管理費は、管理業務の実費とはいえず、使用収益の対価と見るべきである。」
イ 一審原告の主張
原判決7頁10行目から同25行目までのとおりであるから、これを引用する。
(3) 借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求の当否
ア 一審原告の主張
借地借家法32条1項の要件の充足を検討するに際しては、賃貸借契約が締結されるに至った経緯も考慮される。
一審原告は、従来から、仲介業者等に対して、入店に際して一審原告が希望する条件をパンフレット(甲15)で示しており、入店希望者は、仲介業者からその情報を入手して、入店希望を申し入れ、交渉の上で賃料等の金額を決定することになっており、一審被告としても、当然、本件ビルの他のテナントの賃料相場を認識していたといえるところ、本件賃貸借契約を締結するに際して、一審被告から、仲介業者の株式会社アルファ(以下「アルファ社」という。)を介して、賃料を共益費込みで1坪当たり1万3000円としてほしいとの要望がなされた。一審原告としては、本件ビルの他のテナントの共同管理費が1坪当たり7000円であり、一審被告の要望では賃料が共同管理費を下回ることになるため、当初、一審被告の要望を拒否していた。しかしながら、その後も、アルファ社を介して一審被告から入店への意欲が示された。そのため、一審原告は、一審被告が本件ビルの近辺にある大型複合商業ビルである「サターンビル」において店舗を構えていたところ、この店舗が経営不振に陥り、本件建物へ移転することになり、移転に関する費用が必要になることや、本件建物での営業も同様に経営不振になるかもしれないという将来性に対する危惧等から、営業基盤が確立されるまでの3年間は、破格の賃料を要求しているという一審被告の事情を考慮して、3年間という暫定的な期間であれば、一審被告の要望を受け入れることにした。
そして、一審原告は、一審被告に対して、3年後には適正な賃料に改定することを要請し、本件契約書の調印の際にも、一審原告の代表者自らが一審被告に再確認をしているし、アルファ社からも、本件建物の当初賃料額が一審被告の事情を特別に配慮したものであることや3年後の賃料改定のことを記載した報告書(甲13)が提出されたのである。
このように、一審被告の事情を考慮して特別に当初の3年間という期間限定で破格の条件で賃料を定めたことは明らかであるから(社会通念上、商業施設の貸主が、このような破格の条件での賃料が長期間継続されることを前提とする契約を締結するはずはない。)、本件増額請求は、借地借家法32条1項の要件を充足している。
イ 一審被告の主張
本件賃貸借契約の締結から平成16年2月までの3年間で、借地借家法32条1項が規定する土地若しくは建物に対する租税その他の負担が増加したという事情もなければ、土地若しくは建物の価格の上昇といった経済的事情の変動もない。また、同項が規定する「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」とは、相当期間適時適正な賃料改定が行われてこなかったために近傍同種の建物の賃料と比較して不相当となったような場合を予定しているところ、本件賃貸借契約の締結からわずか3年しか経過しておらず、かつ、その3年間で周辺のテナントビルの賃料相場が急激に上昇したといった事情もないから、本件建物の賃料が「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」にも当たらない。
また、一審被告は、本件賃貸借契約の締結に至る条件交渉において、本件ビルの他のテナントの賃料等について何ら説明を受けておらず、甲15のパンフレットも含めて入店条件等の記載された資料も一切受け取っていない。一審被告は、「サターンビル」において営業していたフランチャイズ店が独立することになったため、直営店をA近辺で出店するべく適当な物件を探しており、この店舗の賃料が共益費込みで月額1坪当たり1万3000円であったことから、アルファ社を介して、一審原告に賃料希望額を提示したにすぎず、「サターンビル」の店舗が営業不振であったという事実もないし、営業基盤が確立する3年間は破格の賃料を希望したという事実もない。
そもそも、上記(2)の一審被告の主張のとおり本件賃貸借契約における実質的な賃料は、本件契約書上の賃料と共同管理費を併せたものであり、この実質的な賃料は、当時の賃料相場からみても相当なものであった。
しかも、一審被告は、賃貸借契約書案の5条(賃料等の変更)の条項が「甲において変更することができる」となっているのを、特約条項として「甲乙協議の上」に変更してほしいと要請し、これを一審原告が了承して本件契約書の特約条項になっているのであるから、これに反する特段の合意など存在しない。
したがって、本件増額請求は、借地借家法32条1項の要件を充足しない。
(4) 相当賃料額
ア 一審原告の主張
次のとおり補正するほかは、原判決8頁2行目から同23行目までのとおりであるから、これを引用する。
(ア) 原判決8頁2行目から同3行目までを次のとおり改める。
「 本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額は、月額116万7600円であり、これは、不動産鑑定士乙山二郎の鑑定評価書(甲3、以下「乙山鑑定」という。)により裏付けられる。」
(イ) 原判決8頁4行目の「鑑定」から同5行目の「〔以下「一審被告側鑑定」という。〕)」までを「不動産鑑定士丙川三郎の鑑定評価書(乙5、以下「丙川鑑定」という。)」と改める。
(ウ) 原判決8頁23行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「 鑑定人甲野一郎の鑑定書(以下「甲野鑑定」という。)は、〈1〉差額配分法による賃料を算定する際に、折半法を採用していること、〈2〉スライド法を適用すべきではないのにそれを適用し、スライド指数を本件ビルの周辺地域の商業ビルの賃料動向ではなく、大阪市消費者物価指数の総合とB・A地区の事務所賃料の推移の加重平均としていること、〈3〉利回り法の継続賃料利回りを0.53%と極めて低い数値にしていること、〈4〉賃貸事例比較法を適用していないことなどから不当であり、採用できない。」
イ 一審被告の主張
次のとおり補正するほかは、原判決8頁25行目から9頁10行目までのとおりであるから、これを引用する。
(ア) 原判決中「原告側鑑定」をすべて「乙山鑑定」と改める。
(イ) 原判決9頁10行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「 甲野鑑定は、〈1〉差額配分法、スライド法及び利回り法による各試算賃料を8対1対1と配分して賃料額を算定しているが、この配分比には根拠がないこと、〈2〉鑑定による賃料額に共同管理費を加算した結果が、TKC経営指標による平均賃料比率のやや上方に位置するとして、鑑定の妥当性を根拠付けようとしているが、鑑定に当たっては、共同管理費を賃料に含めておらず自己矛盾を来していること、〈3〉鑑定による賃料額に共同管理費を含めた賃料の1坪当たりの単価が、鑑定評価書中の「試算賃料算出表1」のB、D、Eの賃貸事例のそれと比較して違和感がないとしているが、これらの賃貸事例は、本件賃貸借契約と類似しておらず、不当であることなどから、採用できない。」 第3 当裁判所の判断
1 本件賃貸借契約の締結に至る経緯等
前提となる事実、証拠(甲2ないし6、10ないし16、乙1ないし5、鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 本件ビルは、2棟からなる登記簿上一棟の建物のうち西側に位置する建物(家屋番号 〈住所略〉171番1の4)であり、昭和63年11月に新築された鉄骨鉄筋コンクリート造地下3階付9階建ての飲食ビル(ただし、地下3階は、一部倉庫として賃貸に供されている部分もあるが、基本的には機械室・搬入路等の共用スペースである。)である。
本件ビルは、A1駅の外、B1駅、B2駅、B3駅が集積する駅ターミナルに近接しており、太陽百貨店等の大型複合商業ビルが建ち並ぶ高度商業地域に位置しており、3階部分で南側に隣接する太陽百貨店の遊歩道と、地下2階部分で地下街(駅等の連絡通路)とそれぞれ連結しているとともに、地下3階部分においても、唯一の搬入路として太陽百貨店側の車両搬入路と連結しており、その使用料を一審原告が支払っている。また、一棟建物(全体ビル)である二棟間では、2階、地下1階、地下2階で連結している。
本件建物は、本件ビルの最上階である9階に位置し、天井高が約5mとほかの階(約3.6m)に比べて相当高くなっている。
(2) 一審原告が昭和62年に本件ビルの賃借希望者向けに作成したパンフレット(甲15)には、出店の条件として〈1〉店舗内装工事は入店者の負担とする、〈2〉経常販促費として売上高の1%を負担する、〈3〉9階の保証金を1坪当たり170万円、固定家賃を1坪当たり2万円とする、〈4〉共同管理費として、共同部分・施設に要する費用で空調冷暖房・水道・光熱・給排水・衛生処理・保安設備・清掃・昇降機・植栽管理・屋外照明等々の費用の実費を契約面積につき負担するなどと記載されている。
(3) 一審被告は、平成12年7月ころ、仲介業者であるアルファ社を介して、一審原告に対して、一審被告の会社概要、印鑑証明書及び登記簿謄本をファクシミリで送信するなどして本件建物への入店を希望した。
一審被告は、本件ビルの近辺にある「サターンビル」という名称の大型複合商業ビル内に店舗を構えており、そこから本件建物に移転することを企図していたが、「サターンビル」での店舗の賃料が共益費込みで月額1坪当たり1万3000円であったため、アルファ社を介して、一審原告に対して、本件建物の賃料の希望額として共益費込みで月額1坪当たり1万3000円を提示した。
一審原告としては、当時、本件ビルの他のテナントから共同管理費として月額1坪当たり7000円を徴収しており、一審被告に対する共同管理費も同じ金額になるため、一審被告の希望額では賃料が月額1坪当たり6000円となり、当時の他のテナントの賃料(契約日、面積、保証金額等はそれぞれ異なるものの月額1坪当たり1万円ないし5万円程度)と比較しても相当低額になるため、一審被告の希望賃料額を拒否していたが、一審被告には、他のテナントの賃料や保証金額等の賃貸条件の情報を開示しなかった。
その後も、一審被告は、アルファ社を介して入店を希望し、一審原告と賃料額等について交渉をしたが、最終的には、一審原告は、本件ビルの近辺の大型複合商業ビルから移転することで、本件建物での営業が軌道に乗るまでに費用や時間を要することなど一審被告の抱える諸事情を配慮し、3年後に賃料を他のテナントの賃料水準程度に増額してもらえばよいであろうという見込みのもとで、一審被告の賃料希望額に応じることにした。
他方、一審被告としては、一審原告に提示していた賃料希望額が、本件ビルの近辺の大型複合商業ビルの共益費込みの1坪当たりの賃料と同額であったこと、アルファ社から、賃料と共同管理費はテナント会や経理上の都合で便宜的に区分したものであると報告を受けていたこと、本件ビルの他のテナントの賃料相場を知らなかったことから、他のテナントと比較して特に低額な賃料に応じてもらったという認識を持っていなかった。
(4) 一審原告は、平成12年10月ころ、アルファ社を介して一審原告に契約書案を送付した。この契約書案の5条には「賃料等は、原則として3年毎に経済情勢等の変動に応じ、甲(一審原告)において変更することができる。」との規定が、9条には、「甲が経済情勢の変動その他に鑑み必要と認めて出店保証金の増額を請求した場合(中略)不足の場合は乙は1ケ月以内にこれを補充する。」との規定が、13条4項には、「乙はその責任において従業員を派遣し、(中略)甲の要求があったときは直ちに従業員を変更する」との規定があり、ほかに、6条として「乙は店舗における売上総額をすべてレジスターに登録し、登録後の売上現金を毎日甲に引き渡すものとする」との規定があった。一審被告は、これらの規定につき、アルファ社を介して、5条、9条、13条4項については、いずれも一審原告と一審被告の協議の上、変更できるものとする、一審被告が売上総額をすべてレジスターに登録し、売上金内訳票と売上レシートを毎日一審原告に提出し、登録後の売上現金は一審被告が保管し、翌月7日までに賃料及び共同管理費等を一審原告指定の銀行口座に振り込むなどという内容に変更するよう要請したところ、一審原告は、これらの変更に応じた。
また、一審原告は、アルファ社を介して、一審被告に対して3年後に賃料を改定することを要請していたが、アルファ社は、一審原告に対し、同年11月24日付けの報告書(甲13)によって、一審被告の代表取締役及び専務取締役と面談して得た感触としては、一審被告としては、3年後について予測をすることは困難であり、移転に伴う問題や店舗の立ち上げ等数多くの乗り越えなければならない問題があり、3年後に賃料の改定の申出があった場合には、その時点での運営状況及び近隣の経済情勢を鑑み信頼関係を前提に一審原告と協議して紳士的に決定させていただきたいという意向である旨報告した。
そして、一審原告と一審被告は、同年11月29日、特約事項として「本契約第5条(賃料等の変更)、本契約第9条(出店保証金額の変更)、本契約第13条(乙の義務)第〈4〉項「従業員の変更」は甲・乙協議の上変更できるものとする」と付加した本件契約書(乙1)を作成し、同年10月30日付けで上記の一審被告の変更案を入れた覚書(甲2)を作成したが、3年後に賃料を増額する旨を合意した文書は何ら作成されていない。
(5) 一審原告は、平成15年11月20日ころ、一審被告に対し、本件契約書の5条に基づき、本件増額請求をした。
本件賃貸借契約が締結された平成12年11月から平成16年2月までの間、地価は下落傾向であり、本件建物やその敷地の公租公課が増額したということはなく、本件ビルの他のテナントの賃料や周辺の賃料相場が特に上昇したということもない。また、一審被告の売上額は、平成12年12月から平成13年3月までは月平均の*万円程度であったが、毎年次第に減少し、平成15年4月から平成16年3月までは月平均*万円程度になっていた。
2 争点(1)(賃料増額改訂の特約の有無)について
一審原告は、一審被告の経営事情等を配慮して営業基盤が確立するまでの当初の3年間に限って破格の条件での賃料にしたので、一審被告との間で3年後に賃料を増額することを合意した旨主張する。
確かに、上記1認定事実によれば、本件建物の賃料額は、当時の本件ビルの他のテナントの賃料に比べて相当低額であり、一審原告が、一審被告の経営事情等に配慮してその希望額に応じたという経緯ではあるものの、他方、一審被告としては、一審原告から本件ビルの他のテナントの賃料額について知らされていなかったため、それについての認識を持っておらず(なお、一審被告が出店条件を記載したパンフレット(甲15)を受け取ったことを認めるに足りる証拠はなく、仮に受け取ったとしてもこのパンフレットが昭和62年当時のものであって、それに記載された出店条件が平成12年当時に当てはまるとは考え難いことから、このパンフレットによって一審被告が、当時の本件ビルの他のテナントの賃料相場を認識していたと認めることはできない。)、本件ビルの周辺にある大型複合商業ビル内の店舗の共益費込みの賃料額が月額1坪当たり1万3000円であったことから、本件建物の賃料が他のテナントと比較して相当低額であるとは認識していなかったことが認められる。
このように一審原告と一審被告との間には本件建物の適正賃料額についての認識がそもそも一致していなかったといわざるを得ず、このことは、契約書案の5条が「賃料等は、原則として3年毎に経済情勢等の変動に応じ、甲において変更することができる。」と貸主に賃料等の変更請求権があるという有利な条項となっていたところ、一審被告の要望により、特約事項として、当該条項を「一審原告と一審被告の協議の上変更できるものとする」と改められたことやその他の契約条項についても一審被告の希望に従って変更がされていることに表れているといえる。
また、アルファ社の報告書(甲13)の文面も、一審被告が、3年後に一審原告から賃料改定の申出があった場合、その時点での運営状況及び近隣の経済情勢を考慮して協議の上決定していくという意向が記載されているにとどまり、3年後に増額することを約束したという文面にはなっていない。
以上によれば、一審原告と一審被告との間で本件建物の賃料を3年後に増額する旨の合意があったことを認めることはできない。
3 争点(2)(共同管理費の大部分が賃料に該当するか否か)について
一審被告は、本件建物の共同管理費の大部分が賃料である旨主張する。
確かに、上記1認定のとおり、一審被告は、本件建物の賃料額を決定するに当たり、共同管理費を含めた金額を実質的な賃料として交渉をしており、仲介業者であるアルファ社から、賃料と共同管理費に区分されるのは、テナント会や経理上の都合による便宜的なものであると説明されている。また、証拠(甲3、乙3、5)及び弁論の全趣旨によれば、本件建物の共同管理費は、丙川鑑定(乙5)が参考資料として大阪市内の店舗の賃貸事例として掲げている共益費と管理費の合計額と比較してかなり高額であり、本件賃貸借契約を締結してから月額1坪当たり7000円と定額で推移し、実費精算がされたことがなかったことが認められる。
しかしながら、証拠(甲3、乙1、3、5、鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば、〈1〉本件契約書上は、賃料は月額58万3800円と明確に定められ、共同管理費と区別されていること、〈2〉共同管理費は、警備費用(人員警備及び機械警備)、設備管理費用(設備管理費用、エレベーター管理費用、電気設備保守料、消防設備点検料、空気環境測定料及び水質検査料)、清掃費用(全館共用部分の日常清掃、定期清掃、塵芥処理費用、貯水槽清掃費用、防虫防鼠作業料、共用雑排水通管清浄)、特別修繕費等に使用されており、その明細や領収証は明らかにされていないものの、毎年、一審原告から、一審被告を含むテナント会に対して、管理業務予算案が示されて決議され、その実績が報告されて承認を受けていること、〈3〉本件ビルは、4階に一審原告の事務室やイベントホールがある以外はすべて飲食店業者が入居し、出店しているすべての店舗がテナント会を構成して、共同管理費の予算の決議や決算の承認を行うことになっているのに対し、丙川鑑定が参考資料として掲げる大阪市内の店舗の賃貸事例がこのようなビル全体が商業施設である賃貸借であるのかどうか不明である上、甲野鑑定が参考資料として掲げる大規模複合商業ビルの共益費が月額1坪当たり6100円ないし1万円であって本件建物の共同管理費と差異がないことが認められ、これらの事実によれば、本件建物の共同管理費の大部分が実質的な賃料であると認めることはできない。
4 争点(3)(借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求の当否)について
借地借家法32条1項は、土地又は建物の賃貸借契約が長期間に及ぶことが多いため、事情の変更に応じて不相当になった賃料を調整し、当事者の衡平を図ることを目的としたものであるから、同項に基づく賃料増額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が現実に合意した賃料のうち直近のものを基にして、それ以降の同項所定の経済事情の変動等のほか、賃貸借契約の締結経緯、賃料額決定の要素とした事情等の諸般の事情を総合的に考慮すべきである。
上記1認定事実によれば、本件賃貸借契約が締結された平成12年11月から本件増額請求において賃料改定時とされた平成16年2月までの約3年間で、同項所定の土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増加、土地若しくは建物の価格の上昇といった経済的事情の変動もなければ、本件ビルの他のテナントの賃料や周辺の賃料相場が特に上昇したという事情も認められない。
しかしながら、上記1認定事実によれば、本件建物の現行賃料額は、本件ビルの他のテナントの賃料と比較して相当低額であり、このような低額になったのは、一審被告が本件ビルの近辺のビルの店舗から本件建物に移転することから、本件建物での営業が軌道に乗るまでに費用や時間等を要するという諸事情を一審原告が配慮したためであり、一審被告としても、本件ビルの他のテナントの賃料相場についての認識はなかったとはいえ、一審原告が当初は一審被告の希望する賃料額を拒否していたが、その後の交渉によって希望どおりの条件で賃料額が決定したことや一審原告が3年後の賃料改定を要請していたことなどから、本件建物の現行賃料額が本件ビルの他のテナントの賃料と比較して低額であり、一審原告が一審被告が当時抱えていた諸事情を配慮してその希望額に応じたことを認識できたと認められる。
このような現行賃料額決定の経緯等を考慮すると、本件増額請求は、借地借家法32条1項の要件を充足すると認めるのが相当である。
もっとも、相当賃料額を判断するに際しては、現行賃料が合意されてから賃料を増額する要因となる経済事情の変動がないことや一審原告と一審被告との間では、本件建物の適正賃料額についての認識が一致しておらず、そのため、3年後の賃料改定の際に、本件ビルの他のテナントの賃料水準にするという一致した認識もなかったとことを十分考慮する必要がある。
5 争点(4)(相当賃料額)について
(1) 乙山鑑定について
一審原告は、本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額を月額116万7600円(1坪当たり1万2000円)と主張する。
そして、乙山鑑定(甲3)は、本件建物の平成16年2月1日以降の本件建物の適正賃料額について、差額配分法によると月額137万1000円、賃貸事例比較法によると月額145万9000円、中小企業庁編の経営指標の小売飲食店の売上高に占める支払家賃比率が7%であり、一審被告の平成16年4月から平成17年3月までの平均売上額にこの家賃比率を乗じた額が148万円になるとして、これらの配分比を差額配分法を9、賃貸事例比較法を0.5、売上に占める家賃比率による賃料を0.5として、月額138万1000円と評価している。
しかしながら、乙山鑑定は、差額配分法における差額配分比を、居住用借家の継続賃料と異なり商業施設での継続賃料の場合は、貸主に帰属する割合を70%とする3分の1法が適用され、一審原告が平成15年度にテナントの売上向上のためにイベントを開催するなどして2600万円を支出していることから80%としているが、一審被告の負担する共同管理費が年間817万3200円に上り、借主である一審被告も本件ビル全体の維持管理費用として相当な負担をしていることを考慮すれば、差額配分比を3分の1法や80%とすることは、衡平を欠くといえる。
また、証拠(甲3、5、6、9)によれば、乙山鑑定は、一審原告と一審被告との間で、本件建物においての一審被告の当初の売上予測がつかないことなどから、本件ビルの他のテナントの賃料と比較して特別に低廉な賃料にする代わりに、3年後の賃料改定時期には、本件ビルの他のテナントの賃料水準にする旨の合意をしたことを前提とするものであり、そのため、本件ビルの他のテナントで本件建物と同規模の広さで営業時間等も類似した賃貸事例を収集して賃貸事例比較法を採用していることが認められるが、上記2、4認定説示のとおり、一審原告と一審被告との間では、賃料増額の合意の事実が認められないばかりか、3年後の賃料改定の際に他のテナントの賃料水準にするという認識も一致しておらず、しかも、一審被告は、本件ビルの他のテナントの賃料相場を知らなかったのであるから、本件建物の継続相当賃料額を算定するに当たって賃貸事例比較法を直接的に採用すると、上記のような本件賃貸借契約の個別事情を反映せず、一審被告にとって不測の事態を招くことになって当事者間の衡平を欠く結果になる。そのため、賃貸事例比較法を直接的に採用することはできない。
さらに、中小企業庁編の経営指標の小売飲食店の売上高に占める支払家賃比率を適用して一審被告の売上額から賃料を算定している点については、現行賃料額を決定するに当たって、このような算定方法を用いたのではないし、上記1認定事実によれば、一審被告としては、本件建物での営業をするに当たって、共同管理費も含めた金額によって採算を検討したものと推測できるから、一審被告の売上高に支払賃料比率を乗じて賃料額を算定するという手法を採用することはできない。
以上のように、本件にあっては賃料増額事由の中核となるべき経済・社会的要因に基本的な変化が生じていないのに、乙山鑑定が、差額配分法、賃貸事例比較法を採用し、支払家賃比率を参考に両試算賃料の開差を調整する手法を採用し、一方、現行賃料の合意後の経済・社会的要因をもっとも如実に反映するスライド法を考慮しなかったのは、契約当事者間に、賃借人の意向を容れて現行賃料が他のテナントよりも著しく低く設定され、本件増額請求時には賃料を他のテナントの水準まで引き上げるという合意がなされたことを前提としており、当裁判所がその前提をそのまま採用できないことは記述のとおりであるから、現行賃料の合意時から本件増額請求時までの経済・社会的要因の推移を捨象し、現行賃料の倍額を超える賃料をもって適正賃料とする乙山鑑定を採用することはできない。
(2) 丙川鑑定について
丙川鑑定(乙5)は、本件建物の平成16年2月1日以降の適正賃料額について、差額配分法によると月額88万5000円、スライド法によると月額54万9000円になるとし、スライド法を重視して月額61万6000円と評価している。しかしながら、丙川鑑定がスライド法を重視したのは、差額配分法による経済賃料と現行賃料との差額には共同管理費のうちの実質賃料部分が反映されていないという認識に基づくものであると認められるところ、上記3認定説示のとおり、本件建物の共同管理費の大部分が賃料であるとは認められないから、この点を理由にスライド法による試算賃料に偏した調整をなした丙川鑑定を採用することはできない。
(3) 甲野鑑定について
ア 甲野鑑定は、本件建物の平成16年2月1日時点での適正賃料額について、差額配分法によると月額97万3479円、スライド法によると月額54万6437円、利回り法によると月額58万3047円になり、賃貸事例比較法については直接的に適用ができないとした上で、各評価方式による各試算額を8対1対1の割合として、月額89万2000円と評価している。
イ 甲野鑑定が賃貸事例比較法を直接的に適用していない点については、上記(1)に認定説示した諸事情に照らして合理性があるといえる。
甲野鑑定の差額配分法による賃料の試算過程は、特に不合理な点はなく、差額配分比につき折半法を採用している点も、上記のとおり、借主である一審被告も本件ビル全体の維持管理費用を相当負担していることを考慮すれば、衡平の原則に適うものといえる。
また、甲野鑑定は、スライド指数について、大阪市の消費者物価総合指数と株式会社ベータ調査によるB・A地区の事務所の平均実質賃料推移統計を1対2の割合で加重平均して求めている。
この点、一審原告は、これらの統計数値は、本件建物のような高度商業地に存在する百貨店に隣接した大店舗等に関する統計数値でないので、これらによって変動率を求めるのは不当であり、そもそも本件建物のような高度商業地にある商業施設の継続賃料についてスライド法を適用することは不合理である旨主張する。確かに、スライド法における変動率は、現行賃料を定めた時点から賃料改定時点までの間における経済情勢等の変化に即応する変動分を表すものであり、変動率を求める場合の各種指数は、対象不動産の地域性、用途等の特性を反映したものである必要はあるが、他方で、それを過度に要求すると用いるべき統計資料が存在しないことになる。スライド法は、現行賃料を合意した時点以降の経済状況を反映させて継続賃料を算定するものであり、上記4認定説示のとおり、本件増額請求による相当賃料額を判断するに当たっては、現行賃料が合意されてから賃料を増額する要因となる経済事情の変動がないことを十分考慮する必要があり、これからするとスライド法を適用する合理性は否定できないところ、甲野鑑定で用いた統計数値は、可能な限り本件建物の特性を反映したものといえ、ほかに、甲野鑑定のスライド法による賃料試算過程に不合理な点はない。
ところで、甲野鑑定は、利回り法について、継続賃料利回りを本件賃貸借契約締結当時の本件建物の基礎価額に対する純賃料の割合として0.53%としているところ、一審原告は、商業施設の継続賃料利回りとして極めて低く、不合理である旨主張している。
確かに、継続賃料利回りが0.53%というのは、商業施設の利回りとしては考え難く、これは、現行賃料額が本件建物の経済価値を反映しない低水準の賃料額であったことに起因するものであり、スライド法によって本件賃貸借契約の個別事情を反映することができることを考慮すると、継続賃料利回りを本件賃貸借契約締結当時の本件建物の基礎価額に対する純賃料の割合のみによって算定することには疑問がある。不動産鑑定評価基準においても、継続賃料利回りは、現行賃料を定めた時点における基礎価格に対する純賃料の割合を標準とし、契約締結時及びその後の各賃料改訂時の利回り、基礎価格の変動の程度、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における対象不動産と類似の不動産の賃貸借等の事例又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借等の事例における利回りを総合的に比較考量して求めるものとされているから、本件ビルの他のテナントの賃貸事例や高度商業地の賃貸事例の利回りを考慮する必要性があり、その意味で甲野鑑定の継続賃料利回りは採用できない。そして、高度商業地域の賃貸事例の利回りが6%程度であること(甲9)に加えて本件賃貸借契約締結時点からの本件建物の基礎価格が25%程度減価していること(鑑定の結果)を総合考慮すると、継続賃料利回りを2%と認めるのが相当であり、これによって試算すると、月額79万2692円になる。
ウ 甲野鑑定は、差額配分法、スライド法、利回り法の比率を8対1対1の割合で加重平均して本件建物の平成16年2月1日時点の賃料額を評価しているが、その理由として述べるところは、現行の賃料額が適正でないということに集約される。
確かに、本件建物の現行賃料額は、当時の本件ビルの他のテナントと比較しても相当低い水準であり、現に差額配分法による本件建物の試算額や現行賃料を定めた時点における基礎価格に対する純賃料の割合が0.53%であることなどを考慮しても、現行賃料額が本件建物の経済価値を反映した賃料水準を下回るものであったことは否定できない。
しかしながら、借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求においての相当賃料額を判断するに当たっては、直近合意賃料を基にして、それ以降の同項所定の経済事情の変動等のほか、賃貸借契約の締結経緯、賃料額決定の要素とした事情等の諸般の事情を総合的に考慮すべきであるところ、現行賃料を合意する際、一審被告には本件ビルの他のテナントの賃料相場の認識がなく、一審原告と一審被告との間に3年後に他のテナントの賃料水準に改訂するという認識が一致していたわけではなかったこと、現行賃料を合意した後に賃料の増額要因となるような経済事情の変動がないことを総合考慮すると、現行の賃料額が本件建物の経済価値を反映した賃料水準を下回るという理由で、差額配分法を重視するということは相当ではなく、本件建物の経済価値を反映した賃料水準にするのは、今後の経済情勢の変動を踏まえて、段階的に行われるべきものと解される。
差額配分法、スライド法、利回り法は、継続賃料を算定するに当たってそれぞれ長所と短所を有するところ、本件増額請求による本件建物の相当賃料額をめぐる上記の諸事情を総合すると、各方式による試算額をほぼ均等に考慮するのが相当である。
以上によれば、本件建物の平成16年2月1日以降の相当賃料額を、上記の各試算額のほぼ平均値である1坪当たり月額8000円(月額77万8400円)と認めるのが相当である。
6 以上によれば、一審原告の請求は、本件建物の平成16年2月1日以降の賃料が月額77万8400円であることの確認を求め、これと現行賃料との差額の支払及び差額分に対する年1割の割合による利息の支払を求める限度(一審原告の当審における拡張部分を含めて)で理由があるが、その余は理由がなく、これと結論を一部異にする原判決は相当でないから、一審被告の控訴は一部理由があり、一審原告の控訴は理由がない。なお、仮執行宣言については、相当でないのでこれを付さない。
よって主文のとおり判決する。 第6民事部 (裁判長裁判官 渡邉安一 裁判官 安達嗣雄 裁判官 明石万起子)
解決の方法を提案します。そのためには、情報が必要になります。その情報を「書き込む用紙」を送付するのでご記入の上ご返送ください。届き次第、具体的な解決方法を無料で提案します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの名前ではなく 「6161.jp」で郵送いたします。